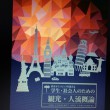『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
人口、地域、, 人流 観光 ツーリズム ツーリスト, 出版・講義資料
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人
祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにされたのは、農耕より1500年前に定住がはじまっていた。
興味深いことに最近まで定住生活を送っていた狩猟採集民がいる。アメリカインデアンのクワキウトルやヌートカである。
定住が促した農耕と人口増加
麦類や稲の農耕起源地での調査 栽培種が現れてから栽培種だけになるまでに3000年
p.140 奴隷という階層
奴隷制社会とは、総人口の20%以上が奴隷になる社会、最初に古代ギリシャ、ローマ 畜力だけではなく奴隷の労働力を利用
西ローマ帝国が崩壊した5世紀ころ、奴隷の確保が困難になり、奴隷の多くが「小作人」に相当するコロヌスと呼ばれる階層に移行 中世ヨーロッパの農奴の起源になった
水田稲作のアジア 奴隷が農耕の主たる労働力にはならず、水田稲作には家族の労働力が投入。奴隷への依存度は低かった
p.142 感染症のリスク
病原体も生物 感染した個体を殺さない、長い進化の歴史がある。
狩猟採集民族の間は、感染症がごくわずか。人が定住を始めてから感染症に罹患するリスクが高まった
人がかかる感染症の多くは動物由来 結核とマラリア ローマ帝国の天然痘は500万人死亡
p.160 二回の人口循環
第一の人口循環 人口が急増したのち、停滞減少に向かった 秦王朝、ローマ帝国が始まるころから急増。停滞の原因ははっきりしないが、地球規模での気温の低下。地球は3世紀から5世紀にかけてわずかに寒冷
中世の人口循環 加速が始まったのが1000年頃、減少は1200年代で1400年頃に終焉
後半 技術の大衆化 戦争と感染症の大規模化
p.195 人口転換 18世紀に欧州の国々で 出生率と死亡率の大きな変化 イギリスに始まり1930年代にはほぼ終結
地球の人口支持率 環境収容力 数理生物学者 ジョエルコーエン「地球は何人の人間を支えられるか」
関連記事
-

-
ハワイ文化 ハワイアンダンス、アロハシャツ
. ルーツは「ポリネシアの移動」にある ハワイアンの先祖は、もともとタヒチやマルキーズ諸島などから
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-

-
概念「「楽しみ」のための旅」と字句「観光」の遭遇 Encounter of the concept “Travel for pleasure” and the Japanese word “KANKO(観光)”(日本観光研究学会 2016年度秋期大会論文掲載予定原稿)
「「楽しみ」のための旅」概念を表現する字句が、いつごろから発生し、どのように変化していったかを、「「
-

-
用語「物流」と用語「人流」の誕生経緯
平成26年度後期の帝京平成大学の授業で「物流論」を担当しています。偶然私にお鉢が回ってきたのですが、
-

-
「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpyPBMJ
-
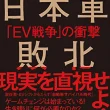
-
『日本車敗北』村沢義久著 アマゾンの手厳しい書評
車の将来の議論の前提に、地球温暖化への見解 ガソリン車 電気自動車 エンジンではな
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-
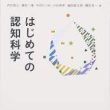
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-

-
人間ってなんなの?:チンパンジーの4年戦争【 進化論 / 科学 / 人 類 】タンザニア
グドール 道具を使うチンパンジーを発見 ジェーン・グドール(Dame Jane Morris Go