伝統論議 蓮池薫『私が見た「韓国歴史ドラマ」の舞台と今』
公開日:
:
最終更新日:2023/05/23
伝統・伝承(嘘も含めて), 観光資源
〇 蓮池氏の著作
「現代にも、脈打つ檀君の思想、古朝鮮の魂』などをよむと、南北共通の教育があることが理解できる
p.86 「住」
ドラマを見ると床下オンドルになっていない。床暖房なら靴履きで入ったり、いすに腰掛けたりしていない。
宮殿では部屋の中でも靴を履き、立式生活をしていたようだ。一説には、高句麗時代に寝室だけ靴を脱いで入るオンドルがあったともいわれている。・・・一日中オンドルの上で暮らす生活は、遠く朝鮮時代になってから普及したという
〇 相撲 女人禁制の伝統の嘘
女性が堂々と土俵に上がり、相撲を取る時代があった--。戦後まで全国で興行していた女相撲を題材にした映画「菊とギロチン」が7日公開され、話題になっている。土俵の「女人禁制」の是非が議論となっているが、監督した瀬々(ぜぜ)敬久さん(58)は「(日本相撲協会が主催する)大相撲が相撲の全てではない。映画を通じて、多様な相撲があることを知ってほしい」と話している。
https://mainichi.jp/articles/20180717/k00/00e/040/234000c?fm=mnm
〇 ついでであるが
祭りも伝統は少ない。つまり農業と祭礼は密接な間、関係があったが、農業が変質したので、伝統的な祭礼はなく、観光祭礼に変質し、人集めが重要になったのである。
騒動になっている阿波踊りも名称は新しい
「奇抜極まる阿波の盆踊り」と説明がある。「阿波踊り」の名称がさほど古い物でなく近年流布したことがわかる。
阿波おどりという名称は徳島県内の各地で行われてきた盂蘭盆の踊りの通称であり、昭和初期からそう呼ばれるようになった。この名称は日本画家・林鼓浪が徳島商工会議所(当時は商業会議所)に提案したものとされる。
関連記事
-

-
『「食べること」の進化史』石川伸一著 フードツーリズム研究者には必読の耳の痛い書
食べ物はメディアである 予測は難しい 無人オフィスもサイバー観光もリアルを凌駕できていない
-

-
『カジノの歴史と文化』佐伯英隆著
IRという言葉の曖昧さ p.198 シンガポールにしても、世界から観光客を集める手法として、
-

-
歴史は後から作られる 『「維新革命」への道』『キャスターという仕事』『明治維新という過ち』を読んで
国谷裕子の岩波新書「キャスターという仕事」をようやく、図書館で借りることができた。人気があるのであろ
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 フィリピンセブ島刑務所の囚人ダンス
フィリピンセブ島観光・旅行【決定版】絶対にするべき39スポット&アクティビティ http://ce
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 資料 ハルハ川戦争 戦跡観光資源
https://youtu.be/RijLPLzz5oU 中国とロシア
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 宇宙旅行
https://youtu.be/KpGnwLiTYj8 https://youtu.be/a
-

-
ヒトラー肝いりで建造の世界最大のホテル・プローラ
観光政策というより、福祉政策なのかもしれませんが、現代なら民業圧迫という声が出るでしょう。
-
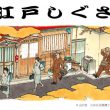
-
伝統は後から創られる 『江戸しぐさの正体』 原田実著
本書の紹介は次のとおりである。 「「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である。本書は


