伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗教」を借りた。
著者は1972年東大文学部卒とあるから、全くの同世代。考え方を形成する時代背景は私と全く同じはずと思い読んでみたが、記述内容にも全く同感させられた。
乱世の戦国時代を宗教に特化して考察する珍しい本である。
観光資源論でいつも、歴史や伝統は後から作られると講義(観光論で教えるから、否定的に言うのではなく、今からでも観光資源はいくらでも作れるということを強調している)しているが、本書でも材料をたくさん得ることとなった。
現在でも、選挙の時には神社で出陣式をするし、新病院を建設するときには地鎮祭を行う。現に私がそうであった。
神を信じる、信じないに関わらず、行わないとおさまりが悪いのは戦国時代でも同じであった。
ましてや宗教と呪術と技術の未分離のものが多い時代であるからなおさらである。
その背景にある「神」を抱いて戦うのであるから、著者は川中島の合戦も一種の宗教戦争だったという。
そう思えば、中東でスンニ派とシーア派が宗教の衣を着て戦っているのも理解ができる。戦国大名は戦場での勝利を神仏に祈り、信長も例外ではなかった。
拡張主義の武田信玄、合理的無神論者の織田信長といった通説が、見事に覆されている(「合理主義者として喧伝され、ルイス・フロイスが活写する在来の日本の信仰には無縁ともいえる信長像を、実態から大きくかけ離れていると考えざるを得ない」「信長がキリシタンに好意的であったかも確実な資料は日本側資料には見当たらない」)。
「一向一揆」についてもこれから一般人の印象が大きく変わる可能性があることを予感させてくれた。
「一向一揆」と言う用語自体が、江戸時代になってから浄土真宗本願寺派が東本願寺派(大谷派)と西本願寺派(本願寺派)と分裂する中で誕生した用語であり、戦国時代の最中には他の土一揆と同じ扱いだったとある。
鎌倉幕府という言葉が明治になって造語されたこととあまり変わりはない。
つまり一向宗徒が興した一揆は一向宗の教祖の政治的な都合によって興された物であり「宗教活動」と言うよりは「政治活動」であるというのである。
これまで私は、一向宗ニアリーイコール浄土真宗だと思っていたが、そうではなかった。
一向宗とは、死霊を供養する力をもつと認識された念仏の呪力を信じる人々が一向宗と自称したからであり、この宗教的色彩のある民間宗教を後日、一向宗と称したのであるとのことである。
すなわち、親鸞の教えが一向宗なのではないとのことである。本願寺は基本的には諸大名、他宗派と友好関係を保っていた。
従って、ドイツ農民戦争時のマルチンルターも一向一揆時の蓮如も最終的には体制側につき民衆を裏切ったのである。
南ドイツではプロティスタントが普及しないのであるが、逆に加賀では浄土真宗が普及したのは面白い。
相良氏、島津氏領など南九州では、一向宗が江戸時代も禁止され続けたそうだが、それは山伏、祝(はふり)、陰陽師など呪術者の取り締まりを目的としたものだったからだそうだ。
このように「一向一揆」は発生していた当時は真宗勢力の政治行動の一種と考えるのが妥当で、真宗の独立的な信仰世界への希求がこれをなした、とするのは江戸時代に創作された神話だと本書はいう。
あるいは、織田信長を苛烈な宗教弾圧者とみなす見解があるが、これも眉唾もので、すべての神仏の帰一と諸宗派のバランスよい共存を理想とした戦国人のひとりであった信長もまた、武力の制圧には積極的でも信仰の抑圧には消極的であったし、宗派間の無駄な争いである宗論を禁じたりと、意外にも穏当な人であったことが示唆されている。
戦乱の時代、日本には大名から庶民、インテリ禅僧から真宗門徒にまでゆるやかに共有されている「天道」が存在した。人間の理解を超えたもの(天道)があるとする観念が日本人にあったのである。他者に自らの信仰を強要すべきではないとする考え方にもつながるのである。神仏を分け隔てなく等しく尊崇していくという信仰形式であった。それはすべての神仏を包括する観念であり、諸宗派・諸信仰は同じだから、他者の信仰は攻撃しないという考え方となり、他宗教、他宗派に攻撃的な宗教は衰退し、禁止されていく。それが江戸時代へとつながっていったとしている。どの宗派も基本的には同じものとして考えられていた。
日本を訪れた宣教師たちはこの「天道」の発想に唯一神デウスへの帰依心と近似した感性を見出し、蓮如は全神仏帰一の思想を阿弥陀仏がすべての神仏の存在を代替するという思想に読み替え、戦国大名は諸宗派の横並び的な共存による世俗道徳の安泰を期待した。が、宣教師はそれを許さずキリスト教以外には救いはないと伝道した。そのようにキリスト教のみが排他的な宗教であったゆえに、危険視された。信長も実は仏教に特別厳しかったわけではないと、ふつう言われていることとは違った見方である。
中世の社寺はアジール(避難所)の性格があった。このものの見方は、公家、武家とともに社寺が存在したとする黒田俊雄説に共通する。
しかし、江戸時代になってからは寺社仏閣の力は弱体化したとされているが、実際は「駆け込み寺」など罪人保護者としての役割は衰えてなかったとするところは初めて認識させられた。
鎌倉の縁切り寺は特殊なものではなかったということが理解できた。
関連記事
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
「米中関係の行方と日本に及ぼす影響」高原明生 学士會会報No.939 pp26-37
金日成も金正日も金正恩も「朝鮮半島統一後も在韓米軍はいてもよい」と述べたこと 中国支配を恐れてい
-
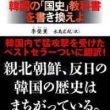
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-
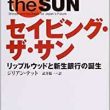
-
『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド
バブル期に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はア
-

-
『外国人労働者をどう受け入れるか』NHK取材班を読んで
日本とアジアの賃金格差は年々縮まり上海などの大都市は日本の田舎を凌駕している。そうした時代を読み違え
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
運輸省(航空局監理部長)VS東亜国内航空(田中勇)のエピソード等
https://www.youtube.com/watch?v=flZz_Li7om8
-

-
『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハー

