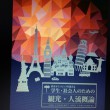AIとの論争 住むと泊まる
公開日:
:
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
関連記事
-

-
Future Direction of Tourism Policy Studies in Japan
In the theory of tourism policy studies, I would l
-

-
🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅(後日談) 忘れ物の入手とエアセネガルへの返金請求処理
◎ カンタス航空ラウンジでの忘れ物 カンタス航空ラウンジに、子供たちからのプレゼントであるポシェッ
-

-
福田村事件 霧社事件
https://youtu.be/s-zWKhVIBow 福田村事件(ふくだむらじけん)は、1
-

-
動画で考える人流観光学講義(開志 )2024 1 22 最終 外国人労働者とAI
観光ビジネスにおいて、外国人労働者を雇用することについて、どう考えるか、800字から1200字の
-

-
上田卓爾「明治期を主とした「海外観光旅行」について」名古屋外国語大学現代国際学部 紀要第6号2010年3月を読んで
上田氏の資料に基づく考察には鋭いものがあり、観光とTOURISMの関係についての議論を発展させる意味
-

-
The basic viewpoint of discussing Human Logistics and Tourism
In the process of studying Tourism Studies, consid
-

-
観光学研究者へのお願い 字句「観光」と字句「tourist」の今後の研究課題
これまで、日本語としての字句「観光」の語源等についての分析は、上田卓爾氏等が発表した論文があり、かな
-

-
『海外旅行の誕生』有山輝雄著の記述から見る白人崇拝思想
表記図書を久しぶりに読み直してみた。学術書ではないから、読みやすい。専門家でもないので、観光や旅行
-

-
MaaSのおとし所 「両備運輸の思い上がり」「JERONタクシーが実証実験だという例として出しているが、とんでもない間違い」
チームネクストの総会に参加していくつか私なりに進展があった。 MaaS以外に自動運