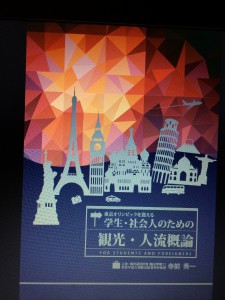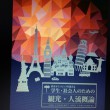東京オリンピックを迎える学生・社会人のための観光・人流概論
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
新しい教科書を出版しました。私はこれまで観光政策論等を中心に出版してきましたが、本書は初めての観光・人流に関する概論書です。本書の構成は、原論、歴史、資源、行動、政策、情報としました。観光・人流に関する全域をほぼカバーできたのではないかと思います。そしてその内容は4つの特徴を持っています。
一つ目は、観光だけでなくヒトの動きにまで拡大して具体的実例を紹介しながら、学生・社会人のため、根本課題をわかりやすく解説しています。そのかわり学術論文ではありませんから、出典等については簡略化して取り扱っています。
二つ目はホームページとの連動性です。観光の語源とされる「易経」がありますが、世代によっては易経そのものの解説が必要となってきました。しかし易経の解説をする必要がある世代は、スマホは自由に使いこなせますから、著者のHPである人流・観光研究所のHP(http://www.jinryu.jp)と連動させ、本文中に示した用語を詳しく学びたい者に、更に詳しく解説を行うとともに、陳腐化するデータ等もホームページに掲示し最新のものを提供できるようにしています。また、出典や参考文献等もHPにおいて詳しく提示しています。もちろんこれらは今後とも適宜アップデートする予定です。
三つ目は学生の他、社会人、外国人を対象にしていることです。プロの観光関係ビジネスマンや観光関係行政マンにもしっかりと原点に立ち返って問題意識を持ってもらえるように記述しているつもりです。特にパッケージ・ツアー料金が認可、届出料金とは無関係に決定できる仕組みについては、プロの観光人にも問題意識を持ってもらえるように記述してあります。また、日本の観光制度等については専門家からの海外への発信が少なかったこともあり、英語版を人流観光研究所HP及びacademia.eduのHPに公開する形で挑戦しました(https://independent.academia.edu/ShuichiTeramae)。翻訳ソフトを活用しましたが、ネイティヴのチェックを受けていませんので不十分な点があると思われます。ご指摘を頂ければ随時訂正してゆきたいと思っています。
四つ目はYubi-Taxi等の政策提言をしていることです。通常の教科書では政策批判はしていても政策提言までは行っていません。なお、Wikipediaは、医学的治療法等に関する記述について、内容的に批判を受けているようですが、観光学に関する項目に関するWikipediaの記述についても、同様と思われます。観光研究者のWikipediaの記述に関する対応ぶりを垣間見ましたが、このままでは観光学の進展が期待できそうに思えません。ただ医学と異なり害がないだけです。本書が刺激となってWikipediaの記述にも進展がみられることを期待しています。
関連記事
-
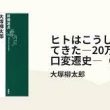
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ
-

-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market ⑩
Ⅸ Future direction of human flows and sightseeing
-

-
AI研究者と俳人 人はなぜ俳句を詠むのか amazon書評
AIが俳句を「終わらせる」可能性は、これまでの「人間による創作」という前提を破壊するという意味では「
-
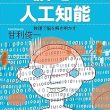
-
甘利俊一 AI時代の到来 その仕組みと新しい文明 学士会会報974 2025年Ⅴ
4億年前、情報処理に特化した脳神経系の器官が生まれた 物理学の法則は今の宇宙に貫徹。生命の法則
-

-
読売新聞、朝日新聞記事に見る字句「ツーリズム」「観光」の用例
読売新聞の記事データベース「ヨミダス」及び朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱ」を活用して「ツーリスト
-
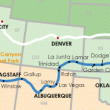
-
ニューメキシコ レッドロック
サウスウェストチーフの車窓からの風景で、深紅のサメと呼ばれるところは、どこですか
-

-
🌍🎒2023夏 シニアバックパッカーの旅 2023年8月24日~25日 イスファハン
FACEBOOK 24日夕刻ホテルにチェックイン。一休み後暗くなってから、スィーオセ橋に行く。
-

-
『諳厄利亜大成』に見る、観光関連字句
諳厄利亜大成はわが国初の英語辞典 1827年のものであり、tour、tourism、hotelは現
-

-
AIとの論争 住むと泊まる
AIさん、質問します。世間では民泊の規制強化が騒がれていますが、そもそも、住むと泊ま
- PREV
- 用語「物流」と用語「人流」の誕生経緯
- NEXT
- お詫び