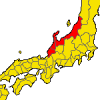用語「物流」と用語「人流」の誕生経緯
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
平成26年度後期の帝京平成大学の授業で「物流論」を担当しています。偶然私にお鉢が回ってきたのですが、ホームページの私の著作物の欄をご覧いただければおわかりいただけるように、私が初めて単行本として出版したものが「経済構造改革と物流」です。閣議決定した物流施策大綱を中心に記述してありますが、すでに20年以上も前のことです。
今回「人流」論議を始めて、改めて用語「物流」の誕生経緯をおさらいしてみました。行政用語として物流については運輸省の組織改正時に貨物流通局を担当しましたのでかなり詳しいつもりでしたが、一般用語としての物流については、初めて勉強させていただくこともありました。この方面に詳しい谷利亨氏にいただいた解説文をHPに掲示してあります(パスワード保護つき)。
経済先進国アメリカでは既に1920年代にphysical distribution の概念が生まれ、戦後高度成長期に日本にも紹介されたのですが、当初は日本に問題意識がないところから日本人には理解できず、適当な邦訳もなかったのです。しかし日本経済もその必要性が高まるとともに、次第に「物的流通」という言葉に収斂してゆきました。一方本家のアメリカではphysical distribution ではなく調達段階も含めたLogistics概念が用いられるように変化してゆきました。Logisticsは軍隊用語ですから、これに対してBusiness Logisticsとも称されたようですが、次第にLogistics単独で用いられ、Businessがつく使用はすたれたようです。
日本ではphysical distributionの概念導入とLogistics概念導入の時期的差異があまりなく、前者が次第に使われなくなっていきましたが、両者の違いを強調することはありませんでした。「物的流通」は、日本語特有の言葉の短縮使用の変化から次第に「物流」へと変化してゆきましたが、同時にLogisticsの邦訳としても用いられるようになりました。この点の、 physical distributionとLogisticsを明確に区分して、邦訳も「物的流通」と「物流」を使い分けたのか、物的流通の短縮形として物流になっていったのかは不明確ですから、研究者が明らかにされるでしょう。
Logistics概念は、兵士の輸送等必ずしも貨物に限定されたものではありませんでしたが、physical distribution の後継語としてLogisticsが使用されるようになると、人的要素が少なくとも研究者の頭からは消滅してしまいました。
ここであらためて、観光に変わる概念として「人流」概念を提唱し、その英訳を Human Logisticsとしている私としては、原語のLogisticsが貨物に限定されていなかったことを強調せざるを得ないことは御理解いただけるでしょう。日本では単純にLogisticsを物流と訳していますが、もともとLogisticsは人的要素を排除していないのです。従って物流は本来non-Human Logistics と訳されるべきであったのでしょう。
関連記事
-

-
観光概論にみる字句「観光」の説明
有栖川図書館で観光の書籍を読む。大橋昭一氏の関係する書籍が開架式の棚に何冊かあり読む。 大橋著『
-

-
「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpyPBMJ
-
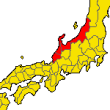
-
越前が、越中・越後と接していないのはなぜですか?
https://jp.quora.com/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E3%81%8C-%
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源 芸術と人工知能
第3回AI美芸研】「芸術と人工知能-人工知能に、人工的な美を追求させることは如何 にして可能か」三宅
-

-
Participation in press tour for Jeju (preliminary knowledge)
The international tourism situation of Jeju is cha
-
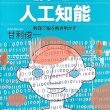
-
『脳・心・人工知能』甘利俊一著講談社BLUEBACKS メモ
AIの基本技術は深層学習とそれに付随して強化学習 そのあと出現した生成AI
-

-
Touristic problem of Jeju island richer than Okinawa and Kyushu held ~ Participation in press tour ~
It was a short time from November 2 to 4, but I pa
-

-
中国新疆ウイグル自治区カシュガルからパキスタンのハンザ地区を通過してパキスタンの空港から日本に戻るルート
中国新疆ウイグル自治区カシュガルからパキスタンのハンザ地区を通過してパキスタンの空港から日本に戻るル