語源論の終焉~概念「観光」と字句「観光」~
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
27年度帝京平成大学紀要に原稿を入稿した。昨年度に続き概念「観光」に関連するテーマであるが、今回は国内観光行政の誕生と発展にウェイトおいた。昨年度の論文は人流観光研究所HPに掲載してあるが、今年度の分は発行予定日が来年3月であるので、しばらく公開は塩漬けになる。HPにはパスワード付きで掲載してあるから、意見がある研究者にはパスワードを連絡してもかまわないと思っているから申し出てほしい。
概念「観光」が日本でいつ頃発生したのかという命題は、概念「観光」の内容をはっきりさせたうえでないと決められない。その概念「観光」はそれを社会が必要とする理由が明確でないと内容は決められないのは当然であろう。
研究者の中には17世紀より前の資料の中に字句「観光」を発見し観光を論じる場合があるが、漢字の組合せであるから「光」を「観る」という組み合わせが文章の中に出てきて不思議ではない。いずれ古文書の高速スキャナーが開発されれば、瞬時に検索できるようになる。重要なのは字句の発見ではなく概念の発見なのであろう。
日本で概念「観光」が発生した時期は未だ定説はない。貴族が楽しみのために旅行した事例はそれこそ万葉集の時代にも存在した。貴族の旅までも概念「観光」に含まれるとしたら、概念「観光」の社会的必要性は何かということになる。概念「Tourism」に関し通説は大衆化を前提としているから、貴族の楽しみの旅まで含めることは混乱のもととなる。弘法大師の修行の旅も同様である。日本で概念「観光」が明示的に使用されるようになったのは御蔭参りの頃からではないかと思っているが、私は専門家でもなく、またそれが本題ではない。
楽しみのための旅が大衆化し、そのための産業が発生したことにより、概念が発生したと考えることが素直であると思っている。その場合に概念「観光」をあらわす字句は、当初「観光」ではなく、例えば字句「遊覧」に代表されるものであったのであろうと思っている。それも根拠があっていっているわけではない。古文書の高速スキャナーが開発されるまで、科学的論争はおぼつかないと思っている。
江戸末期から明治期になり、英語の字句「tourist」「tourism」が紹介された。文化が違うから概念も百パーセント一致しないが、次第に概念「観光」と相互にすり寄っていったのではないかと思っている。法令段階で明確にすり寄ったのは1930年国際観光局設置の時期である。ただし厳密にはTouristと観光がすり寄ったのであり、tourismは明確に認識されていなかった。このことも研究者に混乱を与えている。
この段階で仮説を2つたてた。①概念「観光」ははじめ越境概念が含まれていたが次第に内外無差別になっていったということ②インバウンド概念から始まり次第にアウトバウンド概念が強くなっていったこと の二つである。その前提には大衆化された「楽しみのための旅」を産業として認識する必要性が生まれたことがあると思っている。
言葉の意味であるから、実際にどのようなコンテクストで使用されていたかがわからないと判断できないが、新聞記事検索システムの結果では仮説①②が有力であると思っている。言葉の使用頻度の問題であるから認識の差になるかもしれないが。
仮説①につき、字句「観光」国内の移動に使用している例を相当古い時代にまでさかのぼって指摘する者がいる。参考にはなるが、その場合の概念が不明確であり、その時代全体のことがわからないと、単に字句がヒットしたこと位では論じることができないと思っている。古い時代には、近代的な国家、国境という概念すら存在しなかったのではないと思われる。また江戸時代の古文書の3%程度しか印刷物化されていない現状では、全体の字句の使用方法もわからない。
仮説①②は仮説であるが、アプリオリに概念「観光」が存在するとして、その表現を字句「観光」を用いた時期を限られた資料の中から発見しても、仮説の①②の進展には結びつかない。
仮説が仮説でなくなる時期は、AMAZON等が高速スキャナーを駆使して文書の電子化を完成させる時を待たなければ到来しないかもしれない。仮説を論じることには実は本質的な意味はなく、今回は、仮説を論じる過程で国内「観光」政策が発生した時期を明確に認識できたことが大きな成果であった。その成果を帝京平成大学紀要に投稿したので、発行されたら是非読んでもらいたい。
なお、観光に関する語源論は、観光政策に関する限り、1930年に命名者の鉄道省が語源を命名を易経に求めたとしている以上は、易経でいいと思っている。昭和、平成という元号の語源について、命名者の政府が示しているものと異なるものを主張しても実益がないことと同じである。そろそろ終焉の時期ではなかろうか。
注 観光概念を「楽しみのための旅」としているが、海外では、「生殖ツーリズム」「ジハードツーリズム」「シューイサイドツーリズム」と言った用例が散見されるようになった。楽しみという範疇化ではくくりきれない概念ではないかと思われ、tourismの再検討が必要になってきているかもしれない。
関連記事
-

-
AIに聞く ミネアポリス
私はバックパック一つで旅行しますので、移動は簡単です。ミネアポリスでは、ICEで話題になっているとこ
-

-
ロシア人以外の人が北方領土を訪問する場合のロシア政府に対する手続きを教えてください。
国後島や択捉島、極東・沿海地方結ぶ“初のクルーズツアー”をロシア政府
-

-
human geography
TVドラマのエレメンタリーホームズandワトソンのなかで、ホームズがhuman geography
-
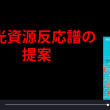
-
AIに聞く、甘利俊一博士の「脳・心・人工知能」を参考にした、『観光資源反応譜』の提案
人流・観光に関する学生用の教科書として、amazonのkindleで『人流・観光学概論』を出版してい
-

-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market (1)⑤
Ⅳ A tourist's longing travel destination for Chine
-

-
🗽🎒2026.4.19 シニアバックパッカー全米全州走破の旅 ハワイ州ホノルル観光編②
パールハーバーとアリゾナ号記念館 所要時間は約2〜3時間。 公式サイトで 事前予約済み Or
-

-
AIに聞く USレールパスによるAMTRAK乗車方法
US Rail Pass(USA Rail Pass)を1月19日に購入済みで、4月20日にロサンゼ
-

-
Future Direction of Tourism Policy Studies in Japan
In the theory of tourism policy studies, I would l
-

-
英和対訳袖珍辞書と観光
先週は都立中央図書館が図書整理のため休館日が続き、ようやく土曜日(6月13日)に閲覧に行くことができ


