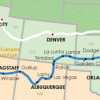観光とツーリズム①
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
「観光」という中国語由来の日本語と「ツーリズム」という西洋語(tourism)由来の日本語が、日本において何時頃から相互に重なるようになってきたのかというテーマがある。「ツーリズム」の語源についてもラテン語、アラム語等3種類あるという学説が欧米で紹介されており、「観光」の語源も易経にあるとされているが、言葉は時代とともに変化するから、江戸期の字句「観光」が今日の字句「観光」と同じ意味であるとは考えられない。漢字の「赤」「青」概念ですら今日の色彩認識は古代等とは変わっているから、語源論も今日の知見のフィルターを通して論じている限界があることになる。
読売新聞及び朝日新聞記事検索を基にした私の現段階での認識では、「ツーリズム」が普通に使用されるようになったのは戦後、しかも近年においてのことではないかと考えているから、「観光」概念は「ツーリズム」ではなく「ツーリスト」を基にして考えないと解明できないのではと思っている。
新聞記事検索によれば「観光」は当初固有名詞に使用されている。「昭和」「明治」等と同じように漢字の組合せよるイメージが中国の古典由来のものであり固有名詞に使用するにはふさわしいものと感じられていたのであろう。
現在の観光の意味には明らかに「(非日常体験を求める)日本人の国内移動に関わるもの」が含まれている。含まれているというより主流である。しかし日本人の国内移動が当初から含まれていたかについては検証が必要である。「内外」無差別に使用されていたという考え方も成立するが、今日的意味での「内外」認識の必要がなかったのかもしれない。いずれにしろ「観光」が国内移動を前提とした「遊覧」と共通の部分を持つようになるには時間が必要であったと思われる。
一つのターニングポイントは「国際観光局」の設立である。国際が使用されたことには論議があったが、同時に国内も概念的に発生するわけである。鉄道省の資料では国際観光事業と国内観光事業を列記しているから、日本人の国内移動に関わるものが含まれ始めたと解釈もできる。しかし、言葉を厳密に使用する法令、組織名であるから、国際観光局が「外客誘致」のために設置された以上、この場合の「国際」観光事業は対外宣伝事業のことをさし、「国内」観光事業は外客のための国内における宿泊施設整備等のことをさしていると考える方が適切であろう。
鉄道省の役人の意識では、「外貨獲得」という政策目的がしっくりこなかったようである。外国人の巾着をねらうという意識があると正直に述べている注1)。従って組織名も「帝国日本の文明を世界に示す」という意識で「観光」を使用したとある。役人出身の私にはよく理解できるところである。博覧会が文化を見せる場であると言う意味で使用し、観光的用例となっているケースは、勿論鉄道省に国際観光局が設置される以前の19世紀から存在した(下記伊藤論文では1895年)。
注1)観光部及び観光庁経験者の本保芳明氏が「転機にある日本観光」(琉球大学大学院観光科学研究科「観光科学」第6号)において、「当時の観光業界の人々における不満の一つは「観光の社会的地位の低さ」であった。政治家の観光への関心は薄く、行政としてのプライオリティはお世辞にも高いとは言えないというのが、観光行政に携わるものとしての実感であった。」「関係者にとって観光の社会的地位の低さは、極めて大きな問題であった。企業モラル、採用等に直結し、政府の支援を得ることを困難にしたからである。また行政レベルでは、政策の優先度を下げ、円滑な政策展開を妨げていた。」と記述している。1930年代の意識と変わらないことがうかがえる。この意識が変化しだしたことは「エリート観光課長の誕生」(高崎経済大学地域政策参照)に記述のとおりである。
では、「(非日常体験を求める)日本人の国内移動に関わるもの」が世の中に存在しなかったのかといえば、そんなことはない。新聞記事検索によっても「遊覧」という用語が明治から現代まで多用されている。時代とともに「観光」が「遊覧」と同種のものとして使用されるようになって行く過程が研究対象になるのであろう。言葉ですから理屈ではなく使用される実態の解明が求められ、その実態もある日突然に意味が変化するというものでもないであろう。
「観光」という用語が普通名詞として使用される事例は、朝日新聞記事検索「聞蔵」によれば1893年10月15日朝刊の「駐馬観光」で、軍人の海外視察における例が初めてである。読売新聞記事検索「ヨミダス」によれば1897年8月18日朝刊に初めて普通名詞の用例として「台湾の生蕃人が内地観光のための上京」に関するものとして登場している。いずれも語源の影響を受けているのであろう。国の光りを見に行く普通名詞「観光」は、当初建前として「遊覧」とは区別して使用されていたと思われる。大橋昭一氏が「観光における平準化傾向(法則)」(『観光学ガイドブック』p.16)と呼んでいるものであるが、私は「日常と非日常の相対化」と呼んでいる。平準化なり、相対化の過程で何時頃から「日本人の国内移動」に関わるもの、遊覧に関わるものが入り込み、市民権を得ていったのか、若手を中心とする研究者により解明してもらえると面白い。鉄道省国際観光局の役人には明らかに観光と遊覧を同義語として世間が既に認識し始めているという意識があったので、わざわざ「国の光を示す」ことを強調したのではないかとも推測される。
この「国の光りを示す」の用例としては、西村捨三農商務次官が1895年行った記念祭協賛会幹事としての挨拶(『京都遷都記念祭紀事巻下』京都市参事会1896年発行p.49)のなかで「此ノ時代祭ヲ観レバ・・・我国ノ光輝ヲ益々発揚スルトヲ得ルナラン・・・外国人ハ非常ノ威ヲナスノミナラス各地ヨリ見物ニ出掛クルモノ続々踝ヲ接スルナラン・・・」と時代祭の構想を語っていることが(伊藤節子「時代祭と観光」『観光研究』p.63 2014年9月30日)に紹介されている。ここでも国の光を外国人に示す意識が表れている。
なお、1907年(明治37年)の文献に皇后陛下の「吉野の御観光」という用例があり、皇族の国内移動に「観光」を使用しているようであるが、これを例外的と見るか一般的と見るかで解釈が分かれる。言葉であるから数量分析が必要である。
○「tourist」が日本語に入ってゆく資料
私は、西洋人が大航海時代以降海外に出かけたとき、宣教師、貿易商、探検家、植民地行政官、船乗り等に加わって、touristに分類される人達も乗り込んでくるようになってきたのではないかと推測している。そのtourist概念はわかりやすかったので、明治になってそのまま「ツーリスト」として輸入されたのではないかと思っている。このことを裏付ける資料となるかは判断のいるところであるが、手近な資料としては中村宏論文(「戦前における国際観光(外客誘致)政策」『神戸学院法学』36巻2号2006年12月)があり、http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/ で読むことができる。ジャパンツーリストビューローの名称について、その専務理事経験者である高久仁乃助氏が『国際観光』8巻2号(1940年)が特集した「国際観光局創立十周年記念座談会」において、「日本観光奨励会」「外客集致局」「観光局」という候補もあったが、英文名(Japan Tourist Bureau)をそのまま「日本名としてもちいるのがいい」ということになったと発言されている。繰り返しになるが、気になるのは「tourist」は外客のみなのかということ、及び何故「tourism」ではなかったのかということである。紹介した中村宏氏は同時に「戦時下における国際観光政策」『神戸学院法学』36巻3・4号2007年4月)も発表されているから参考になる。
○「tourism」の発生
『観光学ガイドブック』p.14の大橋昭一の記述によれば「それまでの富裕層を対象にした旅・旅行は、イギリスでは一般にtravelとよばれていたが、この新しい一般大衆向けの、旅行業者の手配や指示のもとに、旅行客はただ受動的についてゆけばいいようなものは、travelとはいえない。それと区別して、tourismというのが適当という強い声があり、tourismというのが適当という強い声があり、tourismとよぶことが一般化したのである。それは1800年代前半ごろのことであった」となっている。
なお、Wikipediaでは以下のとおりとなっている
「Tourism is commonly associated with international travel, but may also refer to travel to another place within the same country.」となっている。何故国際が通常なのか?
In 1936, the League of Nations defined a foreign tourist as “someone traveling abroad for at least twenty-four hours“. Its successor, the United Nations, amended this definition in 1945, by including a maximum stay of six months.[9]
関連記事
-

-
中国・パキスタン国境越え動画
中国・パキスタン国境越え動画 https://www.youtube.com/watch?v=
-

-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market ⑧
Ⅶ Alaska and Hawaii ~ High latitude tourist site
-

-
AIとの論争 住むと泊まる
AIさん、質問します。世間では民泊の規制強化が騒がれていますが、そもそも、住むと泊ま
-

-
「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpyPBMJ
-

-
よそ者としての「tourist」の語感
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-44312894
-

-
『海外旅行の誕生』有山輝雄著の記述から見る白人崇拝思想
表記図書を久しぶりに読み直してみた。学術書ではないから、読みやすい。専門家でもないので、観光や旅行
-

-
GOTOトラベル政策への総括をAIジェミニに聞く
設問 コロナ時期に、日本政府はGotoトラベル政策を展開しました。私は人流観光ビジネス救済には
-

-
Encounter of Japanese word“観光”and English word“tourist” ~ the birth and development of domestic tourism policy in Japan ~
1 Outbreak of the concept of movement of people
- PREV
- 読売新聞、朝日新聞記事に見る字句「ツーリズム」「観光」の用例
- NEXT
- 観光とツーリズム②