観光とツーリズム②
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
今日われわれが使用している「観光」概念の誕生には日常と非日常の存在が前提となり、日常の前提には定住が前提となる。「ツーリスト」概念が欧米から入り込んできた明治期において、日本列島にどの程度定住社会が成立していたかを柳田国男に代表される民俗学から探ってみたいと思う。また、衣食住の変化を理解することにより、ホテルと旅館、和食といった観光学における重要なキーワードの発生過程も理解してみたいと思っている。
○柳田国男に見る「観光」「遊覧」と「人流」
まず、柳田国男『明治大正史』世相編(1931年朝日新聞社)を読む限り字句「観光」と字句「遊覧」は使い分けられているようである。以下用例を掲載しておく。
「都市はいつまでもどちらつかずの住民を持って充ちていたのである。盆と正月はついこの間まで「帰省客」が大部分だった。そしてその「帰省先」は農村であった。」(p.162)「漂泊者の歴史は日本では驚くほど古く始まっている」「現在のわれわれはおおむね住所を持ち定住しているが、住所不定という人々はかなり多かった。「ホームレス」というのは新世相のようにように見えるがその淵源は古いのである。」(p.211 )「出稼ぎの動機は農村の動揺から起こったものではない」「日本の農村は常識に反して、昔から兼業農家が中心だった。出稼ぎという言葉は決して農村の悲惨を意味するのではなく、社会の総労働力の自主的な配分の仕組みなのである。現在では農作業が合理化されたから、農繁期だけ村に帰る、という「逆出稼ぎ」も出現している」(p.323 )
なお、「明治34年の6月に東京では跣足を禁止した」(p.39)の記述はホテルと旅館に違いを「靴を脱ぐ」ことくらいにしか違いが見いだせなっている現代において、靴をはくという習慣がいつから始まり、畳の発達とともにどう変化していったかを分析する必要性をも惹起させるヒントなる記述である。
第5章「故郷異郷」においての記述 「今日になると信じがたいような歴史だが、いわゆる内地雑居の問題が四十何年前に論じられた頃には、国民の警戒は非常なものであった。雑居をしていたために滅びるような弱い国なら、このままいたところで永く持たないというたぐいの、やや過激な意見さえ飛び出して、やっと決断は着いたのである。ところが我々が予想していたほどには、異人雑居はやってこなかった。今ごろまだ観光局を国で造って、ホテルの客を誘引しようというありさまである。」(p.211 )外客誘致以前に外国人の国内移動を制限していた時期が明治時代に存在したことを充分に理解しておかなければならない。
第6章「新交通と文化輸送車」三「汽車の巡礼本位」においての記述 「なくては済まなかった一通りの幹線が敷設し終わると、次に現れたる各地方の均霑努力は、大抵は他の地の前例を参酌して、この未来の新旅人の数を予算して居る。いわゆる資源の開発が果たして計画の通りのであったものの多いと同様に、人が釣りだされて遊覧の客となったことも、また非常なる大きな数であった。」(p.199 )「巡礼本位は日本の交通機関を、いくぶんか不経済なものにしていることも事実である。年内ある季節の溢れるような乗客のために、用意せられた設備が半季は遊んで居る。ことに北陸・奥羽の雪深い地方では、利用の激減と維持費の増加のために、二重の食い込みを予算する必要があるのであった。」(p.201)「日本は初めて真冬でも共同し得る国となったのである。・・・主としては汽車の大きな効果であった。しかも同時にまた遊覧団体のきままなる移動だけでは、まだ国内の各地方を接近させることができぬことも、考えられてきたのであった。」(p.203)四 「水路の変化」「汽車が毎日の作業として、ひどい山間の交通で開拓しているうちに、水運の方の不信用はかえって少しばかり昔よりも加わってきた。今まで大きな船の遠方通いにのみ熱中して、近くを忘れていたという欠点も確かにあるが、一つには海も荒かったのである。」
なお、大正期の建議の中に「鉄道開通(参宮線のこと)セシヨリ漸次内外観光者ノ来遊増加セル」及び「内外人士ノ遊覧、観光ノ目的物ト為リ或ハ師弟ノ教育・・・」という表現があるようであり、柳田説の例外が存在する可能性がある。
○国内旅行に観光が用いられるようになる過程
柳田国男の「巡礼本位」の鉄道整備思想の影響を受けていると思われる宇田正氏による『鉄道日本文化史考』(思文閣出版2007年)の中の「わが国の鉄道史と「観光」の理念ー巡礼・遊覧・観光」(pp173-185)に次のような記述がある。
「「観光」という言葉がこのときわが国鉄道業界で初めて用いられ、しかもそれは「国際」という限定をともなうものであった」「観光という旅行目的が当時のわが国においてはもっぱら外国人旅行者に固有のものと意識されていたことがうかがえる」(p.182)「それらの旅行はまさしく「巡礼」習俗に根ざす「遊覧」「回遊」「名所旧跡めぐり」という字句表現になっている。それが昭和10年代に入ると、国内旅行でありながら「観光」の字句表現が用いられようになるのが興味ふかい。こうして日本人の旅行文化にも「観光」という異文化間交流的なイメージが定着し、広く海外に向けて国際的に開けてゆくかに見えたが、やがて戦争の強化と敗戦によってその流れは中断された。」(pp184-85)
宇田氏の提示する国内旅行でありながら観光の字句表現が用いられるようになった例には「加賀江沼観光御案内」(観光社出版部、1935年)「観光の和歌山」(1935年)「愛知の毛織と観光」(1937年)があり、溝口周道氏が提示する用例(氏のブログ)には『観光之宮城県図絵』(1938年)」(発行者 佐々木武 印刷所 京都日出新聞社 発行所 くろふね図案社)がある。この「巻頭に」の中に、「・・・名実ともに真の 『御大典記念京都観光案内』として、最も平易に一般の人々へ京都を紹介する絶好の著述であることを自薦して憚らないつもりでございます。・・・」 案内書なので「観光」の語の使用は少ないが次のようなものがある。「観光の日程と順序」という節に「名所旧跡の多い京都の観光は短時日に全部を廻ることは無理ですが、・・・」 奥付の頁に「本書の最後に附してあります白紙四頁は観光者が御気付のことなり或ひは覚書などを記録されるためのものとして・・・」という表現が存在するようである(溝口氏ブログ)。東京都立中央図書館の蔵書検索システムを活用して、1879年~1942年に発行された書籍、雑誌等の書名、出版社名、著作名に「観光」を用いているものを検索した結果、字句「観光」に日本人の国内移動が含まれている用例が見受けられた。
1915年発行の運輸日報社『観光便覧』東京観光案内は「本書は東京観光客のために忠実なる案内者である」とあり国内向けに使用している。かなり古い用例である。・1933年『金沢市主催産業と観光の大博覧会』・1935年『房総の観光』 房総新聞社出版部・1937年『佐渡の史蹟』池田商店出版部・1939年『府下の観光』東京府観光協会。そのほか 1938年横浜市内の「観光」案内をした横浜市土地観光課の『文明開化の横浜』、長崎観光会が発行した1942年『栄光の長崎』がある。内外無差別の意識で観光を使用しているのか、拡大解釈して国内にも使用し始めた用例かは、今のところ判断がしづらいものである。
面白いものに、1938年年発行の高尾保勝会及び津久井渓谷観光協会合作の「武相国境観光地図」がある。国際ではないものの「国」にこだわっている。国内旅行をシャレで外遊という感覚に似ている。1938年に桜華社出版部から出された『全国観光地歌謡集成』は「観光日本の世界的進出は歌謡方面にも様々な姿で歌いだされている」といっているからまだまだ観光の建前に引きずられている。なお、1940年に発行された『北京景観』は北京特別市公署社会局観光課が著作者であるが、印刷所は和歌山市である。
関連記事
-

-
AIに聞く エンパイアービルダー
ここでは エンパイア・ビルダー(St. Paul → Portland)で “左右どちらが良いか”
-

-
文化人類学で読み解く北朝鮮社会 伊藤亜人 公研 2017年10月号No.650
韓国人がなぜ、国内海外を含めてあれほど旅行をするのか考えていたが、一つの答えが見つかったような気がす
-

-
シニアバックパッカーの旅 2019年11月19日 小樽~新潟
https://photos.google.com/album/AF1QipNYbi4hkAlXy7
-
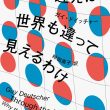
-
言語が違えば、世界も違って見えるわけ (ハヤカワ文庫)amazon書評
https://www.amazon.co.jp/%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%
-

-
動画で考える人流観光学 伝統とマナー、道徳心
◎トイレット部長 https://twitter.com/i/status/11933502315
-

-
中国人観光客の動向調査に役立つHP
百度検索 https://hotelbank.jp/baidu-2017/ 中国出境游研
-

-
日本語辞書と英和辞書に見る「観光」
6月15日 月曜日父親の手術に立ち会うため加賀市立中央病院に出かけた。手術は無事終了し、石田医師には
-

-
旅系Youtube 秘境関係
https://youtu.be/mTpbkUc5Eok?si=7J4ZOT3Jep2359ku
-

-
ハワイは、観光地と観光地ではないところが大きく違うというのは本当ですか
それは**「本当すぎるほど本当」**です。ハワイ(特にオアフ島)を訪れた人が抱く「楽園」のイメージと

