人口減少の掛け声に対する違和感と 西田正規著『人類史のなかの定住革命』めも
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
人口、地域、, 人流 観光 ツーリズム ツーリスト, 出版・講義資料
多くの田舎が人口減少を唱える。本気で心配しているかは別として、政治問題にしている。しかし、人口減少とは定住人口の減少のとことであるから、人は定住が前提と思い込んでいる。そのうえで交流人口の増加という逃げ道を見出しているのである。しかし、本書は、「遊動生活者が定住生活を望むのは、あたかも当然であるかのような思い込み」をうたがい、長い人類史の大部分を占める遊動生活こそ人類の「肉体的、心理的、社会的能力や行動様式」に適したものであったとする。「定住生活は、むしろ遊動生活を維持することが破たんした結果として出現した」とまでいう。筆者は「変化」(あるいは退化)を「進歩」と強弁する現代社会の常識に対する怒りのようなものを感じているようだ。「採集か農耕かということより遊動か定住かということの方が、より重大な意味を含んだ人類史的過程」と考えるのである。p.64 住生活は、体重が50キロ程度もあり、しかも集団で暮らす動物の生活様式としては、極めて特殊
講談社の学術文庫の本書の紹介は、「霊長類が長い進化史を通じて採用してきた遊動生活。不快なものには近寄らない、危険であれば逃げてゆくという基本戦略を、人類は約1万年前に放棄する。ヨーロッパ・西アジアや日本列島で、定住化・社会化はなぜ起きたのか。栽培の結果として定住生活を捉える通説はむしろ逆ではないのか。生態人類学の立場から人類史の「革命」の動機とプロセスを緻密に分析する」とある。
観光の定義を、「日常生活圏を離れ、非日常行動をすること」とすると、日常生活圏が定住により存在するから、定住ありきの概念になる。しかし、定住以前の人類の期間の方が圧倒的に長い。そこで筆者は本書p.22で「旅行によって得ている楽しみの本質もここにあるに違いない。遊動生活の伝統の中で獲得してきた人類の大脳や感覚器は、キャンプを次々と移動させる生活によって、常に適度な負荷が与えられるのであろう。大脳への新鮮な情報供給の不足、あるいは退屈だということが、キャンプ移動の動機として働くこともある」と記述するのである。
第一章「定住革命」で、著者は、これまでの栽培の結果として定住生活が始まったという定説を否定する。遊動生活の破綻の結果としての定住生活。それは、人類の全てを定住生活に向けて再編成した、革命的な出来事だと著者は評価する。定住化については、気候変動により狩猟生活が厳しくなり、反対に植物性の食料が豊富に取れるようになったことから定住したというのが一般的なイメージ
第二章での、移動する理由についての説明。ひとつところにとどまると、どうしても起こる排泄物などの環境汚染。それを避けるために移動する、と著者は書く。
著者は定住化がもたらした人類の変化の問題点について危機感を持っている。しかし後戻りは出来ない。人類はあまりに数を増やしすぎたのだ。定住せざるを得ず、特権階級だけが移動生活が許されるという逆転現象が起きている
主題は狩猟採集民から、農耕民に至るまでの、人類の歩みを論考と発掘された史料からの証明によって裏付けていくというもの。題名にあるように人類の定住化を産業革命と同等に高く評価すべきとし、特に古代の日本ではどのようないきさつで定住生活が始まったのかに重点が置かれている。
人類はおよそ一万年前、それまで数百万年にわたり続けてきた移動生活をやめ、定住生活を始めた。著者は「定住革命」と呼ぶ。きっかけとして有力なのはウケ(筌)やヤナ(梁)、魚網といった定置漁具を使った漁業を始めたことである。定置漁具は携帯が不便だったり不可能だったりするが、その代わり漁獲量の増加が期待できる。製作には繊維や木材を加工する高度な技術が必要で、多くの時間と労力を必要とするが、そのコストに十分見合うリターンを得ることができた。定置漁具の利用は、集団内の分業にも変化をもたらす。狩や刺突漁に比べると労力がかからず、単純作業の反復であるため、女性や子供、老人でもできる。男性は年間を通じた狩猟活動から解放され、その労力を他の仕事に向けられる。三方湖近くの鳥浜貝塚(福井県)からは、大型魚やサザエなど海の魚貝類の骨や殻が出土する。縄文時代の男たちが10キロほど離れた海で漁に興じ、戻って家族らと美味を楽しんだ名残りとみられる。道具の利用が生活を豊かにした
関連記事
-
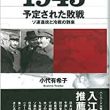
-
歴史認識と書評『1945 予定された敗戦: ソ連進攻と冷戦の到来』小代有希子
「ユーラシア太平洋戦争」の末期、日本では敗戦を見込んで、帝国崩壊後の世界情勢をめぐる様々な分析が行
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-

-
観光学研究者へのお願い 字句「観光」と字句「tourist」の今後の研究課題
これまで、日本語としての字句「観光」の語源等についての分析は、上田卓爾氏等が発表した論文があり、かな
-

-
フィンランドからロシアへの入国など
ィンランドからサンクトペテルブルク(サンクトペテルブルグ)への移
-
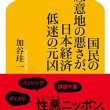
-
『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』 (幻冬舎新書) 加谷 珪一
題名にひかれて、三田図書館で借りて読む。表題は営業用に編集者がつけたのであろう。先進国が消費拡大
-

-
2 中国人海外旅行者数の増大、中国国内旅行市場の拡大が及ぼす東アジア圏への影響
○ 海運の世界で発生したことは必ず航空の世界でも発生する。神戸港は横浜港とともにコンテナ取扱個数にお
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-
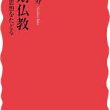
-
『初期仏教』 馬場紀寿著
初期仏教は全能の神を否定 神々も迷える存在であるので、祈りの対象とならない
-

-
『新・韓国現代史』 文京洙著 岩波書店 を読んで、日韓観光を考える。
東アジアの伝統的秩序は、中国中心の華夷理念のもとに、東アジアの近隣諸国が朝貢・冊封の関係において秩序

