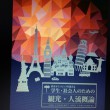上田卓爾「明治期を主とした「海外観光旅行」について」名古屋外国語大学現代国際学部 紀要第6号2010年3月を読んで
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
上田氏の資料に基づく考察には鋭いものがあり、観光とTOURISMの関係についての議論を発展させる意味で大いに参考になった。以下上田氏の説を紹介しながら、私の考え方を述べておく。
① 旅券と観光の定義
上田氏の解説によれば、日本人が正式な渡航ができるようになったのは慶応2(1866)年4月7日の「觸達」によるものであり、旅券(印章、旅切手、免状などの呼称もあった)もこの時に誕生した。明治期における旅券の発行に際しての「渡航の事由」は明治元年から明治42年まで次のように8種類に分けられていた。(①公用 ②留学 ③商用 ④ 漁業(明治25年より「農事・漁業」に変更、明治36年「農業漁業」に変更) ⑤職工 ⑥ 傭奴婢(明治18年ハワイ官約移民開始年から「傭」に変更、明治25年から「出稼、傭」に、明治29年「出稼」に変更))⑦遊歴 ⑧其他諸用(明治元年~14年までは要用:重大な用事)( 明治43年からは①公用、②修学、③商用、④漁業、⑤雑、⑥移民となっている。)
幕末における海外渡航と旅券の誕生、明治初期における海外渡航と旅券制の確立に関しては、『幕末・明治のホテルと旅券』が大鹿武氏(運輸省、日本交通公社)の著作として築地書店から1986年に発行されている。同書によれば旅券を申請するときに旅行の目的を記入する欄が設けられていたようであるが、特に旅券の法的効果に違いがあるものではなかったことから、上田氏の指摘する分類は参考程度のものではなかったかと思われる。
上田氏は、上記8種類中、単なる語義からは最も「観光」に近いと思われるものが⑦の「遊歴」(諸国をへめぐること、たびあるき:昭和3年版「言泉」による)であるとするが、言語学的な意味はともかく、旅券交付において観光が他と区分される実質上の意味があるわけではなく、議論が発展する余地がないとおもわれる。現在の旅券法では、その法的効果から、外交、公用及び一般の旅券に区分し、観光を特別にカテゴリー化してはいないし、する意味もないと判断している。その理由は当時も今も日本に観光概念を必要とする社会的理由がなかったからではないかと思っている。
② Tourist概念の輸入
上田氏の研究で、明治元~42年までで旅券総発行数579,582のうち、「遊歴」は僅かに1,709で、0.29%にすぎないことが示されている。上田氏はこの数字の少なさを持って遊歴を観光とすることに疑問を呈している。両者の法的意義はともかく、私はむしろ当時の社会情勢下において、tourist概念が未だ日本では一般的ではなかったことの証ではないかと思っている。1912年ジャパン・ツーリスト・ビューロが設立されたときにおいて、Touristをツーリストとカタカナ表記し字句観光を使用しなかったことは、当時日本にTouristやTourism概念が一般化しておらず、字句「観光」の概念も今日的な意味で一般化していなかったことの証ではないかと思っている。
注)諸橋轍次著『大漢和辞典縮写版(1968)大修館書店発行』によれば「我が國に於てはあそびの意を表はす文字として遊字を用ひ游字を用ひぬのが通例」
③ 観光、ツーリズムの定義
上田氏に限らず多くの研究者は、Tourismは定義が明確であるのに対して観光は概念が不明確であると主張する。その根拠をUNWTO(世界観光機関)の“Tourism Satellite Account”に求めることが多い。そもそもツーリズムを観光と区別して論じる立場の者が、UNWTOを世界観光機関と翻訳して紹介すること自体が自家撞着であるが、統計をとる際の定義はわが国の指定統計でも当然定義を明確にして行うものであり、その点では変わりはない。さらに、UNWTOの統計にはわが国の提出する統計も含まれているのである。統計を取る意味での論議になれば、経済学的にはむしろUNWTOの統計には商用旅行等の中間投入財が含まれていることの方が問題である。上田氏が引用する井上萬壽蔵が監修した「観光と観光事業」(1967)国際観光年記念行事協力会発行によれば「ツーリズムの語義が不明確で、観光と観光事業とを併せ意味することによるのである。しかし通常は語義のいささか不明確なこのツーリズムの語で一応間に合うということにもなっているのである」としているから、今も昔も五十歩百歩である。
また、上田氏は「「観光」とは物見遊山であるとの思い込みが世間ではなかば常識化しており、一方ではそれを払拭するだけの研究が観光学会でなされてこなかった」と評している。観光が物見遊山であることに否定的な学会の現状、払拭する研究がなされなかった学会の現状に異論はないが、私は払しょくすべきことなのかどうかには異論を持っている。
注)内外の行政機関で統計をとるときに概念が統一されていないと無意味であるから、観光統計の場合、日常生活圏を離れる時間的長さ等を統一することは当然であるが、それぞれ、その統計を取る意味により実施されているものである。このことをもって観光概念が曖昧であるとすれば、tourismも同じことになる。包括旅行運賃には、出発地から旅行が終了するまでに一日以上経過することを条件とする「24時間ルール」がある。このことが影響して国際統計でも「24時間ルール」を採用するが、観光学研究においては、高速時代には日帰りと日帰りでないこと(逆にいえば宿泊の意味)の本質的差異があるのか議論があるはずである。「一年以上居住地を離れる」者をtouristに含めないという統計上のルールは、国際課税制度の影響を受けているからであり、本質的なものであるかは議論があるはずである。業務旅行は、最終的に別の商品の付加価値としてあらわれる中間投入財であるから、個人の私的旅行と異なり、付加価値統計には含めないのが原則である。それぞれ論議する理由が異なるのである。
④ 「観光」の法的定義
上田氏は「観光立国といい、観光庁、国際観光局も設立・改称されているが、まず、定義の整理から始めるべきではなかろうか」とされる。規範性を必要とする法令用語では定義が求められるが、観光の定義は観光基本法制定時の衆議院法制局において断念され「世間で使われている意味」としている。このことから私は自らの博士論文では、観光基本の規範性の欠如を指摘し、法制度においては観光概念ではなく人流概念を用いることを提唱した。そもそも定義などというものは必要性があって行うものであるから、必要性が異なれば定義も異なるものであり、必要性論議が行われていないのである。その意味では上田氏の「観光学大事典」批判には同意する。原子力基本法は原子力の定義を精緻に行っているが、それは取り扱いに他と区別される効果があるからである。
⑤ 字句「tourist」「観光」の語源
観光の歴史を考えるには、当初楽しみのために移動するとされたtouristがどのようにして発生し、認識されるようになってきたかを理解しなければならない。明確に楽しみのために移動する人は、貴族等の特権階級を除き、例外的にしか存在しない時代が長く続いたと考えられ、touristという概念も発生しなかったと考えられる。
touristが誕生するまで、旅をする人には具体的な移動目的があった。行商人、巡礼者、旅芸人、宣教師等である。生活、治安、疫病等を考えれば定住地にいたほうがリスクは少なくてすむ人たちを移動に駆り立てる動機があった。そのような時代に他のどの目的にも該当しない動機、つまり「楽しみ」だけで移動する人たちのことを次第にtouristと呼ぶようになったのであろう。ではこのtouristをtouristではない人たちと何故区別して考えなければならなくなったのであろうか。おそらくtouristに対するビジネスが発生したからであろう。ビジネスになるくらいtouristが増えたのである。
ちなみに、The University of Glasgow Historical Thesaurus of English(http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/)を用いてAspects of travel :: Traveller :: touristを検索してみた。travellerの階層に属する言葉は、pilgrim c1200– farandman c1205–1609 passager c1330–1426 traveller c1375– walker c1430 passenger a1450–1875 voyager 1477–1885 viator 1504– farer 1513 journeyer 1566– viadant 1632 way-man 1638 + 1876 thwarter a1693 migrant 1760 inside 1798– mover 1810– starter 1818– itinerarian 1822D trekker 1851– と歴史的には相当の数に上る。touristの階層では tourist 1780– tourer 1931– grockle 1964– emmet 1975– という検索結果であった。抽象語であるtourismについては holiday-making1792– tourism1811–、touristing 1883、touristry 1883–1894という結果であった。
いずれにしろtourismの概念が観光に比べて明確化されているという神話は早く消滅してほしいものである。
また、字句「観光」の用例に関し、明治期以前の文献の分析調査が行われている。分析調査そのものは言語学的には重要な意味をもつものであるが、「観光学」においては、使用する字句はともかく、観光概念が確立していない時代の用例は意味のないものではないかと思われる。概念が発生してその概念をあらわす言葉が次第に統一されて使用されるようになって行くものであろう。その概念を必要とする社会的存在理由を研究するのが研究者の役目ではなかろうか。
上田氏は、翰林葫蘆集第9巻「興宗明教禪師行状」の当該部分「 今年癸卯、吾國入貢于大明、差前相國子璞禪師爲正使、以希宗爲従僧、希宗曰、某久欲觀光於中華、今也時哉」の用例を発見し、これが、まさにわが国の海外観光旅行を指した用例の初めといえるものであろうとされる(希宗友派は文明15(1483)年~文明17(1485)年まで入明している)。調査結果を否定するものではないが、明治期に日本にはない概念が数多く輸入され、様々な造語がなされ、その中から生き残っているものが今日使用されている。tourismに関して15世紀の日本にその概念が発生していたとは思えない。仮に発生していたとして、様々な表現を用いていたと思われ、その中の一つが偶然字句「観光」であったということにすぎないのであろう。
関連記事
-

-
動画で考える人流観光論 観光資源論 贋作の観光資源的価値
第51回国会 参議院 文教委員会 第4号 昭和41年2月17日 https://kokkai.nd
-

-
『海外旅行の誕生』有山輝雄著の記述から見る白人崇拝思想
表記図書を久しぶりに読み直してみた。学術書ではないから、読みやすい。専門家でもないので、観光や旅行
-

-
観光学研究者へのお願い 字句「観光」と字句「tourist」の今後の研究課題
これまで、日本語としての字句「観光」の語源等についての分析は、上田卓爾氏等が発表した論文があり、かな
-

-
動画で考える人流観光学 伝統とマナー、道徳心
◎トイレット部長 https://twitter.com/i/status/11933502315
-
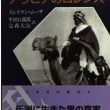
-
シリア、リビア旅行前によむ『アラブが見たアラビアのロレンス』
日本人の一般的な英国のイメージは、映画「アラビアのロレンス」に代表されるポジティヴなものであ
-
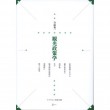
-
用語としての「人流」の発生
○「人流」造語者としての自負○ 「人流」は私が造語したものと自負しております。意識的に著書や論
-

-
「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpyPBMJ
-
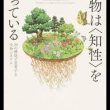
-
保護中: 『植物は知性を持っている』ステファノ・マンクーゾ 動物と植物は5億年前に進化の枝を分かち、動物は他の動植物を探して食べることで栄養を摂取する「移動」、植物は与えられた環境から栄養を引き出す「定住」、を選択した。このことが体構造の違いまでもたらしたらしい。「目で見る能力」ではなく、「光を知覚する能力」と考えれば、植物は視覚を持つ
植物は「動く」 著者は、イタリア人の植物生理学者ステファノ・マンクーゾである。フィレンツェ大学国際