バンクーバー予備知識
公開日:
:
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
フェンタミル
カナダへやってきました。バンクーバー。
街中にそびえるA &Wなどアメリカンな光景を見かけると、沖縄に帰ったような心地になり、まるで帰郷です。バンクーバーの中心地は極めて治安がよく、ショッピングセンター、スーパーマーケット、カフェ、快適な施設がひととおり揃っており、生活に関して困ることはほぼありません。もちろん日本の4,5倍する物価に目を瞑れば、ですが。今後の作品・活動のために、どうしてもこの目で見ておきたかった光景がある。強い光の裏には深い闇が広がり、カナダもまた、オシャレな中心街から外れた通りに、社会から忘れられた人たちの世界がある。自分が足を踏み入れた先は、当然どのガイドブックでも「最も治安が悪いので行かないほうがいい」と紹介されている。あたり一帯、元在住者から見ても危険性が高いので物見遊山で近づくと安全の保証はない。視点をEast Hastings Streetへ戻しましょう。繁華街を抜けて10分ほど。この付近にある警察署を境に、治安は一変する。
このようにきちんと境目があることからも、彼ら薬物中毒者ができるだけ一般社会に悪影響を与えたくない、目立ちたいわけでもないことがわかる。この手前のガスタウンは気楽に大麻の匂いを嗅ぎながら踊り狂う、ちょうど中間の治安をしている街で、「治安のいい中心街→ダンスやアルコールを楽しむ繁華街→薬物中毒者たちが横たわるダウンタウン」と、綺麗に棲み分けがなされていることは興味深い。中間にあたるガスタウンもまた見応えあるスポットですが、今回は主題がブレるので割愛。街の人たちは、だいたい腰がぐいっと曲がってゾンビのような姿に。
俗に言うフェンタニルゾンビだ。あまりに速攻で脳の機能を奪うので、こうして路上で前屈みになって満足に歩くことすら困難に。身体をかけめぐる薬物が一時的に痛みを和らげるが、効果が切れると強烈な離脱症状に襲われ、再びフェンタニルを注入して誤魔化し、腰が曲がっていく。
現代医学がたどり着いた悪魔の薬を流通させることで治安を傾かせる、まるで現代のアヘン戦争の一端がこの場所で起きている。僕は、あんな妙なゲームを作ってしまった原作者として、一時的な快楽で醜い現実を忘れようとする気持ちが痛いほどわかる者として、この路を間近で見ておきたかった。街中を歩き回っていると、強烈な副流煙だけでクラクラと嫌な汗が噴き出る。頭が痛い。
調べると、フェンタニルは気化するとあまり効果がない(そもそも錠剤)らしいが、どのみち覚醒剤、マリファナ、コカイン、あらゆるドラッグが蔓延しており、さらにはどんな場所でも必ず煙に包まれているため、歩いているとどうしても肺に溜まっていく。僕なんかは病気で鼻呼吸ができずに口を開いているため、すべてのドラッグの煙を自動的に吸い込む最悪のカービィ状態である。もはや、どの薬物の影響でくらくらしているのかすらわからない。
が、ある意味では功を奏した。
よろよろと一人、怪しい夜道を歩き回る東洋人。
僕もまた傍目から見てまともには思えない。こうなると街の人たちは受け入れの体制をとってくれる。まあ、「ドラッグ売ろうか?」と売人気質の者も少なくないけれど。それだけではなく、彼らは上記写真のように溜まって吸引をする。だいたいグループの一人二人、耐えきれずに倒れ込んでしまうが、それでも周囲に誰かがいるので死にはしないでしょう。後述するけれども、瀕死の患者のために応急処置が行われる施設もある。
要するに、薬物中毒者同士では細かいこと抜きに助け合って生きているのですね。
みんなダメになっていいじゃない。どこにだって寝転がって許される空気は、むしろ何より「本来の人間の在り方」を感じて安心します。ヒッピー気質極まれり。好きなんですね、人間が。
不動産
- 市場の冷え込み: 2025年後半にかけて、メトロバンクーバーの住宅市場は低調な状態が続いています。
- 高額物件の販売不振: 200万ドル(約2億円)を超えるような高額な戸建て物件などは買い手を失いつつあり、販売率が低迷しています。
- 人口動態の変化: 2025年第2四半期にはBC州の人口が縮小に転じ、カナダ国内で唯一人口減少を記録した州となりました。これは不動産市場にも影響を与えています。
- 金利の影響: 2022年以降の金利上昇により、住宅ローン金利が上昇したことが市場の減速の背景にあります。
- 長期的な価格上昇: 過去20年間で見ると、バンクーバーの不動産価格は3倍以上に値上がりしており、基本的な需要は根強いため、専門家やCMHC(カナダ住宅抵当公庫)は急激な価格崩壊(バブル崩壊)の状態にはないとの判断を示しています。
バンクーバー不動産バブルの象徴とされる建物は、なんでしょうか
特に言及されることが多いのは、以下の2つです。
- 超高級コンドミニアムタワー(ガラス張りの高層マンション)
- 特に、Vancouver House (バンクーバー・ハウス) のような、ユニークなデザインで高額な住宅タワーが、高騰する不動産市場と外国からの投資の流入を象徴していると報じられることがあります。隈研吾氏が設計した「Alberni by Kengo Kuma」なども、新しい象徴的な高級タワーとして注目されています。
- これらのタワーは、バンクーバーのスカイラインを再定義する一方で、「空っぽのコンドミニアム」(Empty Condos) や、地元住民には手の届かない価格設定の問題を象徴しているとも見られています。
- バンクーバー・スペシャル (Vancouver Special)
- これは1960年代から1980年代にかけて建てられた、シンプルな箱型の二階建て住宅のスタイルです。かつては移民や労働者階級のカナダ人が手が届く「夢の家」の象徴でしたが、現在ではその土地の価値が極端に高騰し、古い家が取り壊されてさらに高価な豪邸に建て替えられる現象が、住宅価格の異常な高騰と手頃な住宅の不足を象徴するものとして、皮肉的に語られています。
したがって、「象徴」として特定の一つの建物を挙げるというよりは、「超高級な新しいタワー」 や、「古い低価格住宅(バンクーバー・スペシャル)の土地が高騰する現象」 など、バブルがもたらした都市の変化そのものが象徴と見なされることが多いです。
11月下旬にバンクーバーを旅行します。その際に、旅人としてスマホ写真が簡単に取れるバブルの建物を教えてください
バンクーバー不動産バブルの象徴とされる建物の中で、旅行者として簡単に「スマホ映え」する写真が撮れるランドマークとして、特に現代の超高層タワーをおすすめします。
その中で最も写真の撮りがいがある、際立ったデザインの建物は以下の2つです。
1. バンクーバー・ハウス (Vancouver House)
この建物は、バンクーバーの急騰する高級不動産市場と、大胆な現代建築の象徴としてよく挙げられます。
- 象徴とされる理由: デンマークの建築家ビャルケ・インゲルス(BIG)が設計した、上部が大きく膨らんだ独特のフォルムが特徴的です。グランビル橋の複雑な高架下に建つという難題を解決するために生まれ、その建設費用と販売価格の高さから、バブル期の高級化を象徴しています。
- 写真撮影のポイント:
- グランビル・ブリッジ(Granville Bridge) の橋脚付近や、フォールス・クリーク(False Creek)沿いから見ると、ねじれたようなユニークな構造が際立ちます。
- 特に、グランビル・アイランド(Granville Island)方面から橋越しに見るアングルが有名で、建物の全体像をダイナミックに捉えられます。
2. アルバーニ by 隈研吾 (Alberni by Kengo Kuma)
日本を代表する建築家である隈研吾氏が北米で初めて手がけた超高層ビルです。
- 象徴とされる理由: 日本の伝統的なデザイン要素を取り入れながらも、バンクーバーの中心地コール・ハーバー地区に立つ超高級レジデンスタワーであり、アジアからの資本流入と、富裕層向けのタワー建設ブームを象徴する一例とされています。
- 写真撮影のポイント:
- 建物の基部にある、木材を使った半密閉型の円形劇場(アンフィシアター) の部分がユニークで、ストリートレベルからの撮影に適しています。
- 湾曲したファサードや、外観のパッチワークのようなテクスチャーが美しく、近代的なガラス張りのビルが並ぶ中でひときわ目を引くデザインです。
これらの建物は、ダウンタウンに位置しており、徒歩や公共交通機関で簡単にアクセスできます。
まず、それぞれの場所を地図で確認してみましょう。 バンクーバーへのご旅行、楽しみですね!11月下旬のバンクーバーは少し肌寒いかもしれませんが、写真を撮るには最適な象徴的な建物をご紹介します。
不動産バブルの「象徴」として特にフォトジェニックで、旅行者として簡単にアクセスできるのは、以下のモダンな超高層タワーです。
1. バンクーバー・ハウス (Vancouver House)
この建物は、バンクーバーのスカイラインにおいて最もユニークで印象的なランドマークの一つであり、不動産バブル期の高級コンドミニアム建設ラッシュを象徴しています。
2. アルバーニ by 隈研吾 (Alberni by Kengo Kuma)
日本を代表する建築家である隈研吾氏が北米で初めて手がけた、木材とガラスを多用した美しい超高級レジデンスタワーです。
この2つの建物は、バンクーバーの「ガラスの街」のイメージを象徴する一方で、そのデザインの独自性と価格の高さから、不動産ブームの頂点を示す建築物として知られています。
それぞれの場所は以下の地図で確認できます。
地図情報
どちらの建物もダウンタウンエリアにあるため、効率よく回ることができます。美しいデザインをぜひスマホに収めてくださいね。
関連記事
-
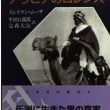
-
シリア、リビア旅行前によむ『アラブが見たアラビアのロレンス』
日本人の一般的な英国のイメージは、映画「アラビアのロレンス」に代表されるポジティヴなものであ
-

-
よそ者としての「tourist」の語感
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-44312894
-
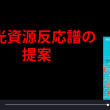
-
AIに聞く、甘利俊一博士の「脳・心・人工知能」を参考にした、『観光資源反応譜』の提案
人流・観光に関する学生用の教科書として、amazonのkindleで『人流・観光学概論』を出版してい
-

-
日本語辞書と英和辞書に見る「観光」
6月15日 月曜日父親の手術に立ち会うため加賀市立中央病院に出かけた。手術は無事終了し、石田医師には
-

-
🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 2024.2.15 DLA カメルーン(トランジット)
昨年に引き続きDLAに。前回は空港で陰性検査を受け、2泊したが、今回はトランジットで空港内に滞在。カ
-
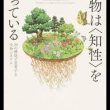
-
保護中: 『植物は知性を持っている』ステファノ・マンクーゾ 動物と植物は5億年前に進化の枝を分かち、動物は他の動植物を探して食べることで栄養を摂取する「移動」、植物は与えられた環境から栄養を引き出す「定住」、を選択した。このことが体構造の違いまでもたらしたらしい。「目で見る能力」ではなく、「光を知覚する能力」と考えれば、植物は視覚を持つ
植物は「動く」 著者は、イタリア人の植物生理学者ステファノ・マンクーゾである。フィレンツェ大学国際
-

-
学生への出題2(外国人観光客と外国人移民の違いをのべ、その違いについての評価を論述せよ)の解答への講評
まず違いの前に共通事項を上げる学生がいた。優秀な学生は「国際的な人流である」「訪問国に経済的な利
-
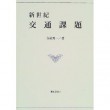
-
Human Logistics の語感(東洋大学国際観光学科准教授徳江順一郎氏のと論議)
東洋大学国際観光学科准教授徳江順一郎氏から「人流がHuman Logisticsですか。 一応、マー
-

-
字句「観光」と字句「tourist」の遭遇(日本観光学会2015年6月発表)
1 ヒトの移動概念の発生と字句の収斂 定住社会における人の移動概念が、英語圏では字句「trav
- PREV
- AIにきく イルクーツク、ヤクーツク、ウラジオストックの旅
- NEXT
- リビアの旅行会社




