『レリギオ <宗教>の起源と変容』 三上真司著 横浜市立大学叢書06 春風社 を読んで 観光とTourismの関係を考える
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
三上真司氏の「レりギオ」の第一章第一節は「宗教」とreligionである。この組み合わせは「観光」とTourismを連想させる。書き出しは「宗教という日本語は二重・三重に不幸な言葉である」で始まるからなおさらである。
「宗教」は西洋諸国の外交文書を日本語に翻訳するという実務的作業において誕生した訳語であり、明治一〇年代になって定着しはじめた。しかし定着の必要性は西洋語にかかわりを持つ役人や知識人という一握りの人々にとっての利点であり、一般人にとっては縁のないものでもあった。
「宗旨」や「宗門」、「教法」や「聖道」など数ある訳語の中から「宗教」という新語がつかわれるようになった主な理由は「教義」という側面を訳語に反映させる必要性が感じられたからとする。
日本人に宗教心が強いか弱いか無神論かと質問をすると、他国人と比較して、わからないという回答が圧倒的に多い。それは、神という存在の意識が希薄な人には宗教心が強いと答えることには抵抗があり、その一方では初詣や墓参りをしながら、その行為を宗教という言葉で言い表していいのか迷う人が多いからである。日本人には宗教とは教義を含む何か次元の高いものという受け取り方が抜きがたくあるからであるとされる。これが「宗教」の第一の不幸である。しかしほかの訳語が生き残ったとしても同じ問題は起きたかもしれない。
ここで三上氏はオックスフォード英語辞典からreligion は、「ある集団に帰属しているという事実」と「超人的な力」に対する信仰心という二つに焦点があるとする。そのうえでreligionには「教え」という意味合いは全く含まれていないとする。その理由は集団的現象としてのreligionから個人の内面の現象としてのreligionへという変遷において容易に埋められない溝があり、religionという語には内部に大いなる分裂を抱えており、religionにふさわしい訳語などというものは存在しないとされる。これが「宗教」のもう一つの不幸であると結論づけられる。
しかし三上氏はそれだけではないとする。日本語の「宗教」とreligionの間で起こったことは、潜在的に他のあらゆる地域で起こりうることであり、実際起こったことである。文化なり宗教は多様な自然環境とのかかわりの中で規定されたものであるならば、はじめから普遍的な共通性を想定することよりも、その多様性をまず認めることが「宗教」に近づくための第一歩となる。西洋語が非西洋と遭遇することによって自らのローカル性と意味の狭隘さを自覚せざるを得なくなるときに感じられる困惑があるとする。
訳語「宗教」が適当かどうかという問いは、ある意味で的外れな問いだということになる。そのような問いが意味を持つのは、訳語がオリジナルの語(religion)の意味を忠実にとらえているかという点についての吟味が成り立つ場合であるが、religionという語にはそのような意味的安定性が二重にかけているとする。そのうえで、三上氏は西洋語のreligionに関する考察を『レりギオ』で詳細に展開されるのである。
religionとはことなり、観光とTourismの関係は、訳語として生き残った「観光」は、その意味は異なるものの、すでに言葉として存在しており、新たに造語されたものではなかったということである。明治十年代の知識人や役人の実務作業にもTourismの訳語はあまり必要性が感じられなかったのであろうから、「ツーリスト」(「ツーリズム」ではない)が用いられていた。そのうえで、両者が接近していったののである。これから観光額研究者に期待されるのは、三上氏がreligionに関し行っているように、概念Tourismに関する研究を展開してもらいたいことである。そうすれば、字句観光に変えて字句ツーリズムを使用しようというような安易な提案はなされないと思われるからである。
関連記事
-

-
読売新聞、朝日新聞記事に見る字句「ツーリズム」「観光」の用例
読売新聞の記事データベース「ヨミダス」及び朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱ」を活用して「ツーリスト
-
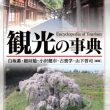
-
『観光の事典』朝倉書店
「観光の事典」に「観光政策と行政組織」等8項目の解説文を出筆させてもらっている。原稿を提出してか
-

-
ハワイ文化 ハワイアンダンス、アロハシャツ
. ルーツは「ポリネシアの移動」にある ハワイアンの先祖は、もともとタヒチやマルキーズ諸島などから
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 2024.2.15 DLA カメルーン(トランジット)
昨年に引き続きDLAに。前回は空港で陰性検査を受け、2泊したが、今回はトランジットで空港内に滞在。カ
-

-
カンザス州 スペイン風邪の進言
https://youtu.be/U9n1ovbfoRg?si=SdPQek_9g6H5d00S
-

-
TTRA発表2015年12月5日 Future Direction of Tourism Policy Studies in Japan
Future Direction of Tourism Policy Studies in Japa
-

-
日本語辞書と英和辞書に見る「観光」
6月15日 月曜日父親の手術に立ち会うため加賀市立中央病院に出かけた。手術は無事終了し、石田医師には

