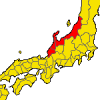Quora 古代日本語の発音
youtubeで、「百人一首を当時の発音で朗読」という動画を見ました。奈良・飛鳥時代の上代日本語で発音されていたのですが、どうして当時の発音がわかるのでしょうか?
1. 奈良・平安時代の発音を知る方法(その一)
『古事記』と『日本書紀』によれば、漢字が日本に伝来したのは3世紀の終わり頃と推察されています。その頃の漢字の読みは、中国の三国時代、呉の国の「呉音」でした。その後、607年に遣隋使、630年に遣唐使が派遣されるようになると、長安の都の発音による「漢音」読みが奈良時代の為政者により推奨されました。遣唐使に随伴した留学生は「長安音」を持ち帰りましたし、奈良の都では唐から招聘されたネイティブ話者の大学寮教授がエリート学生に発音を伝授していました。したがって、奈良時代の知識層は、漢字を「長安音」で音読みしていたと推測されるわけです。そして、当時の「漢音」読みを推察する方法が世の中に残っているのです。それが、601年に隋で編纂された漢字の発音辞典『切韻』と、それを元にした1006年の補填版『広韻』や『韻鏡』等々です。
2. 当時の漢字発音の例:「蝶」=[dʰiep]
現代では「ちょう」と発音されている「蝶」の字は、漢音読みが導入された奈良時代には「長安音」のまま(国際音声記号IPA)で[dʰiep]と発音されていたと考えられます。しかし、その発音を文字として記録できるようになるのは、平仮名と片仮名が使用され始めた10世紀初期(平安時代初期)まで待たなければなりませんでした。そして、短かった奈良時代(84年間)が過ぎて平安時代に入ると、人々は[dʰiep]を「てふ」と書き表すようになりました。濁点や拗音符号が未だ発明されていなかったので「て・ふ」と書くしか方法がなかったのです。「てふ」と書いて[dʰiep]と読んでいたのです。隋唐時代の「蝶」の発音が、中国各地の言語と日本語に、どのように変化して伝わったかをまとめた自作の図表を添付します(Quora既出)。
3. 知る方法(その二)万葉仮名に見る発音
「波・比・不・部・保」は、平仮名の「はひふへほ」の字形の元になった漢字の一部です(他にもあります)。スエーデン、中国、台湾の学者による研究の結果、唐代の長安音は下図のように(敢えて平仮名で書けば)「ぷぁ・ぴぃ・ぴゅ・ぶぅ・ぽぅ」に近い発音であったことが分かっています。そして、奈良時代の日本人は自分たちの和語(大和言葉)を文字で表すのに、漢字の意味を捨てて発音だけを借りた万葉仮名(真名)を発明します。借音の際に、日本人は大和言葉に最も近い発音の漢字を選んだはずです。万葉仮名で書かれた万葉集巻五・793の冒頭「余能奈可波(世の中は)」を当時は「いょのなかぷぁ」に近い発音であったことが、唐代の長安音の影響として推察できるのです。「は行」の字体と発音の変化をまとめた図表を添付します(Quora既出の改訂版)。
4. 発音変化の裏付け(特に「は行」)
ご質問者がご覧になったYouTubeの「百人一首を当時の発音で読む」を私も見てみました。そのシリーズ第4に「ハ行転呼」の説明が出ています。平安時代初期の935年頃に初めて平仮名で書かれた文学作品、紀貫之の『土佐日記』に、それまで「うるはしき」であったものが「うるわしき」と記されていることから、その頃には「は」が「わ」と発音される場合があったことを示しています。また、奈良時代に「ぱぴぷぺぽ」と発音された「は行」が、1516年の『後奈良院御撰何曽(なぞ)』という謎々集によって両唇音「ふぁふぃふふぇふぉ」と発音されていたことが分かっています。それから約180年後の江戸初期1695年に著された『蜆縮涼鼓集』では現在と同じ「はいひふへほ」の声門音に分類されています。この変化は、ドイツの言語学者ヤーコブ・グリル(童話のグリム兄弟の兄)の名前を取った『グリムの法則』にも合致する音韻変化です。フィリピン人が自国を「ピリピン」と発音する一方、スペイン語やフランス語では「h」は無音化したように「p」→「ph」→「f」→「h」→「無音」となる現象です。「富士山」は、その昔「ぷじさん」だったのが現在の「ふじさん」となり、将来は「うじさん」となるのかも知れません。
他にも変化した音はありますが、上述のように古典文献や文学作品、16世紀中頃以降はポルトガル人などが書き残したアルファベットでの日本語辞典や日誌、手紙などで古い時代の日本語発音が解明されています。
関連記事
-

-
明治維新の評価 『経済改革としての明治維新』武田知弘著
明治時代の日本は世界史的に見て非常に稀有な存在である。19世紀後半、日本だけが欧米列強に対抗し
-
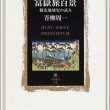
-
『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み
港区図書館で借りだして読んだ。本書は、1998年東北大学提出学位論文がベースとなっている。外部か
-

-
国際観光局ができた1930年代の状勢 『戦前日本の「グローバリズム」』
大東亜共栄圏の虚構を指摘 「バダヴィアに派遣された小林一三商相」国内世論の啓発に努める小林は
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
Quora Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (卒業予定年: 2024年)なぜこんなに沢山の日本人女性が未婚なのですか?
Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (
-

-
21世紀を考える会「仮想通貨の現状」岩下直之京都大教授の話を聞く 2018年4月20日
Bitcoinの発掘の仕組み 256ビットの最初の30個は零が続かなければらないという約束。ハッシュ
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように