朝河寛一とアントニオ猪木 歴史認識は永遠ではないということ
アントニオ猪木の「訪朝」がバカにできない理由
窪田順生:ノンフィクションライター経営・戦略情報戦の裏側2017.9.7 5:00
戦前の日本で初めてイェール大学の教授となった朝河貫一という歴史学者がいる。
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)の報告書に名前が出て一躍、注目を集めた人物なのでご存じの方も多いと思うが、日米開戦直前に、ルーズベルト米大統領から昭和天皇へ親書を送らせようと、当時の日本政府とは関係なく個人で奔走した人物である。
自ら草案を書いて、友人で、ワシントンに顔がきくハーバード大学美術館のウォーナー東洋部長に託した。結局、朝河の草案がそのまま採用されることはなかったが、ルーズベルトは親書を天皇に送った。しかし、時すでに遅しで、届いたのは真珠湾攻撃の直前だった。
そんな朝河を「朝日新聞」では「祖国が平和を諦めた中で、朝河は1人闘う」(2015年4月2日)なんて調子で、戦争回避のために単身働きかけたヒーローのように扱っているが、実は戦前は朝河を敵国のスパイのように扱っていた。
日露戦争で勝利した日本では、ロシアからバンバン賠償金を取れ、朝鮮半島の権益をぶんどるべきだという世論があふれ返っていたが、朝河は、「日本は金や領土のためではなく、アジア解放という大義のために戦ったのだから、そんなものを要求してはならない」と説いてまわった。
それを当時は「愛国マスコミ」の急先鋒だった「大阪朝日新聞」(1905年10月30日)が、いけすかない奴だとディスっている。横浜市立大学の矢吹晋名誉教授があるセミナーで、そのあたりの「悪口」の説明をされているので、引用させていただこう。
《「朝河貫一と呼べる人なり、此の人イェール大学を卒業し、目下、米国某学校に於いて東洋政治部の講師として聘せられ居るものなり。名刺にはドクトル及び教諭と記し、日本人に語るにも日本語を用いず、必ず英語を以てす。此の人、ポーツマスに来たり、日々ホテル・ウェントウォースに在りて、多くの白人に接し、頻りに平和條約の條件に就て説明をなしつつあり。英文にて記せる朝河貫一なる文字とその肩書きの立派なるよりほかは知らざる白人は…」との書き出しで、学校の講師で安月給のくせに、1日に5ドルのホテル代を払って、ここにいるのははなはだ疑わしい、誰の回し者だという書き方です》(日本海海戦100周年記念歴史セミナー「世界を変えた日露戦争」より 2005年5月28日)
猪木氏が訪朝するたびに、「北朝鮮の手先か」とか「北朝鮮に媚びを売っている」といたるところでディスられているのと、ほとんど変わらないのではないだろうか。
関連記事
-
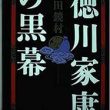
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の
-

-
QUORAにみる歴史認識 伊藤博文公は、当初朝鮮併合に関しては反対だったって話ですが、実際は如何でしょうか?
伊藤博文公は、当初朝鮮併合に関しては反対だったって話ですが、実際は如何でしょうか?
-
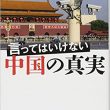
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
園田、石原も認識していた尖閣問題棚上げ論 川島真『21世紀の「中華」』を読んで
気になったところを抜き書きする。 外国人犯罪者の数で中国人の数が多いが、在留率が30%と多い
-
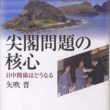
-
『尖閣諸島の核心』矢吹晋 鳩山由紀夫、野中務氏、田中角栄も尖閣問題棚上げ論を発言
屋島が源平の合戦の舞台にならなければ観光客は誰も関心を持たない。尖閣諸島も血を流してまで得るもの
-

-
「戦争を拡大したのは「海軍」だった」 『日本人はなぜ戦争へと向かったのか戦中編』NHKブックス 歴史は後から作られる例
https://www.j-cast.com/bookwatch/2018/12/09008354
-

-
保護中: 『中世を旅する人びと』 阿部 謹也著を読んで
西洋中世における遍歴職人の「旅」とは、糧を得るための苦行であり、親方の呪縛から解放される喜びでもあっ
-
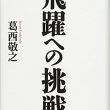
-
『飛躍への挑戦』葛西敬之著
図書館で取り寄せて読んだ。国鉄改革については、多くの公表著作物に加え、これからオーラルヒストリが世
