世界人流観光施策風土記 ネットで見つけたチベット論議
公開日:
:
最終更新日:2023/06/02
出版・講義資料, 旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務, 観光学評論等
立場によってチベットの評価が大きく違うのは仕方がないので、いろいろ読み漁ってみた。
〇 2009.05.07 食えないと死んでしまうが・・・チベット封建制を考える
――チベット高原の一隅にて(43)――阿部治平(中国青海省在住、日本語教師)
http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-745.html
比較的中立で実証的である。日本から、ダライ=ラマ時代について「中国公式筋がいうように、チベット政府は本当にあれほど過酷な政治をやり、農牧民はあれほど悲惨だったのか」という質問を受けた。今年は「農奴解放50周年」という。中国国内ではチベット農奴制について多くの論説があったが、共通するのは、農牧民への抑圧と強収奪、土地への縛りつけ、生産の停滞、そして食うや食わずの生活という内容だった。だが、25年前もダライ=ラマ時代は「農奴は毎年現物あるいは貨幣の形で収入の70%以上の地代を納めたほか、多種の重税と『ウーラ』と高利貸の搾取があった。人身の自由はなく、農牧業生産も発展できなかった」(『西蔵農業地理』科学出版社 1984年)という評価であった。
では公式見解にいう、チベット「農奴」の生活苦の実態はどうだったのか。『蔵族部落習慣法研究叢書之三』(青海人民出版社 2002年)をとびとびに引くと――「(商業都市の出現は)チベット人地域の農牧業の発展にしたがって商業経済が発展したことを物語る」「(中華)民国年間チベット人地域の生産が発展し、各種の農牧産品と工業製品が生れた。チベット人は代々これら製品によって衣食住などの生活の需要を満たしてきた」「社会の発展に従い、チベット人の生活水準も絶えず向上した」これはなんだ、という感じである。ここには「発展できなかった」どころか、ダライ=ラマ時代に生産と商品流通が発展し、農牧民の生活が向上したと書いてある!
さらに商取引が盛んになるにつれて「農奴」の移住や転業が許されたかどうか。中国の商業中心地には旅館や「貨桟」(倉庫兼旅館・仲介業)がある。チベット人地域も同じで、民国時代康定では「鍋荘」が48軒あった。「鍋荘」は商人宿で、通訳や取引の仲介などをやり、口銭を稼ぐ。湟源ではこれを「歇家」といい13軒あった。これらの町へは畜産物の買付にイギリス・アメリカ・ロシアなどの商人も来たという。インドとの貿易はヤートンとギャンゼ、ガントク(シッキム)に集中した。1930年代以後、東部から来た買弁商人は西寧・ラブランなどの土地で羊毛・皮革を買付け、天津・上海で外国商人に転売した。軍閥支配地域では官営資本が茶と各種の地元産品の加工運輸を独占した。
第二次大戦が日本に不利になった1943年、日本政府から派遣された調査員西川一三は中国西北探索のためココノール付近から巡礼に身をやつして「ラブラン=アムチト」という大商人のラサ行きキャラバンに同行した。彼のキャラバンには大量の商品とともに、中小の商人と銃を引っ担いだ護衛と駄夫とが多数いた。
〇 2017-03-22 チベットに潜入した十人の日本人
http://d.hatena.ne.jp/takase22/20170322
20日(月)午後、江本嘉伸さんの講演会があった。23年前に初版で立派な上下巻の単行本『西蔵漂泊 チベットに潜入した十人の日本人』が出たが、今回、その改訂新版が文庫で出版されたのを記念したもの。場所は新宿歴史博物館で、定員の120は満席になった。
以下、講演会のレジュメから―その十人とは
明治時代:仏教の真価を追う旅、そして政治工作のための情報収集
能海 寛(のうみゆたか)東本願寺派僧侶
河口慧海(かわぐちえかい)黄檗宗僧侶
寺本婉雅(てらもとえんが)東本願寺派僧侶
成田安輝(なりたやすてる)外務省特別任務
大正時代:冒険旅行と仏教交流
矢島保治郎(やじまやすじろう)冒険旅行家
青木文教(あおきぶんきょう)西本願寺派僧侶
多田等観(ただとうかん)西本願寺派僧侶
昭和時代:情報員として
野元甚蔵(のもとじんぞう)陸軍特務機関モンゴル語研修生
木村肥佐生(きむらひさお)興亜義塾塾生
西川一三(にしかわかずみ)興亜義塾塾生(木村の一期下)
江本さんによると、これだけの人材が、秘境チベットに潜入したのは日本だけではないかという。とりわけ明治の日本人に、どうしてこんなに行動力があったのかを描きたかったという。
明治維新による王政復古は神道の重視と廃仏運動をもたらした。そこで、日本の仏教界に、「仏教の本質は何か」という問いかけが生まれた。サンスクリット語で書かれた大蔵経がインドからチベットに伝えられ、そこに存在する。その情報によって、日本の仏教教団が動き出した。ことは教団の存立基盤にかかわる。潜入行は命がけだった。現に、最初に挙げた能海寛は、雲南省大理からの手紙を最後に行方不明になっている。
講演会で印象に残ったエピソードは、ダライ・ラマ13世〈現在の14世の先代〉が多田等観に非常に厚く信頼していたことで、多田が十年の修行を終えて帰国しようとしたとき、「ダライ・ラマと枕を並べて名残を惜しんで話しをしながら寝についた」(多田)ほどだったという。多田は、チベット大蔵経をはじめ2万4千部超という膨大な文献を日本に持って帰ったが、これは、チベットの学者たちが前例がないと反対したのを、法王が特別に許可して可能になったという。
関連記事
-
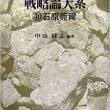
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-
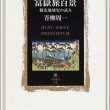
-
『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み
港区図書館で借りだして読んだ。本書は、1998年東北大学提出学位論文がベースとなっている。外部か
-

-
横山宏章の『反日と反中』(集英社新書2005年)及び『中華民国』(中央公論1997年)を読んで「歴史認識と観光」を考える
歴史認識を巡り日本と中国の大衆が反目しがちになってきたが、私は歴史認識の違いを比較すればするほど、
-

-
希望難民ご一行様 ピースボートと「承認の共同体」幻想 (光文社新書) 新書 – 2010/8/17
ピースボートというクルーズ旅行商品があり、かつて週刊誌にその悪評が掲載されたことがある。消費者保護を
-
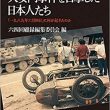
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな
-
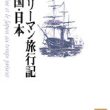
-
書評『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳
日本人の簡素な和式の生活への洞察力は、ベルツと同じ。宗教観は、シュリューマンとは逆に伊藤博文等が
-

-
町田一平氏の私の論文に対する引用への、厳しい意見
町田一平氏がシェリングエコノミーに関して論文を出している https://m-repo.l
- PREV
- ヒマラヤ登山とアクサイチン
- NEXT
- 『チベットの娘』リンチェン・ドルマ・タリン著三浦順子訳

