『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
人口、地域、, 人流 観光 ツーリズム ツーリスト, 出版・講義資料
面白いと思ったところを箇条書きする
p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避したことは、短期的には軍事的脅威を緩和し、軍事負担を軽減する効果があったが、欧米で科学技術が飛躍的に進歩した時期に2世紀にわたって鎖国を維持したことは、日本の軍事技術を決定的に遅らせることになった」
しかし、鎖国をしていない国も植民地にされている。
1600年 1700万人説 低湿地開発はインディカ系赤米 灌漑技術の進歩でジャポニカ米
p.78 近世後半、全国的には人口の増加があったにもかかわらず都市人口の減少があったのは、各地方の都市部では人口が減少した半面。農村部では人口成長があった
p.85 18世紀から19世紀にかけて、三都及び地方の大都市は人口減少もしくは停滞傾向にあった一方で、1-5万人規模の都市と、それより小規模の在郷町において着実な人口増加があった
日本の近代産業は、欧米と比べて早い段階において自由労働市場に直面することとなった。
工業部門における技能形成は、多くの場合、企業の内部労働市場にゆだねられた。
鉱業においては、採用と労務管理を中間管理者に請け負わせる間接管理が支配的であった
1 移動の自由と産業化
p。66
人の移動が自由である場合、その身体に質権や抵当権を設定することはできないから、労働者自身が金融市場から移動や訓練の費用を調達することは困難
教育投資が過少となってしまうのは、労働者が移動の自由を持つことと表裏一体の事象である
欧米の場合、19世紀を通じて、労働者に物権を設定する強制労働市場や、転職を法的に規制する労働法が長く残った。
例えば、18-19世紀におけるヨーロッパからアメリカへの移住者 拘束契約労働者
アメリカが労働者本人の自由意思による契約労働をも禁止したのは1900年
p.67
ヨーロッパにおいては、19世紀末から20世紀初めにかけて、職業学校と、同一事業所における徒弟制を接続する改革が進み、特にドイツにおいては現在においても重要な訓練機関となっている。
アメリカの徒弟制度も、19世紀終わりまでは、雇用主の費用負担によって、拘束契約労働と組み合わせて運用されていた。
その後、産業別労働組合が運営する徒弟制が製造業や建設業において営まれており、修了者が同一産業にの組合に入れば、訓練費用は組合費として回収される。
日本の場合、早くも豊臣政権において人身売買が禁止された。近世において、年季奉公契約は残ったものの、人買いが禁止されていたので、奉公人を転売する二次人身売買市場は存在しなかった。欧米に比べて極めて早い労働の自由化は、家族からの離脱を困難にする幕藩体制下の住民登録制度によって、農業成長と両立した。幕府や藩によって認められた株仲間が、株を持つ加盟業者相互による職人の引き抜きを抑制した。
しかし、明治維新後、住民登録制度による移動の制限が撤廃されるもにならず、移動の自由は権利として保障されてしまう。同業組合の賃金規制も禁止された。
拘束契約労働は認められず、雇用主のギルドや産業別の労働組合もない。日本の雇用主は、欧米と比べて極めて早い段階から、自由に移動する労働市場と向き合うことを強いられた。
p.68
労働者の技能形成を起業特殊的なそれに誘導し、転職を抑制する内部労働市場は、優良大企業において1970年代ころまでに形成されてきたが、それが1980年代以降、広く普及することとなった。
最高裁判所も、75年、解雇権の乱用を規制する法理として雇用関係一般に適用し、内部労働市場の形成に起業を誘導する効果をもたらした。 昭和50年4月25日 最高裁判例
p.69
人別改帳 子が親から逃げ出す費用が高くなる制度を構築 削除されると法の保護の対象外とされた
明治維新後1882年に戸籍制度を通じた移動規制が撤廃 大日本帝国憲法22条
p.70
1896年民法 627条628条 慣習による雇用契約解除の制限は廃止 辞職の自由を制限することは禁止
1975年最高裁判決以降、司法は使用者側による解雇の乱用を制約するために雇用契約に関与しているが、逆転していることになる。
第3節 教育投資
神門氏の作成した図からすると、教育的キャッチアップが経済的キャッチアップよりも40年近く先行している。 神門パラドックスという
なぜ投資したのか?
近代国家をめざっす政府のリーダーシップと、国民の側の立身出世の動機
戦後ながらく、高等教育のキャッチアップは停滞 高給の高学歴者大量輩出をおそれた財界の意向
この高等教育不足が、新規のビジネスモデルを発案する力を失わせて、1990年以降の長期不振をもたらした可能性がある
関連記事
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に資本主義が形成されたか
ちしまのおくも、おきなわも、やしまのそとのまもりなり
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
バンクーバー予備知識
フェンタミル カナダへやってきました。バンクーバー。 街中にそびえるA &
-
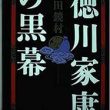
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-

-
ゆっくり解説】突然変異5選:新遺伝子はどうやって生まれるのか?【 進化 / 遺伝 子 / 科学 】
https://youtu.be/bGthe_Aw1gQ ミトコンドリアと真核生物の起源:生物進化
-

-
中国「デジタル・イノベーション」の実力 公研2019No.665
モバイル決済は「先松後厳」まずは緩く、後で厳しく 日本の逆 AirbnbやUberが日本で
-

-
倉山満著『お役所仕事の大東亜戦争』1941年12月8日『枢密院会議筆記』真珠湾攻撃後に、対米英宣戦布告の事後採決
海軍が真珠湾攻撃のことを東条に伝えたのは直前のこと 倉山満著『お役所仕事の大東亜戦争』p.2
-
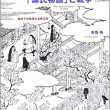
-
『「源氏物語」と戦争』有働裕 教科書に採用されたのは意外に遅く、1938年。なぜ戦争に向かうこの時期に、退廃的とも言える源氏物語が教科書に採用されたのか
アマゾン書評 源氏物語といえば、枕草子と並んで国語教科書に必ず登場する古典である。
-

-
4月20日ロス国際空港からサンタモニカへバスで行く GEMINI回答
TAPカード アメリカ・ロサンゼルス(LA)近郊の地下鉄(メトロレイル)や路線バス(メトロバス
- PREV
- 看中国2017年12月6日ー12日のインタビュー記事
- NEXT
- 大関真之『「量子」の仕業ですか?』

