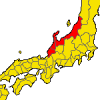『眼の神殿 「美術」受容史ノート』北澤憲昭著 ブリュッケ2010年 読書メモ
公開日:
:
観光学評論等
標記図書の存在を知りさっそく図書館から借りてきて拾い読みした。
観光資源の文化資源、自然資源という分類法に異を唱えている立場から、本書は参考になった。
公開の思想
p.133 博物局博物園博物館書籍館建設之案」には「放観」の語と共に「人口ノ進歩」という言葉が記されているのだ。この「進歩」を促し、体現するのは明治の国家であり、国家はそのために「放観」を実践したのだが、古社寺調査では、「放観」を目指して、個人の所有物にまで手を広げることになったのであった。
自然と人工
p.134 江戸の本草学でいう人類と物類という発想
人工物、自然物という対立
p.136 美術というもの自体がそもそも人工物、自然物という対立の中から、いわば人工物の代表格として登場してきたのではなかったか。
自然というものを客体としてつきはなすのではなく、具体的な体験性においてとらえることを得意とした日本人 おそらく臆するところがあった
では、近代の日本人はかかる前代の自然観をよく近代西洋の自然観に改めえたかというと、むろんそんなことはない。
文化財保護法の「文化財」概念には自然物(天然記念物)までもが含まれておいるのであり、
p.361
足立元の解説
日本(語)の「美術」が近代に新しく形成された制度の一つ 日本美術を学ぶものの共通認識 このような共通認識は1989年出版の本書を契機としてこの20年間に形成された。
「美術」概念が明治の初めに西洋から輸入されたもの 1872年の官製訳語であることは周知のこと
「日本美術史」も「美術」という言葉により構築された近代の諸「制度」によってはじめて可能になったことを明らかにした。
杉本つとむ著『江戸の博物学者たち』
本草学は、動・植物学、鉱物学等にわたる壮大な学問であり、ほぼ博物学に相当する。中国渡来のこの学問は、江戸期に日本独自の本草学を創成し、小野蘭山、畔田翠山により、その研究は頂点へと達した。明治期、本草学は欧米流学問の奔流に呑み込まれていくが、その成果は生物学、民俗学、方言学等に継承された。学問史に異彩を放つ日本本草学の消長。
狩猟民ではない農耕と魚撈(ぎょろう)の日本人はおのずと自然を友として、自然を人類のうちなる物類と認識したのである。五穀豊穣というように、物類の中核が草木であれば、自然を対象とする研究に草(そう)を本(もと)とする本草学の名が与えられ、卓越した詩人と求道者によって本草学が創造されていったのも当然のことといえよう。……人民の厚生を念じた日本の本草学者、それをとりまく社会・学芸・文化を時代とのかかわりで記述してみた。
〇
https://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/44f417134f8ad5f4e63993d6941f5129
源内の、『物類品隲』は、本草学の中でも異彩をはなち、日本博物学史上の傑作と評価されているようだが、この”物類”という名称には、彼の自然観が反映しており、源内以前に貝原益軒は本草学で、”人類・博物”の用語を使っているが、この”物類”という用語はは、当時本草学が博物学に更に深く傾斜していったことの表れでもあり、”人類”と一応対応する概念だという
関連記事
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-

-
人流観光学の課題(AI活用)江戸時代の旅日記、紀行文はその9割以上が解読されていない。「歴史学の未来 AIは膨大な史料から 何を見出せるか?」
江戸時代の旅日記、紀行文は2%程度しか解読されていない(『江戸の紀行文』板坂曜子)。古文書を読む人手
-
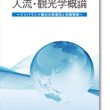
-
電子出版事始め『人流・観光学概論』
大学のテキストで使用するつもりであった『人流・観光学概論』、ウィネットの好意で、校正済みのPDFを
-

-
観光と人流ビッグデータとウェアラブルに関する意見交換会
2015年2月17日14時から一般社団法人日本情報経済社会推進協会/gコンテンツ流通推進協議会におい
-

-
『科学の罠』長谷川英祐著「分類の迷宮」という罠 を読んで
観光資源論というジャンルが観光学にはあるが、自然観光資源と文化観光資源に分類する手法に、私は異議を唱
-

-
京都大学経営管理大学院講義録「芸術・観光」編を読んで
湯山重徳京大特任教授が編者の講義録、京都大学なので興味が引かれた。エンタテインメントビジネスマネジメ
-

-
字句「美術」「芸術」「日本画」の誕生 観光資源の同じく新しい概念である。
日本語の「美術」は「芸術即ち、『後漢書』5巻孝安帝紀の永初4年(110年)2月の五経博士の劉珍及によ
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-

-
Nikita Stepanov からの質問
Nikita Stepanov (Saint-Petersburg State Polytechn