『仕事の中の曖昧な不安』玄田有史著 2001年発行
公開日:
:
観光学評論等
書評ではなく、経歴に関心がいってしまった。学習院大学教授から東京大学社研准教授に就任とあることに目が行った。とある大学設立準備事務を手伝っており、既存大学の教師をリクルートするにあたって、この職位(教授等)が問題になるからである。文科省には職位に関する内規が存在するが、既存大学の職位は教授会で決定するから、当然ずれが発生する。しかし考えてみれば、会社の社長から別の会社の部長になることはいくらでもあるだろう。大学も学校教育法上の取り合扱いは同じであるが、その社会的評価には差が出てくるから、職位にもずれが出るのである。なお、玄田氏の評価はWikiを読むと面白い。
アマゾン書評
2002年 現代の経済学は、社会学的視点を抜きには語り得ない、ということがよく分かった。にしても、素晴らしい論文だと思う。
「高齢化社会、若年労働力の減少に危機感」などという記事を目にする割に、若年労働市場って明るさがない。何なんだ、これは!そんな苛立ちを解放してくれる。
今、団塊世代が定年を迎えつつある。この大量の高給取り達が、グループ終身雇用(出向、転籍を含めた大きな意味での終身雇用)の囲われた会社から出ていく今後(本書によると2010年あたり)、現在のような閉塞感に覆われた状況は変化するのだろう。
1990年代以降に辛酸をなめた世代は、どうなるのだろうか。「俺達のころは、おまえらみたいにおいそれと大企業に入れなかったんだ」などと言う世代になっていくのだろうか。それも経済学者の一部が言うように大企業が衰退してそんな時代はこないのだろうか。今後についても、いろいろと思索させてくれる材料を提供してくれる。
2002年 中高年の既得権益に関する本書の内容は、間違いなく若年層には圧倒的な支持を得るだろう。 記載されている内容はデータの裏づけがあり確度も高いと思う。
中高年層が権益を掌握する社会では、本書或いは本書と同等の趣旨が 例えば著名経済誌等で明らかにされることがありえないのは当然か。
世界的に進行する少子高齢化とともに社会構造的問題の本質はひょっとするとここにあるかもしれない。
中高年層が本書を読んだ感想はいったいどうなるのだろうか。 開き直るか、逆ギレするか、なにせデータによる合理的な説明が本書にはある。
いずれにせよ若年層であれば、大いに共感し勇気付けられることは間違いない。
私も中高年層の影響を最小化するためのスキームを早く考えねば...。
関連記事
-

-
観光資源、観光行動の進化論
「クラシック音楽に隠された「進化の法則」、東大京大の研究者が発見」tいうひょだいの興味深い記事を発
-
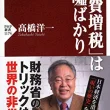
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-

-
「DMO」「着地型観光」という虚構
DMOという新種の言葉が使われるようになってきていますが、字句着地型観光の発生と時期を同じくします。
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
角本良平著『高速化時代の終わり』を読んで
久しぶりに金沢出身の国鉄・運輸省OBの角本良平氏の『高速化時代の終わり』を読んでみた。本を整理してい
-

-
「観光をめぐる地殻変動」-観光立国政策と観光学ー石森秀三 を読んで
学士會会報2016年ⅳに石森秀三氏の表題記事が出ていた。論調はいつものとおりであり驚かなかったが、感
-

-
田口亜紀氏の「旅行者かツーリストか?十九世紀前半フランスにおける“touriste”の変遷」(Traveler or “Touriste”? : Distinctions in Meaning in Nineteenth Century France)共立女子大学文芸学部紀要2014年1月を読んで
2015年4月15日のブログに「羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作
-

-
観光と人流ビッグデータとウェアラブルに関する意見交換会
2015年2月17日14時から一般社団法人日本情報経済社会推進協会/gコンテンツ流通推進協議会におい
-

-
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月 を読んで
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月の存在をうかつにも最近まで知
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
- PREV
- ◎『バブル』永野健二著
- NEXT
- 『カシュガール』滞在記 マカートニ夫人著 金子民雄訳

