国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
観光学評論等
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。
そこで、私の論文が紹介されていることを発見し、久しぶりに昔のことを思い出したので、既述しておく。
観光基本法を改正したいという二階俊博代議士の意向をうけ、基本法として規範性の欠如に問題があることと、改正理由に中央集権規定の削除がタイムリーであることを申し上げたことを思い出した。中央集権規定は佐伯宗義代議士が大反対していたことを申し上げると、二階代議士は当時の佐伯代議士のことを記憶されていたので話が早かった。当時私は日本観光協会の理事長とともに、日本観光戦略研究所という二階代議士のシンクタンクの理事をしていた関係で接触できる機会を多く得ていたからである。実行力という意味で、小泉総理を動かし観光立国宣言を世に出し、旅フェアに総理を出席させ、基本法を改正させ、観光庁を設立した政治家としての力量は比類のないものであろう。
観光基本法は議員立法であったから、その改正法も議員立法になるのが通例であり、内閣法制局審査もない。従って国会事務局職員の手で原案が作成されるのであろうから、その間の経緯も事務的には一番知りえる立場であったであろう。
福山論文では、「一般に基本法とは、その対象とする政策分野に関係する他の法令に参照されながら、一つの法体系を構築し、全体として規範性を発揮するものである7。観光分野においても、関係する法令は数多く存在する。しかし、こうした法令の中に観光基本法を実質的に参照しているものはなく、体系的な法規範は構築されていない。また、基本計画の作成が法定されていないことも、批判されている。観光に関する計画は、いくつかの法令が個別に法定しているのが現状であり8、その関係性を明確にするためにも、基本法を根拠とする基本計画の法定が求められている9。」として私の教科書を紹介している。
「7 寺前秀一『観光政策・制度入門』ぎょうせい,2006,pp.8-12.例えば、「災害対策基本法」(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)と「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和 37 年 9 月 6 日法律第 150 号)の関係など。」
「9 寺前 前掲注 7,pp.33-34. 」
「政府内で、観光政策を所掌しているのは国土交通省総合政策局であるが、実際には様々な省庁が観光を目的に掲げて、施策を実施している。そのため、各施策間の調整が機能していない例も指摘されており10、「観光庁」のような組織に一元化すべきであるとの主張も強い11。また、地方公共団体も施策の実施主体として規定されているが、「国の施策に準じて施策を講じる」受動的な立場であると批判されている12。」
「12 寺前 前掲注 7,p.27.」
すでに10年以上も昔のことになってしまったのである。
関連記事
-

-
CNN、BBC等をみていて
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方
-

-
田口亜紀氏の「旅行者かツーリストか?十九世紀前半フランスにおける“touriste”の変遷」(Traveler or “Touriste”? : Distinctions in Meaning in Nineteenth Century France)共立女子大学文芸学部紀要2014年1月を読んで
2015年4月15日のブログに「羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作
-

-
角本良平著『高速化時代の終わり』を読んで
久しぶりに金沢出身の国鉄・運輸省OBの角本良平氏の『高速化時代の終わり』を読んでみた。本を整理してい
-

-
「植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策」李良姫(メモ)
植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策 李 良 姫 『北東アジア研究』第13号(2007年3月
-

-
『佐藤優さん、本当に神は存在するのですか?』メモ
竹内久美子×佐藤優 著 文芸春秋 本当に対談で語られたことなのか、発行済みの著作物をもとに編集部が
-
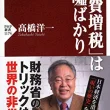
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-

-
千相哲氏の「聞蔵Ⅱ」を活用した論文
「「観光」概念の変容と現代的解釈」という論文を偶然発見した。 http://repository.
-

-
『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
p.52 70年前の戦争を日本側に立って解釈してくれる存在は国際社会では驚くほど少ない・・・日本に
-

-
日本の観光ビジネスが二流どまりである理由
日本の観光ビジネスが二流どまりになるのは、人流に関する国際的システムを創造する姿勢がないからです。
-

-
岩波新書『日本問答』
本書では、大島英明著『「鎖国」という言説 ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史 人と文化の探究』


