田口亜紀氏の「旅行者かツーリストか?十九世紀前半フランスにおける“touriste”の変遷」(Traveler or “Touriste”? : Distinctions in Meaning in Nineteenth Century France)共立女子大学文芸学部紀要2014年1月を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
観光学評論等
2015年4月15日のブログに「羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで」を掲載しておいたところ、読者k氏から田口氏の論文を紹介されさっそく読んでみたところである。
この論文は、英語であるtouristが外来語としてフランスにわたりフランス語として受け入れられてゆく過程を辞書や文学作品等をもとに解明している論文である。田口氏の言葉を借りれば「本稿ではフランス十九世紀中葉までの文献、特に旅行記に現れる(voyageur) と(touriste) の語を拾い上げ、(touriste)の語に付与された意味を検討する。1830年代後半から1840年前半にかけての時期はヨーロッパにおける近代ツーリズムの勃興期とされるが、この時期の(touriste)の指示対象を丹念に追うことで、当時変わりつつある旅のしかたを概観することができるだろう」ということである。
私がこのブログでもお願いしているように、外国語の字句「Tourist」が日本に紹介されていったときに、どのようにして日本語の字句「ツーリスト」、字句「観光(客)」とシンクロナイズしていったのかという課題についても、是非若手研究者の手で解明してもらいたいと思っている。田口氏の分析のとおり「英語からの借用だった(touriste) は、フランス語への導入時にはイギリス圏内を旅するイギリス人旅行者を、やがてフランス、スイス、イタリアを旅するイギリス人を指すようになった」ということをそのまま我が国に当てはめれば、「tourist」に付与される意味はイギリス人に代表される西洋人であり、そのまま字句「ツーリスト」と表記したということになる。ジャパン・ツーリスト・ビューロは西洋人のためのものであり、国際観光局も外貨を持っている西洋人のためのものであるから「観光客」とは日本を訪れる西洋人ということになる。
文学について知識のない私には、(voyageur) と(touriste)の緊張関係への理解に乏しいのであるが、田口氏も羽生氏と同様にこの関係を詳しく論述している。(voyageur) も(touriste) も「旅する者」を意味するのであるが、そこには田口氏の言葉を借りれば「ツーリストは格下だというニュアンスが読み取れる。団体旅行は羊の群れに例えられたり、パッケージ旅行への参加を商品購入という消費活動の一環とされたりして、「ツーリスト」には分が悪い。」ということのようである。
田口氏によれば(touriste)の語が辞書で定義され始めるのは十九世紀後半であり、(touriste)の語は、1872年のアカデミー・フランセーズの辞書には未所収であるが、1875年刊行の「十九世紀ラルース辞典」には登場しているとのことである。我が国の辞書における観光関連用語の出現等ついては2015年6月14日及び17日のブログで紹介しておいたように、19世紀末にTouristは出現しているが観光との関係は不明である。そもそもtourismの出現が1930年代になってからである。なお1895年『和訳英字彙』(蔦田豊著、大蔵書店発行)においてtouristの対訳に「山川ヲ跋歩スル人」とある意味は田口氏の論文を読んで理解できたところである。
フランスの辞書の定義は十九世紀後半に、近代観光が成立した状況を前提にしている。田口氏は「世紀後半には、産業革命の成熟、鉄道や蒸気船の発達、宿泊施設の増加、万国博覧会の開催、観光協会の設立、トーマス・クックによる団体旅行の開始などの要因によって、観光文化が成り立ち、観光が人びとの聞に浸透し、旅に対する意識が大きく変化した。1860年頃には鉄道の発展とともに旅が身近になり、レジャーが人びとの生活に組み込まれていくと、次第に旅行者のコノテーションも変化していく。(touriste)の語が多用されるようになると(voyageur) との境界が唆味になり、現代における観光の認識へとつながっていくだろう」と締めくくっている。我が国の近代観光の成立が南進助等の試みに求められるとするならば二〇世紀初頭のことであり、1911年『辞林』(金沢庄三郎編三省堂発行)への字句「観光」の登場も理解できるのである。
関連記事
-

-
世界人流観光施策風土記 ネットで見つけたチベット論議
立場によってチベットの評価が大きく違うのは仕方がないので、いろいろ読み漁ってみた。 〇 200
-

-
辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
CNN、BBC等をみていて
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方
-

-
『佐藤優さん、本当に神は存在するのですか?』メモ
竹内久美子×佐藤優 著 文芸春秋 本当に対談で語られたことなのか、発行済みの著作物をもとに編集部が
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-

-
『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
p.52 70年前の戦争を日本側に立って解釈してくれる存在は国際社会では驚くほど少ない・・・日本に
-
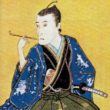
-
『眼の神殿 「美術」受容史ノート』北澤憲昭著 ブリュッケ2010年 読書メモ
標記図書の存在を知りさっそく図書館から借りてきて拾い読みした。 観光資源の文化資源、自然資源という
-

-
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛著
ディプラーニングを理解しようと読んでみた。 イタチとロボットの会話は全部飛ばして、解説部分だけ読め


