『佐藤優さん、本当に神は存在するのですか?』メモ
公開日:
:
観光学評論等
竹内久美子×佐藤優 著 文芸春秋
本当に対談で語られたことなのか、発行済みの著作物をもとに編集部が作り上げて、最終的に対談者が了解したものなのかわからないが、どうでもいいのであろう。印象としては、極めて要領よくまとめてある上に、読みやすいから編集者の手によるものと思ってしまった。竹内さんが自分がうつ病で苦しんでいたことを述べているところがあるが、ご本人の了解がなければ記述されないであろう。私も運輸省の広報誌で、架空の対談を編集したことがある。勿論当事者に了解のもとにではあるが。以下面白いと思ったところをメモする。
キリスト教は神は「有る」からスタート。第一次大戦あたりから疑わしいとなって「無い」ほうに向かう。「無い」の代表が古くはダーウィン、この対談のきっかけになったドーキンス。自立した人間は神という仮説作業なしに世界を理解する努力をするべき。
神という名の偶像を排除することが神学的課題
チンパンジーもゴリラも手話はできる。文法も理解している。英語のヒアリングもできる。声帯の問題から複雑な発声ができないだけ。
手話のできる「ココ」というメスのゴリラは「死=安らかに眠る」くらいまではわかるようだ。チンパンジーも葬式らしき儀式をする
実在したかはわからいないが、そもそもイエスが考えたのは、悔い改めて正しいユダヤ教徒になるということだけ。
それをイエスにあったこともないペテン師的なパウロが終末論を唱えて、新しい宗教をたてた。しかしパウロ教では自分の行状を知っている連中は誰もついてこないからイエスに従う形で作り上げたのかもしれない。
パウロはユダヤ人共同体にいれらないようなことをしたのであろう。その国に合わせるところが創価学会とパウロは同じ。
博愛はストアの発想。ギリシャで流行したストア哲学。キリスト教の隣人愛は万人向けではない。ユダヤ教の時代からヒトを選別して気に入らない奴は虐殺する。
同性愛を明確にとがめたのはキリスト教だけだが、本気で取り締まりを始めたのは産業社会ができてから。人口を増やさないといけないから。4%の割合で発生するのだから同じなのであるが。
日本人は江戸時代サルを食べていた。
連れ子への虐待 報道されるほど少なくなった
人間の場合子殺しが少なくなったから、これほど人口が増加した
女は免疫力の強い男を選ぶ パラサイトが最大の脅威
男性ホルモンの代表がテストステロン しかし、免疫力を弱める
定住に関しての記述
農業があるから罪が出てきたのか、罪を持っているから農業を始めたのか。
佐藤説 西田正規氏が「定住革命」説でいうように、農耕を始めて富が蓄積されるようになってから定住が行われたのではなく、定住の結果として農耕が始まったと考える方が説得力がある。では何のために定住を始めるかというと、支配したいから定住を始める。定住生活が始まると、人が人を支配するから罪と結びつきやすい。
竹内説 定住するから抗争が起きる。チンパンジーは数十頭で群れをなしている。その縄張りから出ると半殺しの目に合う。人類もそうだったのでは。そこに罪が芽生えたのではないか。
関連記事
-

-
辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02
-

-
観光学が収斂してゆくと思われる脳科学の動向(メモ)
◎ 観光学が対象としなければならない「感情」、「意識」とは何か ①評価をする「意識」とは何か
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-

-
観光資源、観光行動の進化論
「クラシック音楽に隠された「進化の法則」、東大京大の研究者が発見」tいうひょだいの興味深い記事を発
-

-
「旅館の諸相とその変遷について」「近代ホテルにおける「和風」の変遷とその諸相」を読んで
溝尾良隆立教大学名誉教授が中心となっている観光研究者の集まりが7月8日池袋で開催された。コロナ後の久
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-
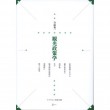
-
羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで
一昨日の4月9日に立教観光学研究紀要が送られてきた。羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀
-

-
CNN、BBC等をみていて
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方
-

-
角本良平著『高速化時代の終わり』を読んで
久しぶりに金沢出身の国鉄・運輸省OBの角本良平氏の『高速化時代の終わり』を読んでみた。本を整理してい
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
