伝統は後から創られる 『江戸しぐさの正体』 原田実著
公開日:
:
観光資源
本書の紹介は次のとおりである。
「「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である。本書は、「江戸しぐさ」を徹底的に検証したものだ。「江戸しぐさ」は、そのネーミングとは裏腹に、一九八〇年代に芝三光という反骨の知識人によって生み出されたものである。そのため、そこで述べられるマナーは、実際の江戸時代の風俗からかけ離れたものとなっている。芝の没後に繰り広げられた越川禮子を中心とする普及活動、桐山勝の助力による「NPO法人設立」を経て、現在では教育現場で道徳教育の教材として用いられるまでになってしまった。しかし、「江戸しぐさ」は偽史であり、オカルトであり、現実逃避の産物として生み出されたものである。我々は、偽りを子供たちに教えないためにも、「江戸しぐさ」の正体を見極めねばならないのだ。」となっている。
著者の原田氏は、江戸しぐさは、もともと明治以降の誤った日本を否定しようとする芝の反骨の産物であるとする。ところが結果として過去の日本を賛美する、安倍晋三等の勢力にとっても価値を持ってしまったとするのである。戦前の芝が最も嫌っていた勢力に支えられて文部科学省からお墨付きを得たというわけだ。彼が墓場まで持ってゆくべきものが、彼の死後越川等の働きで教育現場等で重宝されるものとなっていったのである。
AMAZONの書評も
1つは「江戸しぐさ」なる捏造された歴史に対する批判です。これは江戸時代の浮世絵や書物などの史料を元にしているため、信憑性は高い。「江戸しぐさ」がいかに現実の歴史とかけ離れているかを提示するだけでなく、その提唱者のどのような経験や思想からそういった「嘘」が作られていったか、という点まで踏み込み、完全な検証こそ困難なものの説得力のある仮説として提示している。嘘を嘘だからと切り捨てるのではなく、そういう嘘が提唱されるに至った経緯を解明することで、「江戸しぐさという虚偽が発生したこと」という一連の事象そのものを研究対象とする、というスタンスは読んでいて非常に興味深いものでした。
「道徳を教える根拠に嘘を用いたら、それが嘘だと判明したときに道徳そのものが崩壊する」というのは非常にまっとうな指摘で、願わくばそういった事態に世の中が向かわないことを祈るばかり。
本書は、と学会会員でもある歴史研究家の著者が、江戸しぐさを標榜するマナーが公共広告機構の宣伝を経て学校の教科書にまで採用されていく捏造の流布の過程を仔細に検証した一冊。
本書のテーマについて、一つ見落とせないベースは、江戸しぐさを生み出した方またその普及に尽力した方達には、捏造の自覚はあったかもしれないが、基本は善意で行っていた節がある点。公共広告機構にも文科省にも一部政治家にも悪意というほどの意識はなかったようにも受け取られる。
だからこそと、著者は力説する。プロの歴史家が少し検証すれば分かることを彼らは誰も確かめない。由来も証拠も不確かなことだが、一見良いことに見えるから公共広告機構も文科省もスルーで受け入れてしまう。そして、同じことを、著者と一部の人たちを除けば私達一般大衆もしていた。「マナー大事だよね」くらいのお気楽な気持ちで私は江戸しぐさのCMだかポスターだかを見過ごしていた。悪意の捏造の例を著者はいくつか例示しているが、悪意は捏造を隠蔽するために頻りに証拠を捏造しそして自滅する。しかし、善意の捏造は敢えて証拠を捏造しないためボロが出づらい。しかも、日本人は善意の人や良いことを疑わない傾向にあるから、なおさらだ。
著者は、そこへの展開を敢えて行っていないが、江戸しぐさ=良いこと=愛国心 × 道徳教科書 から何が導き出されるのか?私は、愛国心を否定する者ではないし、教科書のないのをいいことに反日や独善的な洗脳を行う教員という問題もあるので道徳教科書を一概に悪いとも思わない。しかし、とんでも捏造を見抜けない文科省や教科書会社には、それを任せるのはどうなんだろう?と呆れたのも事実。
私は、歴史や伝統の捏造を頭から否定するものではないところに、原田氏とは視点が異なる。観光資源という意味では、歴史や伝統など、フェイクもいいところであるが、それでも人を移動させる力があるという意味で、観光資源として意味があるのである。
歴史や伝統など後からいくらでも作れるから、観光資源などどこにでも転がっているのであるが、それだけに競争も厳しいのである。
関連記事
-

-
蓮池透・太田昌国『拉致対論』めも
p.53 太田 拉致被害者家族会 まれにみる国民的基盤を持った圧力団体 政府、自民党、官僚、メディ
-
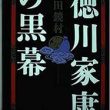
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-
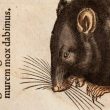
-
ペストの流行 歴史は後から作られる例
BBCを聴く。中世の黒死病、ペストの流行はネズミによるものだと、学校で教えられたはずだが、残存するデ
-

-
大衆軍隊出現の意味 三谷太一郎講演メモ 学士会報2018-Ⅳ
226事件は、天皇の統帥権の名目化 軍隊の大衆化 軍隊内の実権は将官、佐官、尉官へと下降した
-

-
歴史は後から作られるの例 「テロと陰謀の昭和史」を読んで
井上日召の「文芸春秋臨時増刊 昭和29.7 p.160「血盟団」の名称は、木内検事がそう呼んだので
-

-
『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文
-

-
『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場 https://www.nicovideo.jp/watch
-

-
『動物たちの悲鳴』National Geographic 2019年6月号
観光と動物とSNS https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/m
-

-
明治維新の見直し材料 岩下哲典著『病と向きあう江戸時代』第9章 医師シーボルトが見た幕末日本「これが日本人である」
太平の世とされる江戸時代に自爆攻撃をする「捨足軽」長崎奉行配下 福岡黒田家に「焔硝を小樽に詰めて肌身
-

-
観光資源・歴史は後から作られるの例
http://www.asahi.com/articles/ASKB05T40KB0ULZU015.


