『「食べること」の進化史』石川伸一著 フードツーリズム研究者には必読の耳の痛い書
公開日:
:
人口、地域、, 感情、感覚, 観光情報 コミュニケーション, 観光資源
食べ物はメディアである
予測は難しい 無人オフィスもサイバー観光もリアルを凌駕できていない 「穴居人の原理」洞穴時代からの昔ながらの欲求が勝利を収めてきた 新しいテクノロジーで新しい職が受け入れられるか?
1804年缶詰め発明 フランス海軍で採用
多様性と均質性のパラドックス
人の脳は因果関係を認知する能力を高めて進化してきたが、うまく因果関係を認知できない場合に、脳の特殊能力として宗教という体系を生み出した
エルブリ 人の脳をびっくりさせる料理
分子調理学と分子調理法
人工培養肉の現実化 イスラム教義
人間が動物を食べモノとしてみるようになったのはいつごろからか
ナッツ類を摂取するようになり脂質の消化に係る腸が発達、繊維の消化に係る盲腸が縮小する自然選択が発生、結果として肉を食べるに適した腸を持つ個体が残る
nエネルギーを腸と脳にどう振り分ける、腸は神経細胞が一億もある第二の脳
調理のジレンマ 肥満になる理由 節約遺伝子仮説と料理仮説
未来の健康 様々なテクノロジーが先回りして健康管理 気が付いたら120才
頭脳効率化人間の可能性
光合成できる独立栄養生物といった食べない多細胞生物 消化器官は不要になる
意思による進化を可能とする合成生物学の進歩は、食べるという行為を時代遅れにする
思想的な選択を食において行っている スシポリス
美食思想は、宗教にかわる思想となり、文化というレベルになった
ベジタリアン ソローフード、フードロス、食育 食が社会性を持つ
スペイン 豚肉を食べることが踏み絵
現代日本の食の激しいはやりすたりをまとめた「ファッションフード。、あります」B級ご当地グルメ
児童書に食の物語が多いのは、食が大人文学おける性の代替
そもそもおいしさは科学的に解明できるのか 『美味しさの脳科学』
脳機能研究の進展は目覚ましい 前頭眼窩野の活動から快不快が予測できるという論文もある
国連世界人口展望 2050年98億人 2100年は112億人 ヨルゲンランダースの予測は2040年代81億人をピークに減少 少なくとも2052年までは十分に食料はある
家族団らんは高度成長期のみの出来事 近代まで食事中の会話は禁止 誕生したのは明治20年代。教育家の岩本善治がキリスト教主義の雑誌等に記事を書き、その後国家主義的な儒教教育と結びついて、家族そろって食事するべきという意見が広まる。それが一般的風景になったのは1970年代 1980年代には孤食が登場
関連記事
-

-
「地消地産」も「アメリカファースト」も同じ
『地元経済を創りなおす』枝廣淳子著 岩波新書を読んだ。ちょうど教科書原稿を書いているときだったので参
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 文字
https://youtu.be/eXhYsJNiktI
-

-
『公研』 2018年2月号 「日本人は憲法をどう見てきたか?」
歴史は後から作られるの例である。 境家史郎氏と前田健太郎氏の対談 日本国民が最初から憲法九条
-

-
新華網日本語版で見つけた記事
湖南省で保存状態の良い明・清代の建築群が発見 http://jp.xinhuanet.com/20
-
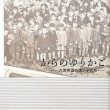
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-

-
観光資源としての吉田松陰の作られ方、横浜市立大学後期試験問題回答の例
今年も一題は、歴史は後から作られ、伝統は新しい例を取り上げ、観光資源として活用されているものを提示
-

-
国際人流・観光状況の考察と訪日旅行者急増要因の分析(2)
1 国際「観光」客到着数 『UNWTO Tourism Highlights 2016 E
-

-
Quora 現代科学では、人工生命は可能なのでしょうか?
可能です。何しろ既にできています。 こちらに示しているのが人類が現段階で到達している最先端の
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド
