伝統は後から作られる例 関西は阪神フアンという伝統
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
伝統・伝承(嘘も含めて), 観光資源
これも学士會会報の記事、何時も面白い話をしてくれる井上章一氏の「ゆがめられた関西像」
戦後しばらく関西では巨人が大人気だった。映像記録を見ると1962年阪神が優勝を決めた当日の甲子園球場はガラガラであったそうだ。阪神電鉄の鉄道輸送記録や付帯収入も調べてみると面白いかもしれない。阪神フアンが増えたのはごく近年の現象なのだそうだ。ほとんどの子が巨人の帽子をかぶりあとは数名、南海の帽子をかぶっていた。
戦前は、人々は地元のライバル会社の大戦に興味を持った。「反東京」「反読売」という考え方にあおられる客はほとんどいなかった。
最初に「反巨人」に燃えたのは南海フアンだった。別所投手引き抜き事件の影響。1959年エース杉浦で日本一は私・寺前も子供頃で記憶があり、確かに阪神フアンは少なかったような気がする。私もテレビ中継がある巨人のフアンだったが、友達が「巨人フアンの野球知らず」といっていたことを思い出す。
新聞社の販売競争から二リーグ制が始まる。阪神は春の甲子園を毎日新聞に支えてもらっている恩義から、パリーグにゆく口約束をしていたが、セリーグに残留してしまった。怒った毎日新聞は阪神から有力選手を引き抜いた。この時に阪神フアンに「反毎日」感情が発生。まだ「反東京」ではなかった。
1959年の天覧試合、これも私はテレビで見た記憶がある。天覧試合の相手は阪神である必要はなかった。つまり巨人のライバルではなかった。その天覧試合の最終回、村山が長嶋のホームランでサヨナラ負けをしたことにより、「反巨人」の阪神フアンが誕生したと井上先生は解説されている。
「「あほらしいと思われることが、結構私たちを左右している」という信念のもと私はこれからもこうした研究を続けていきたいと思っています」と井上先生は締めくくっている。私も何時頃からか巨人も野球もどうでもよくなったが、伝統と思われていることが結構新しいということには相変わらず興味が尽きないのである。
関連記事
-

-
童謡「赤とんぼ」から躾を考える
村のしつけが対象とするのは正規メンバーだけで、共同体からはみ出た子供たちは、アウトサイダーとして
-

-
伝統論議 蓮池薫『私が見た「韓国歴史ドラマ」の舞台と今』
〇 蓮池氏の著作 「現代にも、脈打つ檀君の思想、古朝鮮の魂』などをよむと、南北共通の教育があること
-

-
『動物たちの悲鳴』National Geographic 2019年6月号
観光と動物とSNS https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/m
-
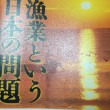
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場 https://www.nicovideo.jp/watch
-

-
2019年1月28日横浜私立大学期末試験 伝統、歴史は後からつくられている例を挙げさせた。その回答例の紹介
2019年1月28日横浜市立大学の観光振興論の期末テストを行った。問題は2問。下記のとおりである。
-

-
現代では観光資源の戦艦大和は戦前は知られていなかった? 歴史は後から作られる例
『太平洋戦争の大誤解』p.183 日本人も戦前はほとんど知らなかった。戦後アメリカの報道統制
-

-
『ピカソは本当に偉いのか?』西岡文彦 新潮新書 2012年 を読んで
錯覚研究会での発表に備えて読んでみた。演題が「ピカソの贋作は本物を超えるか」としたため、慌てて読んで
-

-
『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話 ムハンマドの活
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が

