『「鎖国」という外交』ロナルド・トビ 2008年 小学館 メモ 歴史は後から作られる
公開日:
:
最終更新日:2018/01/17
観光資源
ロナルド・トビさんは、江戸時代から日本には「手放し日本文化礼賛論」があったことを説明し、富岳遠望奇譚となずけている。「霊峰」富士山が朝鮮半島からも見えたという奇譚である。現在のインバウンドブームもややそれに近い印象がある。征韓論という形で発露された日本人の朝鮮認識は江戸時代から萌芽がみられ、途切れることなくその縁を伸ばし続けており、現在の嫌韓論にまで続くのであろう。
p.277 国境を越えて「三国一」になったのは、近世以降の現象。頼山陽も清正の富岳遠望奇譚を歴史的事実として受け止め『日本外史』の中に取り入れている。
p.298 19世紀の日本では、対外危機感が日に日に増してゆく中、日本外国と戦った「異国退治譚」が流行。「三韓征伐」「朝鮮征伐」「蒙古退治」が飛ぶように売れていった。
p.309 朝鮮通信使は霊山金剛山には及ばないと必ず言った。
愛国心の高揚を図った政府の思惑で、国定教科書でも清正が朝鮮で果たした「遊飛」が語られ、学童に教えられるようになり、清正は国民的英雄に担ぎ出されたのである。
日清戦争直前に出された延一による『加藤清正朝鮮ヨリ富士ヲ望ム』という新聞錦絵も、江戸時代に築き上げられてきた富岳遠望奇譚や、富士山対異国人という言説のさらなる力を雄弁に物語っているのではないかと思われる。
雨森芳洲 盧泰愚大統領が紹介して知られるようになった。善隣外交の意思を持っていた例外的人物
p.332 江戸時代の日朝関係が友好的であることを強調すればするほど、何故、急に明治時代に急に「征韓論」が生じてくるのかが説明できなくなる。
近・現代の征韓論の土壌に、近世以前からの神功皇后の三韓征伐神話や近世初頭の秀吉の朝鮮侵略があり 明治期になって征韓論という形で発露する日本人の朝鮮認識は江戸時代から萌芽見られ、江戸時代にも途切れることなくその根を伸ばし続けていたのではないか
関連記事
-

-
『公研』 2018年2月号 「日本人は憲法をどう見てきたか?」
歴史は後から作られるの例である。 境家史郎氏と前田健太郎氏の対談 日本国民が最初から憲法九条
-

-
『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話 ムハンマドの活
-

-
AI に書かせた裸婦とダリ
AIに描かせたという裸婦の絵がネットで紹介され、ダリが描いたようだと注釈。 正確にいえば、AIが描
-

-
ウッドストック50周年中止 歴史は後から作られる
newspicks のコメントが面白い。Wikiの解説とは一味違う。これも歴史は後から作られる例か
-

-
ヒトラー肝いりで建造の世界最大のホテル・プローラ
観光政策というより、福祉政策なのかもしれませんが、現代なら民業圧迫という声が出るでしょう。
-

-
蓮池透・太田昌国『拉致対論』めも
p.53 太田 拉致被害者家族会 まれにみる国民的基盤を持った圧力団体 政府、自民党、官僚、メディ
-
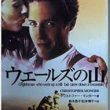
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
八鍬友広著『闘いを記憶する百姓たち』
自力救済の時代は悲惨であった。権力が確立すると訴訟によることとなり、平和が確立される。 江戸時代は
-

-
観光資源評価の論理に使える面白い回答 「なぜ中国料理は油濃いのか」に対して、「日本人は油濃いのが好きなのですね」という答え
中華料理や台湾料理には、油を大量に使用した料理が非常に多いですが、そうなった理由はあるのでしょうか

