『おクジラさま』佐々木芽生著 備忘録 伝統は古くはない
公開日:
:
最終更新日:2019/07/02
伝統・伝承(嘘も含めて), 観光資源
https://spice.eplus.jp/articles/137344
p.25 庄司元町長 1968年NHK「新日本紀行」 次の産業は観光しかないと語り、目玉として鯨の博物館と水族館と旁、イルカショウを見せるという構想を持ち、67年アメリカ視察をし、コーヴの主人公オリバーが働いていたマイアミ海洋水族館を視察する。
p.32 コーヴ批判の多くの人は見ていない 隠し撮りはアメリカでは合法。日本だけが問題視する
p.43 日本で捕獲される2万頭のイルカのうち太地町は2000頭 ステータスシンボルになっている
p.59 1951年当時のアメリカのニュース映画 マッカーサーの許可でジャップの捕鯨が復活 空腹の国民には歓迎されるのだ。
p.65 環境保護団体からの明らかな圧力は2000年代になってもまだ続きていた。カリブ諸国に対して「グリーンピースは観光のボイコットを呼びかけるつもりはありません
p.69 アメリカ イヌイットの鯨捕獲には固執 先住民迫害の歴史がある
鯨が環境保護のシンブルになったことで、政治家は海洋生物を利用するなって口が裂けても言えなくなった
日米で、伝統に対する考え方も違う
p.99 需要の少ない鯨肉のため巨額の補助金を投入して南極に行く必要があるか、沿岸捕鯨再開の方がよい
p.185 水銀汚染 濃度は高いが健康被害はない 太地沖で捕獲された鯨には解毒システムが備わっている
p.199 人間を脅かす獰猛なクマがテディベア セオドアルーズベルトが熊内に行った時のエピソード
戦後のオリンピック捕鯨に日本も参加
近海のすべての哺乳類と鳥類は環境庁所管の鳥獣保護管理法 鯨とイルカは例外扱いで水産庁
p.246 海外からの圧力がなくなると鯨を食べることも忘れてしまうのではないか
関連記事
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド
-
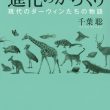
-
進化論 宗教と進化論 『進化のからくり』千葉聡 ガラパゴス島が観光資源になる過程の材料として面白い
イスラム教と進化論、初期キリスト教と進化論 https://youtu.be/i_lrAKC3
-

-
『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話 ムハンマドの活
-

-
『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-

-
混浴は伝統ではない 『温泉の日本史』『温泉の平和と戦争』を読んで メモ
書評に「論文等を査読・掲載する学会誌を年2回刊行、全国の温泉地で年2回開催している研究発表大会が基本
-

-
本当に日本は職人を尊ぶ国であったのか?
司馬遼太郎氏は、韓国、中国との比較においてなのか、『この国のかたち』のなかで、「職人。実に響きがよ
-

-
2015年「特攻」 HNKスペシャル
http://www.dailymotion.com/video/x30z4ho フィリピ
-

-
『帝国陸軍師団変遷史』藤井非三四著 メモ
薩長土肥による討幕が明治維新ということになっているが、なんと首都の東京鎮台本営に入った六個大隊のう
- PREV
- 『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
- NEXT
- 『連合軍の専用列車の時代』河原匡喜著


