『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
p.52 70年前の戦争を日本側に立って解釈してくれる存在は国際社会では驚くほど少ない・・・日本に対してはファシズムの一翼を担い、最後まで自由主義社会に対して反抗した国として認知されている
p.90 パリのテロ事件に対してシリアやイラクで毎日多くの犠牲者が出ているのにパリの事件だけを特別視して追悼のアイコンを使用するのはおかしいと批判がFACEBOOKで一時あふれた。これに対して筆者はパリは特別の存在意義がある。そこでのテロは近代西洋システムの思考に慣れ親しんだインテリのアイデンティティへの挑戦であり、問題の本質を見誤っていると批判。テロは肯定しないが、この辺りが筆者の限界かもしれない。国際法上の戦闘行為でない限り、同じである。
p.95~97 カーン平和記念館の前に「勝利のキス」の彫像 対日戦争の終焉を記念 南京虐殺を断罪する展示もある ビシー政権への複雑な感情 無欠開城がパリを救った(バギオを思い出す) ナチスのユダヤ人虐殺と同じことを日本もマレー半島で行っていたという展示
p.138 ロス郊外の「寛容の博物館」では日本の在特会(在日特権を許さない市民の会)を紹介 KKKとともにNet Far Right (ネット右翼)という言葉で展示
p.195 乃木希典の長男の慰霊碑が旅順にはあるが誰も花を手向けた様子が見られない
p.219 負の世界遺産という言葉は英語にない heritageに内包されている 怨親平等の思考形態で過去を水に流してきた
関連記事
-

-
観光資源論と 観光学全集「観光行動論」を考える ベニスのクルーズ船反対運動への感想と併せて
現在「観光資源論の再構築と観光学研究の将来」と題した小論文をまとめているが、観光資源(正確には観光対
-

-
◎◎3 戦争、観光、メディア~戦争も観光資源へのパスポート~
戦争・戦闘はメディアが好んで取り上げる。メディアは刺激を基本とするからである。観光を論じる意義とそ
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-
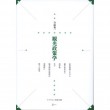
-
羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで
一昨日の4月9日に立教観光学研究紀要が送られてきた。羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀
-

-
東アジア人流観光論の骨格(人口と人流)
○東アジアの人流を考える場合に、まずその地域の定住人口の推移を把握しておく必要がある。私は定住人口の
-

-
「観光をめぐる地殻変動」-観光立国政策と観光学ー石森秀三 を読んで
学士會会報2016年ⅳに石森秀三氏の表題記事が出ていた。論調はいつものとおりであり驚かなかったが、感
-

-
辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
戦前に観光が展開された時の日本の状況
日本の学会では1920年代の国際秩序をワシントン体制という概念で論じることが通例。1931年の満州事


