『科学の罠』長谷川英祐著「分類の迷宮」という罠 を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
観光学評論等
観光資源論というジャンルが観光学にはあるが、自然観光資源と文化観光資源に分類する手法に、私は異議を唱えている。
(http://www.jinryu.jp/201703023474.html)
本書の中の一説「分類の迷宮」という罠を読み、単純に観光資源の分類に異議を唱えていた自分が恥ずかしくなったのここの記述しておく。
著者は、科学は「WHAT」(何であるか)ではなく(26〜36・98・129頁)「WHY」・「HOW」を探求することと位置付け(37〜56頁)ている。分類はコミュニケーションツールであるとする。そして常に書き換えられているとする。ある分類を使わなければいけないといえるのは、誰もが従わざるとえないことが示される場合だけである。本でいえば、字数。特に著者の専門である生物学関係では第1・2章を割き、とりわけ分類学の曖昧性を取り上げつつ(第2章)、分類学は科学でない(98頁)とまで言い切っている。
関連記事
-

-
京都大学経営管理大学院講義録「芸術・観光」編を読んで
湯山重徳京大特任教授が編者の講義録、京都大学なので興味が引かれた。エンタテインメントビジネスマネジメ
-

-
Deep learning とサバン(思い付き)
「 スタンフォード大学の研究チームが、深層学習を用いて衛星画像からソーラーパネルを探し出すディープ
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
「観光をめぐる地殻変動」-観光立国政策と観光学ー石森秀三 を読んで
学士會会報2016年ⅳに石森秀三氏の表題記事が出ていた。論調はいつものとおりであり驚かなかったが、感
-
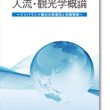
-
電子出版事始め『人流・観光学概論』
大学のテキストで使用するつもりであった『人流・観光学概論』、ウィネットの好意で、校正済みのPDFを
-

-
田口亜紀氏の「旅行者かツーリストか?十九世紀前半フランスにおける“touriste”の変遷」(Traveler or “Touriste”? : Distinctions in Meaning in Nineteenth Century France)共立女子大学文芸学部紀要2014年1月を読んで
2015年4月15日のブログに「羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-

-
『地方創生のための構造改革』第3章観光政策 論点2「日本における民泊規制緩和に向けた議論」(富川久美子)の記述の抱える問題点
博士論文審査でお世話になった溝尾立教大学観光学部名誉教授から標記の著作物を送付いただいた。NIRAか
-

-
『佐藤優さん、本当に神は存在するのですか?』メモ
竹内久美子×佐藤優 著 文芸春秋 本当に対談で語られたことなのか、発行済みの著作物をもとに編集部が
- PREV
- 『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
- NEXT
- 「DMO」「着地型観光」という虚構

