「旅館の諸相とその変遷について」「近代ホテルにおける「和風」の変遷とその諸相」を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/07/11
観光学評論等
溝尾良隆立教大学名誉教授が中心となっている観光研究者の集まりが7月8日池袋で開催された。コロナ後の久しぶりの再会で、楽しい時間を共有した。その機会に東洋大学の内田彩氏から下記論文2編をいただいた。私の論文も若干引用されているので興味深く読ませてもらったが、観光政策研究の立場からは、他分野の観光研究者に、観光政策に関する視点を更に深度化して、観光研究を総合的に推進してもらいたいという思いを強めることとなった。観光政策をきちんと論じる研究者の数が相対的に不足していることが影響しているのであろう。
「旅館の諸相とその変遷について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafit/29/0/29_35/_pdf
「近代ホテルにおける「和風」の変遷とその諸相」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafit/30/0/30_39/_pdf
まず、この論文が何を目的に記述しているかを考えてみた。公権力の行使を前提とする観光政策論としてではないことは明らかであったが、それにしても、旅館業法等の制度に触れる記述が相当程度存在する論文でもあり、言及する以上はこの機会にきちんとした理解を求めたいとの思いを強くした。観光事業論としては、経済的分析がなされていないことから、キーワードの一つが「和風」となっており、私にはあまり知識のない、社会現象論として論じているのかと、とりあえず理解しておいた。その場合には、私などは芦原義信の『街並みの美学』が大変参考になったが、上記論文では触れられていないので、私の理解が不足しているのかとおもっている。研究論文は文化論であろうが制度論であろうが、論じられるものの概念が明確になっていないと、議論んが散漫になってしまう。霞が関の役人は法令を制定する場合に、内閣法制局で概念整理に関する議論を厳しく行われるから、定義に敏感であるが、その経験から本論文を読むと、失礼ながら物足りなさを感じてしまう。
◎観光政策論としての宿泊施設
政策論として宿泊施設を理解する場合、立法資料である国会議事録を読んでおく必要がある。その意味では引用する文献として私の学位論文がまとまっていると思うが、残念ながら他の研究者から引用されたことがない。私のHPにも掲載してるので是非参考にしてもらいたい。しかしそれ以上に、明治からの国会議事録が簡単にネットで検索できるので、時間があるときに読み込んでおくことが後で役に立つとおもう。そのほか、立法時の行政官の発表した論文も補足資料になる。国際観光ホテル整備法は、議員立法であるものの、運輸省観光局発行「国際観光」に数多く投稿されている運輸省職員の国井富士利氏の一連の論文は研究に不可欠のものであり、私の学位論文でも詳細に引用してある。その観点で現行国際観光ホテル整備法を理解するには、観光に関する税・助成制度の理解が不可欠である(学位論文に詳細説明)。税政策から考えると、大蔵省から30年以上前から国際観光ホテル整備法への疑問が呈されており、観光政策としても、宿泊税を是認する立場からは税の減免除が目的の国際観光ホテル整備法は政策的不調和な存在となる。宿泊施設を論じる場合は目を閉ざすことはできないであろう。国際観光ホテル整備法において継子扱いであった国際観光旅館がきちんとした扱いになった1990年代時点では、政策的には税制上の意義付けはなくなっており、規範性の薄い法律となってしまっていたことの認識が、本論文では欠如している。叙勲等への影響を考える制度廃止を望まない官民の意向により皮一枚残ったという印象がある。大手ホテルの経営者は国際観光ホテル整備法の廃止にはそれほど抵抗はないのではと思う。
なお、和式、洋式(中国では西式)論も不十分であり、韓国式、中国式、イスラム式は、国際観光ホテル整備法ではホテル以外のもの、つまり旅館であったことの言及がないことも現代となっては不思議である。また、旅館という言葉が中国から伝来したという言葉ということが引用されているが、孫引きであり、その原典を示さないといけないであろうし、おそらく、そんな単純な言葉ではなかったと推測している。また明治期には、法律上の用語として宿屋が用いられたとも引用されているが、行政機関が定めた規則は存在するものの、法律は存在しないはずであり国会法令検索で確認しておくことが望まれる。あえて記述するのであれば、法令上の用語としなければならないであろう。
ホテル百万石という宿泊施設は、制度上は国際観光旅館として登録されていた。現在の状態は確認していない。いずれにしても、宿泊施設の商品論なり、建築論としてホテル旅館を論じるのであれば、その違いは論じる価値はあるが、政策論として論じる価値は、外貨獲得が政策目的とはならない変動相場制のもと、円が国際決済通貨である以上現在では、なくなっていると考えることが適当である。
◎宿泊施設と居住施設の関係議論の深度化の必要性
「旅館業法が下宿営業にも適用される点において、結果として住宅政策の一部を担っていた」と私の論文が引用されているが、このような形で抜き書きされるとややミスリードである。それどころか宿泊行政イコール住宅行政だったのである。旅館業法は、旧内務省関係法令(現行厚生労働省)であり、治安維持を法目的にしていた規則から始まっている(宿泊業の振興は近年になって加えられたもの)。旧内務省及びそれを引くつぐ厚生省は、居住施設を保有できない社会層に宿泊施設を提供することを行政目的として、下宿、簡易宿所を位置付けていた。現代のように観光施設として宿泊業を位置付けてはいなかった。恒久的居住施設提供、つまり住宅政策を行政目的にするのは、出征兵士が後顧の憂いなく家族を残していけるように、戦時法制から始まったのであり、戦後の旅館業法もそのような時代に制定されていることに認識が必要である。現在でも住宅政策は国土交通省の所管事項ではなく、厚生労働省であり、従って生活保護の住宅扶助が住宅政策の根幹と理解されているのである。簡易宿所料金が住宅扶助費と連動する理由でもある。一方宿泊事業は文字通り旅人を宿泊させる交通機関の補助機関であるということが本来の目的として意識され、法制度の対象とされてきた。食事の提供が制度として含まれないこともそのことから理解されている。この辺りは自分の学位論文を思い出しだし記述しているので不正確かもしれない。
研究者の視点が、施設供給者の視点にウェイトがおかれているから、無理もないのであるが、利用者の視点からすると、不動産賃貸業と宿泊施設提供業は、法的にきちんと区分することは極めて困難であると私は思っている(このブログでも過去何度も記述している)。下宿営業の定義が現在1か月に延長されたが、期間は本質的なことではない。ウィークリーマンションは、民泊法以前から存在しているし、現在でも民泊法ではなく、不動産賃貸借契約で扱われている。不動産施設の使用形態如何で結果として宿泊施設として利用されるということだと考えているが、既存旅館業者の抵抗は大きいであろう。本来は、裁判所で決着しておくといいのであろう。
◎和風ということ
旅館の定義、ホテルの定義でもあるが、キーワードが現代では和風か否かということになることは否定されないであろう。しかし、その和風とは、現代日本人の日常風ではないことも事実である。日本人の生活スタイルは、中国、米国等との違いよりも共通するものの方が圧倒的に多くなっている。幕末期シュリューマン等が紀行文に残しているような、ちゃぶ台、寝具等の生活用具はほとんど見られなくなっている。食事時は会話は禁じられていたことも現在の習慣とはことなる。
コールドチェーンがない時代に、鮮魚が手に入った地域は限られているから、思われているほど日本人は魚を食べていなかったといわれている。結論から記述すると、現在旅館と称されている宿泊施設で提供されている食事は、近年開発されたものが多く、従って、沖縄から、本州の山岳部、北海道の孤島に至るまで、かなりの割合で世界中からコンテナ船で運ばれてきたものが提供されているのである。例外的なものを強調して和式、和風と言ってみても、着物、足袋、下駄等と同様それは例外的であり、すぐに変化してしまうものであろう。個々の宿泊施設が販売上強調するのは理解できるが、研究対象としては、和風に対する見方を変えて論じる事も必要なのではないかと思われる。
トイレについて、欧米の映画では、ウォッシュレットの事をジャパニーズ云々と言ってことがあるが、直訳すると和式、和風である。現代日本人が感じる和風と、外国人が感じる和風は異なるのであろうし、その外国人も地域によって違うかもしれないから、国際観光ホテル整備法が制定された米国人のイメージする和風(日本旅館は混浴というイメージ)とは異なるかもしれない。研究論文としては更に深度化させると面白いはずである。
関連記事
-

-
Ctripの空予約騒動について 大山鳴動に近い騒ぎ方への反省
「宿泊サイト、予約しない部屋を販売」といった表題でテレビが取り上げ、関係業界内ではやや炎上気味であ
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-
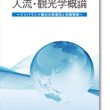
-
電子出版事始め『人流・観光学概論』
大学のテキストで使用するつもりであった『人流・観光学概論』、ウィネットの好意で、校正済みのPDFを
-

-
ウェアラブルデバイスを用いた観光調査の実証実験
動画 https://youtu.be/Sq4M3nvX6Io 10月29日にg-コンテン
-

-
角本良平著『高速化時代の終わり』を読んで
久しぶりに金沢出身の国鉄・運輸省OBの角本良平氏の『高速化時代の終わり』を読んでみた。本を整理してい
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月 を読んで
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月の存在をうかつにも最近まで知
-

-
観光とツーリズム~日本大百科全書(ニッポニカ)の解説に関する若干の疑問~
日本大百科全書には観光に関する記述があるが(https://kotobank.jp/word/%E8

