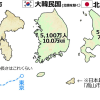観光資源としての「隠れキリシタン」 五体投地、カーバ神殿、アーミッシュとの比較
公開日:
:
観光学評論等, 路銀、為替、金融、財政、税制
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録された。江戸時代の禁教期にひそかに信仰を続けた人々を「潜伏キリシタン」、明治のキリスト教解禁後もカトリックに合流せず先祖伝来の信仰を守る人々を「かくれキリシタン」ないし「カクレキリシタン」と区別して呼ぶらしい。従って隠れキリシタンのほうは遺産というより現役財産である。アーミッシュの人々やヒンドゥーの行者が観光行動の対象となるのと同じであり、私にとってチベットの五体投地をみることが旅行目的になったとことと同じである。それにしては隠れキリシタンはインパクトが弱いと思われる。フィラデルフィアのアーミッシュを見に行ったことがある。もう30年も前かもしれない。まだトランプさんがカジノを現役でやっていたころである。それでも、アーミッシュの人たちに対する敬意を払い、気付かれないように車で遠くから眺めた程度である。今回のチベットでは、五体投地がいたるところで見られたし、観光客用にビジネスでやっているような人もいたから、ビデオにも納められた。カーバ神殿に至っては、信者でなければ近づくこともできないし、見つかったら大変なことになるであろう。これらに比べると「かくれキリシタン」は極めてインパクトが弱い印象があるのはなぜだろうか。急に世界遺産登録のため注目を浴びているような気がする。日本の各地にある風習の一つ程度の印象しかないからである。
江戸時代にキリスト教が禁止されたことは学校教育で学習するから誰でも知っている。また私の世代は眠り狂四郎でそのイメージを持っているが、外国人で潜伏キリシタンを知っているのはまれではないかと思う。ましてやキリシタン禁止の大きな理由の一つに日本人を海外に奴隷売買することの防止強化策があったとすればなおさらである。
以前、宮崎賢太郎著『カクレキリシタンの実像』を読んでいたが、図書館で予約していた中園成生著『かくれキリシタンの起源』が届いたので、両者を比較して考えることができた。
前者はキリスト教を日本風に変えたとする「禁教期変容論」、後者はそれを否定するものである。前者は、いわゆるかくれキリシタンの人々は、昔宣教師が布教したものを、長い歴史の中で自分たちで変えてしまってきた (信仰を変容させた信者)とするが、後者はそれに異議を唱え、各地の日本人が変えたことはなく、各地を訪れた当時の外国人宣教師が、もともと日本人に、そしてその土地ごとに合うように布教しており、そしてどの地でも、それをそのまま信仰してきたのだと結論付けた(そして他の宗教とも信仰並存している)。
中園成生は地元のかくれキリシタンの信仰や儀礼を調査し、16~17世紀に日本で布教した宣教師の記録を丹念に調べた。結果は驚くべきものだった。かくれキリシタンの信仰形態は、現在のカトリックとは異質だ。オラショを呪文のように唱え、聖水を使って病気を治し、日本の神や仏にも敬意を払う。実は昔、西洋から来た宣教師の布教方針は柔軟で、現地にあわせて信仰形態を作った。宣教師が日本から追放されると、潜伏キリシタンは信仰形態を忠実に守り続けた。日本人が勝手に変えたわけではないことを、著者は実証する。
これと立場を異にする本が、宮崎賢太郎『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』である。禁教期のキリシタンは命がけで先祖伝来の信仰を守り通したが、それはキリスト教ではなく、伝統的な神仏信仰の上にデウスという神も拝む民俗宗教だった、と論証する。宮崎氏の本を読むと、今度はこちらが正しく思えてくる。
宮崎は、幾多の迫害を耐え抜きキリスト教への純粋な信仰を守り続けてきた「隠れキリシタン」、というのはおおよそ嘘であるとするから、面白い。「カクレキリシタン」として特異な宗教文化を数百年間に渡りこの国で維持してきた人々の信心のかたちは、日本の民俗的な神仏信仰の風習にキリスト教的な装いを若干付け加えただけであり、その本質は先祖崇拝(供養)と現世利益であるとする。島原の乱を学校で習い、天草四郎の伝説をメディアで印象付けられたものには、驚きである。一部の熱烈な殉教者たちを生んだキリスト教到来の初期の頃は、確かに唯一絶対の神への信仰があったかもしれないが、その後の潜伏時代の信徒たちが教義を正確に理解することはできず、キリスト教に由来する儀礼や慣習は先祖伝来のありがたく(呪術的効力を有する)もないがしろにするとおそろしい(タタリをもたらす)文化へと姿を変えたといわれると、なるほどそうだったのかと思ってしまう。
明治からのキリスト教解禁後も、カトリックに「戻る」人々はあまりおらず、「カクレキリシタン」として先祖が伝えてきた行事を粛々とこなす者が大多数であったようだ。いまやその文化も存続の危機を迎えているが、その理由としてあるのは、「信仰」の弱体化ではなく、過疎化や職務形態の変化、女性の地位向上など、社会的な要因が大きいと宮崎は解説するが、ほとんどの日本人は、無関心ではなかろうか。
宗教学の専門家からの宮崎説への批判もある。つまり、宮崎が「キリスト教」の典型として挙げているのは、彼自身が言うところの「ヨーロッパスタイル」の特徴にすぎないのであり、キリスト教の歴史と世界的広がりの視座にたてば、時代的・地理的制約を免れない。宮崎は日本の宗教的メンタリティーの基層を祖霊崇拝であるとし、お盆・お彼岸・墓参りを中心とした「日本仏教」を、「シャカの教義とは別の日本的受容」であると評価している。それなら、“カクレキリシタンは370年余の弾圧の果てに、ヨーロッパスタイルから教義上は大きく変容し、日本的に土着化したキリスト教である”となぜ言えないのか、との疑問が直ちに湧き、論理が破たんしてしまっているとする。。明確な「クリスチャンの定義」を提示していないと批判する。
いずれにしても、近年観光研究者がパワースポットに着目しているようだが、観光資源としての五体投地や隠れキリシタン等と比較して、ビジネス対象ならともかく研究対象として取り上げるには、いささか早いような気がする。もう少し歴史がある、ゆるキャラ、B級グルメ等ですら風前の灯火になってきている感があり、カニ族、アンノン族、小京都等と同じく、一時期の世相として記憶される程度のものかもしれないのである。
関連記事
-

-
肥後交通グループの第2回オフサイトミーティングに参加して
チームネクストの番外の研修として、熊本県人吉市に所在する中小企業大学校研修室を使用して開催された、肥
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-

-
観光とツーリズム~日本大百科全書(ニッポニカ)の解説に関する若干の疑問~
日本大百科全書には観光に関する記述があるが(https://kotobank.jp/word/%E8
-

-
自動運転車とドローン
渋谷のスクランブル交差点を見ていると、信号が青の間の短い時間に、大勢の人が四方八方から道路を横断して
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-

-
『戦後経済史』野口悠紀雄著 説得力あり
ドッジをあやつった大蔵省 シャープ勧告も大蔵省があやつっている。選挙がある民主主義では難しいこと
-

-
報告「南チロルのルーラルツーリズム発展における農村女性の役割」を聞いて
池袋の立教大学で観光研究者の集まりがあり、標記の報告を聴く機会があった。いずれきちんとした論文になる
-

-
保護中: 『from 911/USAレポート』第827回 「アベノミクスの功罪と出口シナリオ」冷泉彰彦 これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働集約型の観光業を主要産業とするという、どう考えても悲劇的な産業構造に追い詰められた、これは7年半にわたって改革に消極であったことのツケにしても、随分と妙な方向になったと思います
結果的に、これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働
-

-
人民元の動向と中国の通貨戦略 日本銀行アジア金融協力センター 露口洋介 2011.1
中国の現状は。日本の1970年を過ぎたところに当たる 大きく異なるのは、①中国は海外市場で
-

-
『財務省の近現代史』倉山満著 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
p.98 「中国大陸での戦争に最も強く反対したのは、陸軍参謀本部 p.104 馬場