観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
観光学評論等
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたから、ロボットを見てロボットにミラーニューロンを与えるためには、人間の脳の仕組みを正確に理解しないと、完全なるロボット、つまり完全なるAIはできないのだろうと思った。従って、人間の脳の完全なる理解ができるか否かが、AIが実現できるか否かということになるのあろう。少しずつではあるが進んでいることは間違いはない
「インタラクションの認知科学」のまえがき
人は赤ん坊のときから両親や様々な人とインタラクションすることで成長していきます。生活の中でも友達・先生・同僚・上司と日々インタラクションしながら、学んだり、助け合ったり、ときには喧嘩したりと、人と人がお互いに関わり合いながら社会を構成しています。誰かとインタラクションできる人の知性や能力を知ることも、認知科学という人の知的活動の仕組みを明らかにする学問の重要なテーマです。本書は、人とインタラクションできるロボットを題材として、ロボットに必要な仕組みを考えながら、人が行うインタラクションの仕掛けを紐解いていきます。
インタラクションの認知科学を考える上で、なぜロボットを引き合いに出すのかをまず説明しましょう。スムーズにインタラクションが行われるためには、インタラクションの参加者がお互いに共通の仕組みや約束事を持っていたり、共通の情報を持っていたりする必要があります。持っていないと大変な思いをすることは、日本語の話せない外国人と会話する場面を想像するとわかりますね。人とスムーズにインタラクションするロボットを作って行く中で、人の持っている仕組み・約束事・知識を、共通に使えるようにロボットにも入れていく必要があります。問題は、何が共通なものとして重要なのか自体がわからないことなのです。人とインタラクションできるロボットを作ることを通して、インタラクションの中で人がどのような仕組みを働かせ、どのような約束事に従い、どのような知識を活用しているのかが明らかになります。これは、人の知的能力を明らかにする認知科学の目的そのものです。ロボットを活用したやり方で可能になる認知科学研究を知ることができるのも本書の特徴です。
ロボットが人とインタラクションする際に難しいのは、言葉を認識することや、目の前の人を認識することだけではありません。人とロボットが周囲で起きている出来事や周辺にある物を話題として会話することが難しかったりもします。本書は、人とロボットを実際にインタラクションさせた実験をたくさん紹介します。実験を通して、ロボットが人と状況を共有し、自然な形でコミュニケーションする際に必要となる能力がどういうものなのか解説していきます。
インタラクションの実験、特にロボットを用いた実験は、文章だけからでは実際の雰囲気がわからないことが多々あります。実験で何が起きていたのか、ロボットがどのように動いたのか、よりわかりやすく伝わるようにビデオが閲覧できるホームページを用意しました。下記のURLでアクセスしてみてください。人やロボットの些細な動きがいかに影響力を持つのか、本で読んでもわからなかった部分がきっと理解できると思います。
http://www.ailab.ics.keio.ac.jp/webpage_personal/cognitive_robot_interaction/
本書は、認知科学の知見を紹介するとともに、人とインタラクションできるロボットの構造の説明にもなっています。人とコミュニケーションできるロボットを設計する上での基礎知識にもなります。インタラクションにおける人の知的な振る舞いを知りたい人から、人とインタラクションできるロボットを将来作ろうと思っている人まで楽しんで読んでいただける内容になっているかと思います。人の知性、ロボットの知能の双方の側から、インタラクションという現象を解き明かしていきますので、どうぞお楽しみください。
関連記事
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-
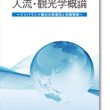
-
電子出版事始め『人流・観光学概論』
大学のテキストで使用するつもりであった『人流・観光学概論』、ウィネットの好意で、校正済みのPDFを
-

-
マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解
-

-
辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-

-
『科学の罠』長谷川英祐著「分類の迷宮」という罠 を読んで
観光資源論というジャンルが観光学にはあるが、自然観光資源と文化観光資源に分類する手法に、私は異議を唱
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
CNN、BBC等をみていて
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
