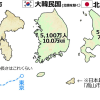千相哲氏の「聞蔵Ⅱ」を活用した論文
公開日:
:
観光学評論等
「「観光」概念の変容と現代的解釈」という論文を偶然発見した。
http://repository.kyusan-u.ac.jp/dspace/bitstream/11178/267/1/sen56-3.pdf
著者は千相哲氏であり、九州産業大の教授をされている。直接面識がないが、日本観光研究学会メンバーで立教大学卒業生であるから共通の知人は存在すると思われる。
内容は、ごく概論的なことで、私の論文でも何度も取り上げていることであるから、繰り返さないが、朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱを活用していることが目に留まったのである。私の知る限り、私以外には、千氏がはじめてである。
商経論叢56巻3号とあるから2015年に公表されている。
私の論文も2015年3月に公表しているからほぼ同時期である。
http://www.jinryu.jp/public/wp-content/uploads/2015/04/%E5%B8%9D%E4%BA%AC%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B4%80%E8%A6%8126-2-15_%E5%AF%BA%E5%89%8D.pdf
しかも、原稿自体は2014年12月にHPにアップしてある。
http://www.jinryu.jp/201412101754.html
更に、2014年11月に発売した私の教科書「観光人流概論」にも聞蔵の記事を掲載してある。
従って氏の論文より私の方が数量分析も伴って半年ほど早いのであるが、ほとんど同時期であり、氏の論文には私の論文の引用がないのも仕方がないのであろう。
また、私の論文は、その後追加論文があり、最終的結論を出している。
http://www.jinryu.jp/public/wp-content/uploads/2016/04/%E5%B8%9D%E4%BA%AC%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B4%80%E8%A6%81%E7%AC%AC27%E5%B7%BB%EF%BD%9C15_%E5%AF%BA%E5%89%8D.pdfhttp://www.jinryu.jp/public/wp-content/uploads/2017/10/%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%A8%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%80%80%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%80%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A68-1%E5%AF%BA%E5%89%8D%E7%A7%80%E4%B8%80.pdf
関連記事
-
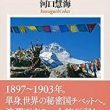
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛著
ディプラーニングを理解しようと読んでみた。 イタチとロボットの会話は全部飛ばして、解説部分だけ読め
-

-
Ctripの空予約騒動について 大山鳴動に近い騒ぎ方への反省
「宿泊サイト、予約しない部屋を販売」といった表題でテレビが取り上げ、関係業界内ではやや炎上気味であ
-

-
日本観光学会に参加して
6月26日日大商学部で日本観光学会が開催され、「字句「観光」と字句「tourist」の遭遇」と題して
-

-
字句「美術」「芸術」「日本画」の誕生 観光資源の同じく新しい概念である。
日本語の「美術」は「芸術即ち、『後漢書』5巻孝安帝紀の永初4年(110年)2月の五経博士の劉珍及によ
-

-
「旅館の諸相とその変遷について」「近代ホテルにおける「和風」の変遷とその諸相」を読んで
溝尾良隆立教大学名誉教授が中心となっている観光研究者の集まりが7月8日池袋で開催された。コロナ後の久