脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら公研10月号が贈られてきており、シンポジウムと同じテーマの西垣通氏の文章がでており興味深く読ませてもらった。
シンポジウムのテーマに脳科学と人工知能が選択された動機は主催者の説明では、人口減少時代を迎え、交通事故死亡者の数倍にのぼる自殺者が出ている現代にとって大きな問題であり、解決手段がAIの活用にあるからだとする。うつ病等の精神疾患のデータがバラバラで解明されていないが、AIを駆使してその脳内メカニズムのビッグデータ解析ができないのかという主催者の問題提起から始まった。このイントロで、「楽しみのための移動」を対象とする観光学もアプローチは正反対だが、ビッグデータを駆使した研究が必要だと感じていたので大いに共鳴した。ただし、精神疾患の場合、原因解明は病気治癒につながるわけであるが、観光学研究では、ヒトの移動するモチベーション解明であるから、それがわかったとしたら、誰でも対応することが可能となり、ビジネスとしての観光は成り立たなくなることになる。このことは、マーケティング全体に言えることである。その一方そのようなことは不可能といったとたんに、では観光学はサイエンスとしては存立できないということになり、マーケティングは博打と同じくサイコロを振って予測するということになるという、やや詐欺めいた研究なのであるということにもなる。
しかし、ことは簡単ではない。ビッグデータなら、テストデータもビックでなければ、数学的に意味がない。汎化誤差というのだそうだ。今のデータ量ではとても無理であるとの説明。10万人のデータ規模でないとということである。しかも、健常者の個人差が、精神疾患患者の個人差の倍もあるということであるから、これまで何の意味もない論文が数多く発表されていたのだという説明を聞き、現在の観光学会のアンケートを中心にした論文のことを思い浮かべてしまった。クロス集計も無理であるとのこと。施設格差が大きすぎて意味がないのだそうだ。病院がそうなら、ましてや観光施設は比較すること自体がナンセンスかもしれない。
それにしても、一を聞いて百を知るという人間は不思議なものである。
合原一幸東大教授が次世代人工知能と数理脳科学につて講演された。ニューラルネットワークとAIは前は交流がなかったが、現在は脳科学と3分野が交流している。神経の研究のため、ヤリイカの人工飼育に成功したというエピソード。現在のノーベル賞委員会に受けそうな話。神経スパイクの回路のモデルの話もあった。しかし人間はわずか20ワットの電源で脳を動かしているようだ。合原氏はattentionの数理モデルを開発中とか。蝙蝠がエサを探すときの脳の働きを分析し、自動運転に応用できると考えている。つまり実際の脳の非線形動力学の解明を目指しているようだ。脳の正常機能の数理モデル、異常機能の数理モデル、ゲノムのモデルから、脳の全体像を解明できないかということのようである
attentionは脳に制約があるから存在するが、AIには制約が少ない。パワーがあればattentionは必要がないのである
参加者からの興味は「人工知能で善悪が判るか」という、人工知能が倫理や道徳に与える影響をテーマにした講演であった。夢が読み取れるようになると、それでいいのかという話は、観光研究に共通する話である。人の行動をビッグデータから読み取れるとした場合、事前に犯罪を予測できるかという問題が提起された。マイノリティレポートというトム・クルーズの映画も紹介されていた。その場合に、例えば特定の人種のある社会背景を持った人たちがかなりの確率で犯罪を犯すと予測するデータを反道徳的として禁止できるか否かという問題提起である。AIのアルゴリズムにそれを書き込むことの問題提起であるが、フロアーから、それは受け止める人間の問題ではないかという意見が提起された。しかし、講演者は、人を殺してはいけないという命題に対して、刑の執行者は例外である等際限なく但し書きが必要となるはずであり、難しいのではないかという答えをされた。確かに、自動運転車の場合のアルゴリズムを作成するにあたって、事故が回避できない場合に、誰をはねていいのかいいのかというアルゴリズムが必要なのかもしれないが、そんなアルゴリズムは反道徳的となるのであろう。
ロボットのアイボ供養をする日本人のメンタリティの話がでて、針供養、人形供養をする伝統があるからだとの説明があり、さらに追い打ちをかけるように、実は、これらの供養は古くはなく、江戸時代にはなかったということで、伝統は古くはないという次節の補強材料がまた一つ増えることになった。でも、ネットには人形供養400年の歴史があるという長福壽寺が出ているが、嘘だとすると住職は大したものである。多分「現在のような供養の形は、すでに江戸時代に原型はあったようだが、上記のような有名どころでも供養が始まったのは昭和や平成になってからである」https://dot.asahi.com/dot/2017101300060.html?page=2という説明が正しいのであろう。
西垣通氏の論文 氏の話は「概念というものは社会的なもの」という一語に尽きる。「コンピュータが社会的概念を認識できるようになったわけではないのに、深層学習を過大評価した。それがAIが人間の知を超えてゆくという話ににもつながっていってしまった。困ります。」「将棋や碁は有限状態ゲーム」「宇宙あるいは世界というものは、一種の調和、秩序を持っている。それは音楽によってハーモニーとしてあらわされている。同時にそれは数学的・論理的な秩序を持つ幾何学であり神学。神様に行き着く。そこからバッハの平均律が生まれ、ニュートン力学が花開いて行く」といつもの西垣節が展開されていた。
関連記事
-

-
『公研』 2018年2月号 「日本人は憲法をどう見てきたか?」
歴史は後から作られるの例である。 境家史郎氏と前田健太郎氏の対談 日本国民が最初から憲法九条
-

-
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛著
ディプラーニングを理解しようと読んでみた。 イタチとロボットの会話は全部飛ばして、解説部分だけ読め
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-

-
字句「美術」「芸術」「日本画」の誕生 観光資源の同じく新しい概念である。
日本語の「美術」は「芸術即ち、『後漢書』5巻孝安帝紀の永初4年(110年)2月の五経博士の劉珍及によ
-

-
シャマンに通じる杉浦日向子の江戸の死生観
モンゴルのシャマン等の観光資源調査を8月に予定しており、シャマンのにわか勉強をしているところに、ダイ
-
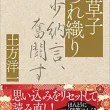
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
2015年「特攻」 HNKスペシャル
http://www.dailymotion.com/video/x30z4ho フィリピ
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
-

-
「DMO」「着地型観光」という虚構
DMOという新種の言葉が使われるようになってきていますが、字句着地型観光の発生と時期を同じくします。
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h


