有名人の観光資源化
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
観光資源
昔懐かしい、T新聞I記者から電話があった。有名人を顕彰する博物館が崩壊しそうであり、何か観光資源として知恵が出せないかということであった。そこでネットを基にいろいろ調べてみた。I記者は私が加賀市山中温泉に所在した森光子記念館の顛末を承知しているから取材されるのであろうと思い、加賀山中温泉の森光子記念館にも触れてみたい。
まず、有名人を顕彰する施設は、おそらく世界中に存在するが「有名人」である限りは存続の道はあるのであろう。問題は「有名人」でなくなった場合である。有名人でなくなっても、文化的価値、宗教的価値、学術的価値があれば、当該顕彰物は存置される可能性がある。単独では難しくても、より広範な施設に引き取られることは考えられ、運が良ければ大英博物館に引き取られることもあるであろう。
世界を見渡せば、エルビスプレスリー、ビートルズが代表例として存在する。メンフィスにはまだ行ったことがないがエルビスを顕彰する施設がある。エルビス自身の肖像権を管理する団体もあるはずだが、それに限らず、グレイスランドの前の通りはエルヴィス・プレスリー・ブールバード(大通り)といい、世界中のプレスリーのファン、ファンクラブからの募金のみで運営しているセイント・パウロ・エルヴィス・プレスリー記念病院もある。リバプールはビートルズの出身地、マジカルミステリーツアーという旅行商品が販売されており、私も利用した。ストロベリーフィールド、・ペニーレイン、・マシューストリート、・ジョンの家(ツアーでしか入れない)・ポールの家(ツアーでしか入れない)等に手軽に回れ、値段は3千円程度であった。つまり町ぐるみ顕彰するビジネスに成長しているのであり、実在しないものでも、ピーターラビットとコッツウォールズなどもその成功例なのであろう。
日本でも寅次郎と柴又は成功事例であるが、その後の継続の可能性は地元の力による。
もう一つの成功事例は、基金の設立である。基金があれば永続性が確保できる。松井秀喜は大リーガーの盟友ジータの発想にならい、自ら基金設立「松井55ベースボールファウンデーション」を設置しているという。将来この基金を基に松井を顕彰する施設が設立される可能性はあるから、仮に松井秀喜が有名人でなくなっても継続できる。長嶋茂雄に関しては生家の保存も危ういと報道されている。読売新聞社がどうするかであるが、難しいであろう。世間によくある〇〇御殿の大半も崩壊しており、明治の元勲の屋敷等が一部財団等で保存されているものがある程度である。相撲は一代年寄という制度を設けており、知恵が出されているものの、化粧まわし等は支援者等の個人財産となっているものが多い。
両者の例で理解されるように、有名人の検証施設が継続できるのは、簡単にまねができないということであろう。地域とのつながりは、歴史と時間を必要とする。単に生まれたぐらいならどこにでもある。裕次郎と小樽も裕次郎の名前ビジネスであったのだろう。彼が小樽開拓者のリーダーだったならまた違ったのであろう。日本中に石原プロダクションンの話があるから、警戒もされるのである。基金も簡単にはまねができない。有名人の遺品をめぐって、遺族や関係者の醜い争いが起きないことを前提としなければならないが、争いが起きるのが常である。
加賀山中温泉には、森光子記念館と片岡鶴太郎美術館がある。前者は短命であった。
市長時代に、加賀山中温泉八百年継続した吉野家が倒産し、湯快リゾートホテルが引き取ってくれた。しかし、天皇陛下宿泊の別邸依緑苑は商業施設としての継続が難しく、加賀市が引き取ってほしいということであった。財政負担が伴うことから、議員の中には消極的な意見もあった。えてしてこの手の寄付を受けるのは、市長の個人的趣味に左右されるという批判がある。しかし、天皇陛下三代にわたりご宿泊され他という歴史は重要であり、寄付を受けることにした。この別邸の活用をめぐり、加賀山中町関係者の一人から、森光子記念館にしてほしいという要望が内々出されてきた。森光子さんは文化勲章受章者であり、菊の湯の名誉館長であったから、市としても十分に大儀はたつが、遺品の管理には責任が伴うものであり、遺族から市に寄贈してもらわないと受けられないと条件を出した。ところが、遺品の所属をめぐり、関係者で話がつかなかったのであろう、依緑苑ではなく、自分たちで個人的に運営するということに落ち着いた。開館当時は人気も高く、ビジネスとして成功したかのように見えたのだが、森光子さんの名声であっても、競争施設が数多くあり、北陸新幹線開業まで持たなかったのある。
一方、片岡鶴太郎美術館は、大手山中漆器経営者(現在は故人)が個人で片岡鶴太郎さんの作品を収集し、自宅の屋敷の一部に掲示しているものである。いってみれば、芸術家片岡鶴太郎氏のパトロンとして作品を買い上げているとうことで、これにより利益を出そうというものではない。しかし片岡鶴太郎の作品の評価が高まれば価値はでる可能性はある。贅沢な楽しみであるが真似はしにくい。
観光資源開発に関する意見をよく聞かれる。
地域の観光資源は地域の個性の発揮であるから、他の地域に真似のできないものが必要である。
ゆるキャラ、B級グルメはすぐにまねができる。1年で作ったものは1年で真似をされる。百年かかったものは百年真似されないのである。
岐阜県にある「日本大正村」は高峰三枝子さんを初代館長に、現在は竹下景子さんが勤めている。県の支援も受けて町ぐるみであるが、大変であろう。あと50年は頑張れるかである。
加賀温泉郷には赤瓦の家並みがある。おそらく明治以降形成されたのであろうが、百年はかかっているから、地域のシンボルカラーにしては提案したことがある。
これから百年かけて赤瓦の家並みを復元すればいいと思ったからである。補助金など出さずに、自分の意思で赤瓦にしなければ意味がない。
残念ながら、地元には理解されておらず、もっと短期のものを望まれているようである。
関連記事
-

-
偽物が本物を上回る例 コスモスの「ロッチビックリマンシール
https://www.youtube.com/watch?v=vwBlC73ZmuE
-

-
マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-
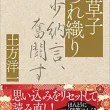
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-

-
『「食べること」の進化史』石川伸一著 フードツーリズム研究者には必読の耳の痛い書
食べ物はメディアである 予測は難しい 無人オフィスもサイバー観光もリアルを凌駕できていない
-

-
小川剛生著『兼好法師』中公新書 安藤雄一郎著『幕末維新消された歴史』日本経済新聞社
『兼好法師』 現在広く知られている兼好法師の出自や経歴は、没後に捏造されたもの。 一世紀を経
-

-
ハイフンツーリズム批判と『「日本の伝統」の正体』藤井青銅著
観光研究者が安易に○○ツーリズムを提唱していることへの批判から、これまで伝統や歴史は後から作れると述
-

-
マザーテレサ 歴史は後から作られる例
マザーテレサについて、ウィキペディアは、正反対の記事を二つ載せている。 スコピオを旅行したと
-

-
2015年「特攻」 HNKスペシャル
http://www.dailymotion.com/video/x30z4ho フィリピ
- PREV
- 通訳案内士と旅行業法等の関係
- NEXT
- 国際観光収支の黒字に意味があるのか?


