「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料, 観光資源
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。
一世一元制は古くからの伝統ではなく「明治に始まる伝統」にすぎない
元号法は伝統を根本的に変えた 天皇が時を支配することにあるなら、天皇が制定権者でなければならないが、元号法は政令で定めるとして決定権は内閣にあるとした
翌年に改元 する「踰年改元」の伝統がなくなった。元号法は「代始改元」を定めたものの、「継承があった場合」として改元時は旧皇室典範以上に不明確になった。
出典の伝統も変わった。漢籍からではなく、万葉集
明治に始まる一世一元制は天皇主権と不可分であり、元号自体はともかく一世一元制は違憲。現在の「平成最後の××」とかの言葉が横行 国民主権意識を阻害している。
関連記事
-
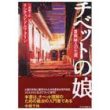
-
『チベットの娘』リンチェン・ドルマ・タリン著三浦順子訳
河口慧海のチベット旅行記だけではなく、やはりチベット人の書物も読まないとバランスが取れないと思い、標
-

-
鬼畜米英が始まったのは、1944年からの現象 岩波ブックレット「日本人の歴史認識と東京裁判」吉田裕著
靖国神社情報交換会に参加した。歴史認識は重要な観光資源であるとする私の考えに共鳴されたメンバーの
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の
-

-
童謡「赤とんぼ」から躾を考える
村のしつけが対象とするのは正規メンバーだけで、共同体からはみ出た子供たちは、アウトサイダーとして
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
『日本軍閥暗闘史』田中隆吉 昭和22年 陸軍大臣と総理大臣の兼務の意味
人事局補任課長 武藤章 貿易省設置を主張 満州事変 ヤール河越境は 神田正種中佐の独断
-

-
動画で考える人流観光学 マクスウェルの悪魔
【物理学150年の謎を日本人教授が解明】マクスウェルの悪魔が現れた!/東京大学 沙川貴大教授/教え子
-

-
『デモクラシーの帝国』 藤原帰一2002岩波新書 国際刑事裁判所 米国の不参加
国際刑事裁判所の設立を定めたローマ規程は、設立条約に合意していない諸国にも適用されるところから、アメ
-
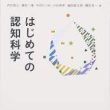
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-

-
試験問題1(歴史や伝統は後から作られるということを何度か述べました。その実例を自分で考えて3編以上紹介し、観光資源としての歴史、伝統の活用について、400字以内で論述せよ。)
この設問は、事前に講義中に出題しておいた。実例を自分で探してもらうためだ。出席していない学生は教科書

