『QUORA 日本人の賃金が30年間増えなかった理由』vs 渡辺努東大教授の「物価と賃金の心地よい状態」説
公開日:
:
出版・講義資料
渡辺努「世界と日本の物価に何が」2022年12月13日 (火)
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/477384.html
物価は消費者物価指数という統計で見るのがもっとも一般的です。
消費者物価指数は約600の品目から構成されています。600品目の中には、シャンプーなどのモノはもちろん、理髪料金などのサービスも含まれています。

この図は、600品目のそれぞれについて前年の同じ月からどれだけ上がったか下がったか、つまり個別の品目ごとのインフレ率を計算し、その頻度分布を描いたものです。横軸は品目別のインフレ率です。たとえばプラス20%というのはその品目が20%上昇したことを、マイナス20%はその品目が20%下落したことを意味します。縦軸は、その品目が600品目全体に占める割合を示しています。
この図から読み取れる第1のことは、高インフレの進行です。電力などエネルギー関連の品目が10%を超す高い伸びとなっています。これは、海外発のインフレが国境を越えて侵入してきているということを示しています。これを「急性インフレ」と呼ぶことにします。
この図のもうひとつの注目点は、横軸のゼロ%の近辺に鋭角的にそびえたつピークです。これは多くの品目がインフレ率ゼロの近辺に集中していることを意味しています。正確に計算すると、私たちが日常的に購入するモノ・サービスのうち約4割がゼロ近辺にあることがわかります。言い換えると、日本の企業の約4割は昨年と同じ値札をつけているということです。
ゼロ%のところに高いピークがあるという特徴は、日本が金融危機に襲われた1990年代後半から観察されるようになりました。それがいまなお続いており、日本経済の慢性的な病となっています。これを「慢性デフレ」と呼ぶことにします。
米欧のデータを使って同じ図を描いてみると、急性インフレは日本と同じように表れますが、ゼロ%にそびえたつピークは見られません。つまり、慢性デフレは日本に特有の現象だということです。約4割の品目が価格据え置きになっている、だから日本のインフレ率は米欧との対比低いのです。
「急性インフレ」と「慢性デフレ」という2つの病を抱えるという日本の問題の複雑さは、米国と比較するとはっきり見えてきます。
米国の病は急性インフレだけなので、その治療だけに専念すればよいことになります。インフレが問題であれば、治療は金融引き締めです。
実際、米国はその治療をすでに実行に移しています。金融の世界はグローバルに繋がっているので、各国の中央銀行が行う金融政策は、多くの場合は同じ方向を向くようになります。ところが、2022年現在、米国が引き締めを始めているのに対し、日本は金融緩和を維持しており、政策の方向が正反対を向く結果となっています。
日本も米国と同じように引き締め始めれば、急性インフレという病にはよい効果が期待できます。しかし同時に、引き締めにともない生産や雇用は悪化するので、消費者は生活防衛に走ることになるでしょう。そのとき消費者は、いまよりもさらに価格に敏感になります。そうすると企業は、価格を引き上げによって顧客を失うリスクが高まったと認識し、価格を据え置くという姿勢をさらに強めることでしょう。その結果、図のゼロ近辺の品目はさらに増加し、そびえたつピークはもっと高くなります。
このように、金融引き締めは急性インフレという病は癒すことができますが、同時に、日本が長年患ってきている病、慢性デフレをさらに悪化させてしまうことにもなるのです。
*****
そもそも慢性デフレはなぜ起きたのでしょうか。その仕組みのカギは賃金です。物価の据え置きがはじまった90年代後半は同時に賃金の据え置きが始まった時期でもありました。賃金が据え置きなので企業としては価格を引き上げる理由がありません。一方、労働者は、物価が据え置きなので、賃金が据え置きでもさほど困りません。本音を言えば、労働者は賃上げが欲しいでしょうし、企業は値上げが欲しいでしょう。しかしそこまで欲張れないとすれば、両者ともに据え置きというのは、それなりに居心地のよい状態と言えなくもありません。かくして、価格も賃金もともに据え置きというのが、ちょうどよい「落としどころ」になったと考えられます。
実は、この「落としどころ」の土台が大きく揺らぐということが現在おきています。先ほど述べたとおり、日本のインフレ率は3.6%で米欧と比べれば低いのですが、それでも私たちの生活が脅かされていることに違いはありません。つまり、価格が据え置きだから賃金据え置きでも仕方ないという、これまでの理屈がもはや通用しなくなっているのです。
そうした中で、労働組合の集まりである「連合」は、インフレから生活をまもるには賃上げが必要との認識のもと、来年の春闘の賃上げ目標を5%に設定すると発表しました。近年の賃上げは2%程度でしたからそれと比べるとかなり高い水準です。そんな高い水準を要求するのは無謀だという指摘もあります。しかし物価が3%を超える率で上昇する中で賃上げ5%というのは決して無理な要求ではありません。どちらかと言えば低すぎるくらいです。
*****
物価上昇で国民の生活が苦しくなるのはピンチです。しかし、いまの状況は、見方によってはチャンスともいえます。価格も賃金も据え置きという、これまでの日本から脱却し、価格と賃金のダイナミズムを取り戻す絶好の機会だからです。ピンチをチャンスに変えることができるかどうかはすべて来春、十分な賃上げを実現できるかどうかにかかっています。社会全体として、賃上げの機運を高めていくことが大事です。
QUORA
なんとなく見聞きするニュースや感覚値では知っていた事実ではありますが、こうやって定量化したグラフにされると、ちょっとダメージがデカイですね…。
一方で、日本の法人税率の推移が下記のグラフです。
働く人の賃金が据え置かれているのにも関わらず、法人税率は下がっています。ミクロな視点で見ると当然その間に大企業の倒産などはありましたが、それでも日本経済全体で見れば、リーマンショック時の年などを除けばGDP成長率も0.3%~2%程度を保つなど、僅かではありますが一応経済成長もしています。
つまり、経済成長で生み出された利益、下げられた法人税で浮いたお金は内部留保と配当金に消えていたわけです。
本来、法人税率の引き下げは海外の資本を参入しやすくするため、という側面もありましたが、本来は税金に払っていたお金を従業員の給料や設備投資にまわして、個人消費や設備の更新を刺激して経済を回すシナリオでした。
しかし、実際には従業員の給料はずっと据え置かれ、役員報酬もそれに比べたら上がりはしましたが、それでも欧米の主要企業の水準に比べれば日本の役員報酬はずっと低い方です。
このグラフだけを見てよく「日本は格差が!」「金持ちに不当に利益を搾取されている!」という人がいますし、言いたい気持ちもわかりますが、事態はそう単純ではないと考えています。
個人的な考察ですが、このようなことになってしまった背景には、政府の責任もありますが銀行の責任も大きいと考えています。
これらの数値の中で一番の問題が「内部留保」です。内部留保はつまり、貯金ということですね。
なんだかネットニュースなどを見ていると、世の中の会社経営者というのは全員利益を不当に自分のポケットに入れようと悪巧みをしている奴らという前提で書かれている記事が多いですし、一部にはそういう経営者もいるでしょうけど、実際はごく少数でしょう。
ほとんどの経営者は自社の生産性を上げるにはどうすれば良いかに日夜頭を悩ませています。そして、生産性を上げるために何をするのが一番カンタンかと言えば、この2点に尽きます。
- 従業員の給料を上げること
- 常に最新の設備を整えておくこと
この2点を行うことができれば、世の中に数多ある美辞麗句が並んだハウツー本や経営者向けセミナーなどすべて無意味になります。
高度経済成長の頃の日本は、今じゃ考えられないくらい法人税が高額でした。どうせ税金に取られるくらいなら…と、利益を極力従業員の給与やボーナスに還元したり、設備投資をしたりしてお金を使っていました。これが日本人の個人消費をうまく刺激し、次々と世界で通用するようなコンシューマー向けの家電製品を開発、販売するような企業が現れました。
なぜそのようなことができたかと言えば、当時の日本には地銀、都市銀合わせて数多の銀行があり、設備投資や従業員の給料に利益を使ってしまっても、新たなビジネスを始めるときは銀行にお金を借りれば良い、という社会的な了解があったことが背景にあります。
しかし、バブル崩壊以降の日本はどうか…。不良債権処理に失敗した日本の多くの銀行は苦境に立たされ、体力のない銀行は破綻の憂き目に遭います。その結果に起きたのが、銀行による企業への厳しい貸し剥がしと貸し渋りです。
それらと当時進行で経営が厳しくなった銀行は次々と合併を繰り返し、銀行そのものの数が激減しました。
銀行の貸し剥がしと貸し渋りに耐えきれず倒産した日本企業も数しれず…。1990年代中盤から2000年あたりの不況の構図はだいたいこんな感じです。
このあたりから、日本では「銀行はいざというときに助けてくれない」というイメージが定着し始めます。そして、今の大企業の経営陣などは、世代的にもだいたいこの時代に30代や40代などの働き盛りだったわけで、こうした銀行の態度をよく見ていて、しかもまだまだ鮮明にその時のことを覚えているはずです。
ですので、いざという時に銀行が助けてくれないのなら、自分たちでなんとかしなければなりません。つまり、「貯金=内部留保を増やす」という発想に繋がって行くのです。配当金を増やすのも内部留保が増えたのと同じ発想で、新たなことを始めるときに必要なお金を銀行が貸してくれないのなら、株式市場から調達するしかありません。では、株を買ってもらうために何をしなければならないかと言うと…配当金を増やす、という発想になりますよね。
この20年間、日本経済で起きていたのはだいたいこのようなことでした。
よく20年間所得が増えなかったことを挙げて「日本は貧しくなった」とか「搾取が起きている」と言う人がいますが、実際には日本は微増ながらも経済成長はしているし、イメージほど役員報酬が高いわけでもありません。それどころか、給料や設備投資の原資にできるよう、法人税の引き下げという政策まで行われていたのに、結果は狙いとは真逆の方向に行ってしまいました。
このような現状を憂いて、最近は保守派からも「法人税率を下げすぎたんじゃないか?個人消費も冷え込み過ぎだ。だから法人税率を上げて消費税を下げたらどうか」なんて声が聞こえるようになりました。
…え!?これってこの20年間、日本共産党がずっと主張していたことと一致しています(笑)。
ですので、最近は経済保守派と日本共産党が同じことを言い出しているという、摩訶不思議な状況に陥っています。
関連記事
-
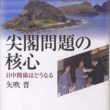
-
『尖閣諸島の核心』矢吹晋 鳩山由紀夫、野中務氏、田中角栄も尖閣問題棚上げ論を発言
屋島が源平の合戦の舞台にならなければ観光客は誰も関心を持たない。尖閣諸島も血を流してまで得るもの
-

-
『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、
-
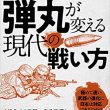
-
『弾丸が変える現代の戦い方』二見龍 照井資規 誠文堂新光社 2018年
本書は、今までほとんど語られてこなかった弾丸と弾道に焦点を当てた元陸上自衛隊幹部と軍事ジャーナリ
-

-
「温度生物学」富永真琴 学士会会報2019年Ⅱ pp52-62
(観光学研究に感性アナライザー等を用いたデータを蓄積した研究が必要と主張しているが、生物学では温
-
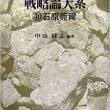
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-

-
運輸省(航空局監理部長)VS東亜国内航空(田中勇)のエピソード等
https://www.youtube.com/watch?v=flZz_Li7om8
-

-
『海外旅行の誕生』有山輝雄著の記述から見る白人崇拝思想
表記図書を久しぶりに読み直してみた。学術書ではないから、読みやすい。専門家でもないので、観光や旅行
-

-
「脳コンピューター・インターフェイスの実用化には何が必要か」要点
https://www.technologyreview.jp/s/62158/for-brain-
-
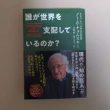
-
ノーム・チョムスキー著『誰が世界を支配しているのか』
アマゾンの書評で「太平洋戦争前に米国は自らの勝利を確信すると共に、欧州ではドイツが勝利すると予測

