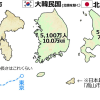『平成経済衰退の本質』金子勝 情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘 情報と人流のずれが、過剰観光
公開日:
:
最終更新日:2023/07/16
出版・講義資料, 路銀、為替、金融、財政、税制
いつも感じることであるが、自分も含め観光学研究の同業者は、研究原理を持ち合わせていないということである。エコツーリズムがその代表であるが、近年はあまりエコツーリズムを言わず、エコツーリズムをっていた者がオーバーツーリズム等を言い出す始末である。
金子勝氏の著書を読んで、説明方法にヒントを得た。氏は情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘している。この論法を用いれば、スピードの一番遅い自然・農業と観光には大きなタイムラグが出るから、観光からすればエコツーリズムを叫ばざるを得なくなると説明できる。情報と人流のずれが、過剰観光である。日本人観光客よりも外国人観光客に大きく表れる。
現物給付は地方に権限を持たせる。年金のような普遍的給付は中央政府だが、介護や足の確保は自治体である。その点で日本は特殊な国である。
今週末旅行作家協会で講演をする。東京オリンピックで旅行客が増えるか否かという質問が想定される。金子氏流にこたえるとすると、 米中貿易戦争が激しくなると、投機マネーの行き場を失わせるから、バブル崩壊が起こるかもしれず、旅行などといってはいられなくなる。そういえば、リーマンショック後アジアだけが成長、日本だけが取り残されたから、安い日本に周りの観光客が増加したのは必然だったと説明できる。中国がこの地域との結びつきを強めている 日本の輸出半数以上アジアである。
の『平成経済衰退の本質』の内容は「 バブルとバブルの崩壊から始まった平成時代。マクロ経済政策も、規制緩和中心の構造改革も、「失われた20年」を克服できないどころか、症状を悪化させてきた。セーフティネット概念の革新、反グローバリズム、長期停滞、脱原発成長論などをキー概念に、一貫して未来を先取りした政策提案を行ってきた著者による30年の痛烈な総括」であり、書評には「
本書によると、平成の30年間に進行した日本の経済的衰退は世界史的過程であってほぼ不可避だったようですね。絶対に避けられないものではなかったにせよ戦後日本が築いてきた社会体制がそれを阻んだ。戦後50年の圧倒的に成功した仕組みがそう容易に変わるわけはない。その意味で不可避だったというわけです。衰退の帰結としての格差社会、そこに至るまでの因果連鎖をたどるとやはりバブル崩壊が起点。しかしバブルは変動相場制への移行という国際経済システムの変化によって準備されたものであり、今日世界全体がバブル循環に苦しめられている。日本はその最初の犠牲者であったに過ぎない。
しかしただ経済が衰退するだけで格差社会は生まれない。格差の主要因は非正規労働の拡大にある。その誘因となったのは職業別に分断された年金制度や健康保険制度。これこそ戦後日本を成功に導いた「会社主義」の帰結であり、格差社会は戦後の社会体制がその仕組みの中で経済の衰退過程に適応しようとした結果だというわけですね。著者によれば、アベノミクスは政府が日銀と結託して金融緩和や株価の吊り上げによって経済の実態を隠蔽し国民を欺く欺瞞的な政策に過ぎない。経済を建て直そうと続けられてきた金融緩和は銀行の収益を減らし、新規産業へのリスクをとった貸付を難しくしてしまい、むしろ経済の建て直しを阻害する結果になっている。こうした状況は、成功した社会体制が終わりを迎える最後の様相としては歴史的にはよく見られる状況である。残念ながら私たちはそういう時代に居合わせてしまったのだろう。こうなったらもう腹を括るしかない。本書を読んでそんな気持ちになった。
経済学研究者馬場宏二 「富裕化と金融資本」 現代資本主義論のキイワードは大衆的富裕化である。マルクス経済学は、古典的窮乏化論や資本主義停滞論に固執することで、この現実への説明力を喪失してしまった。本書は、宇野金融資本概念の再検討・改鋳によって、富裕化現象をときあかそうとするもので、貧困論から富裕化論へのマルクス経済学のパラダイム転換を企図した野心的試論集である。
「大衆消費社会の賛美の中に隠された大量の資源浪費と環境破壊を伴う過剰富裕化」といった字句がみられる。ラグジェリーツーリズム等というのんきなことを言っている同業者がいるが、どう考えるのであろう。
『日本経済史』有斐閣 武田晴人著
pp.299-300限られた可処分所得と一定に水準に達した生活水準の下で、追加的な消費の方向は個性的で、差別化されたものが求められた。それは、生産システムに対して新たな大きな負荷を課すものであった。大量生産の技術的な基盤となっている現代の技術は、このような生産方式の変化には迅速には対応できなかった。その結果、生産性の上昇が鈍い部門へと産業構造が重心を移すこととなり、経済成長の減速は不可逆的な変化として定着した。
25人に一人が死亡、行方不明 7222万人となる。
船舶の被害が最も大きく、鋼材生産設備や水力発電はそのまま。民需用設備の大な生産能力の低下は、空襲ではなく戦時動員の転用の結果であった。
戦後のインフレと高度経済成長は、その結果であったが、戦後賠償問題の帰趨により変わった可能性があった。
p.379 高度経済成長期の日本では国民の税負担率が軽い一方で、社会的給付水準も低く、ヨーロッパに比べ半分程度の水準に過ぎなかった。社会保障政策を介した財政による所得再分配効果は限定的であった。
関連記事
-

-
2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教
-

-
『金語楼の子宝騒動』(「あきれた娘たち」縮尺版)少子高齢化を想像できなかった時代の映画
1949年新東宝映画 私の生まれた年である。嫁入り道具に風呂敷で避妊薬を包むシーンがある。優生保護
-

-
保護中: 『市場と権力』佐々木実を読んで
日銀が量的緩和策で銀行に大量にカネを流し込んだものの、銀行から企業への融資はそれほど増えなかった。
-
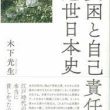
-
『貧困と自己責任の中世日本史』木下光夫著 なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追及する社会となってしまったのか。それを、近世日本の村社会を基点として、歴史的に考察
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか 奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村
-

-
1936年と2019年のホスピタリィティ比較
『ビルマ商人の日本訪問記』ウ・ラフ著土橋康子訳を読むと、 1936年当時の日本の百貨店のことを、店
-

-
岩波書店の丁稚奉公ストライキ
『教科書には載っていない戦前の日本』p.222 封建的な雇用制度の改善を求めて岩波書店側に突
-

-
Quora 「汎化性能」
すべてのデータサイエンティストが知っておくべき、統計学の重要なトピックはなんでしょうか?
-

-
『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、
-

-
脳波であらすじが変わる映画、英映画祭で公開へ
映画ではここまで来ているのに、観光研究者は失格である。 http://jbpress.isme