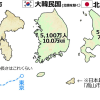国際観光収支の黒字に意味があるのか?
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
路銀、為替、金融、財政、税制
観光基本法が全面改正された法制上の大きいな理由は、中央集権規定の廃止であった。農業基本法等戦後成立した基本法はみな中央集権規定が例文のように存在したが、それらの規定は順次基本法が全面改正されるたびに廃止されていった。最後に残ったものが観光基本法のそれであったが、観光基本法はあってもなくてもよい基本法であったため、中央集権規定が存在しても実害がなかったのである。
私が観光協会在職中、二階俊博代議士が観光基本法の改正について新年賀詞交換会で触れられた機会に、議員会館にお邪魔をして、観光基本法の問題点をご説明させていただいたことがある。佐伯宗義代議士が当時この中央集権規定がある観光基本法に大反対をしたことを申し上げると、二階先生は佐伯宗義代議士のことをご存じであった。
ふたを開けてみて、私も驚いたことがある。法律名が観光立国推進基本法になっていたことである。条文作成は衆議院の法制局職員であったろうが、大枠は二階代議士が決めたはずであり、字句「観光立国」を二階先生はご自身の著作でも用いておられるから、相当気に入っておられたのであろう。
さて、基本法の政策理念である。総花的な記述はさておき、外貨獲得の政策理念は日本の場合不要どころか、逆に国際問題視されかねない。自由な活動にゆだねるほうが良いと考えられる時代になっている。アウトバウンドもインバウンドもである。そこで、政策理念として、国、地域の誇りの理念が記述されることとなっていた。日本の国際的地位に比べて、日本を訪問する外客数があまりにも少ないという珍しい字句が前文に挿入されている。教育基本法を制定した直後の第一次安倍内閣の時である。観光基本法はもちろん議員提案ではあるが。
トランプ大統領が盛んに貿易赤字を問題視している。日本の観光研究者も観光収支の黒字の是非を頭から疑ってかからない者が多い。しかし、浅川雅嗣財務官は、『公研』2017年7月号で、二国間の貿易収支の黒字、赤字に着目することがどれほど意味があるのか、正直疑問なしとはしないと述べておられる。(浅川氏は私が海事産業課長時代に主計局の運輸省担当主査で、国際船舶制度の予算要求をさせていただいたことがある。)氏は、貿易が行われるその裏側で、それよりもはるかに巨大な額の資本取引が行われているわけだと述べられる。要は投資が多すぎて、貯蓄が足りないということだとバッサリ切り捨てておられる。
浅川氏の言葉を借りれば、日本の国際社会に占める地位を考えると、政策として、旅行収支の黒字に着目する意味がどれほど意味があるのかということにもなる。国際旅客運送収支はオープンスカイ政策により、ナショナルフラッグキャリア概念すら消滅している。頭数としての外客数が増加することは、日本の文化を見てもらうという視点では好ましいことであり、子供たちに自慢できることある。しかし、政治的には旅行客を送り出す方が力を持つことは間違いがない。モノの見方であるから仕方がないのである。
中国は、域外旅行客が2億人になると予想している。団体客は安売りツアーを規制する方針のようであるが、個人旅行は規制できず確実に伸びる。世界中の観光地が中国人旅行客の獲得競争に乗り出せば、中国の政治的力が増すことは仕方がないのである。
関連記事
-

-
肥後交通グループの第2回オフサイトミーティングに参加して
チームネクストの番外の研修として、熊本県人吉市に所在する中小企業大学校研修室を使用して開催された、肥
-

-
1936年と2019年のホスピタリィティ比較
『ビルマ商人の日本訪問記』ウ・ラフ著土橋康子訳を読むと、 1936年当時の日本の百貨店のことを、店
-

-
『知られざるキューバ』渡邉優著 2018年
4年前のキューバ旅行のときにこの本が出版されていれば、また違った認識ができたとの思う。 カリ
-

-
パブリックコメント「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の一部改正に関する意見公募について
道路運送法の有償性に関する事務連絡の改正が検討されており、パブリックコメントが募集されたので、応募し
-
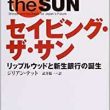
-
『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド
バブル期に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はア
-
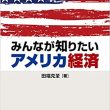
-
書評『みんなが知りたいアメリカ経済』田端克至著
高崎経済大学出身教授による経済学講義用の教科書。経済、金融に素人の私にはわかりやすく、しかも大学教
-

-
『国債の歴史』(富田俊基著2006年東洋経済新報社)を読んで
標記図書を読み、あとがきが要領よくまとめられていた。財政に素人の私には、非常に参考になる。 要約す
-

-
保護中: 対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み
対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み 日本経済新聞【経済教室】2020年6月29
-

-
深夜運転のスキーバス問題の解決方法の一つ
深夜運転のスキーバス事故が発生し、社会問題になりました。飲酒運転や過積載事故が社会問題化し、飲酒運転