英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
公開日:
:
最終更新日:2023/05/21
出版・講義資料, 路銀、為替、金融、財政、税制
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 http://tanakanews.com/があります。ロンドンの配車プリの調査から帰国したばかりでしたので、英国の対外投資姿勢がわかる記事として面白く読んだところです。以下概略掲載しておきますが、本文http://tanakanews.com/150322china.htmを読んでもらった方が間違いはないでしょう。
2015年3月12日、英国政府が、中国が創設した国際開発金融機関である「アジアインフラ投資銀行」(AIIB)への参加を表明した。北京に本部を置くAIIBは、アジア地域の道路や港湾、発電所などのインフラ開発に国際投資する事業を行う予定で、中国が2013年秋から設立を提唱し、14年10月に正式発足した。
従来、国際金融機関といえばIMFと世界銀行という「ブレトンウッズ機関」を筆頭に、米国の覇権運営を補佐する存在だ。アジアではIMF世銀体制下に、日本が歴代の総裁職を占めてきたアジア開発銀行(ADB)がある。近年、中国やインド、ロシア、ブラジルなどの新興諸国(BRICSなど)が経済力をつけ、米国とその傘下の日欧の発言力が圧倒的な国際金融機関の運営体制を変えてほしい、新興諸国の発言力を増加してほしいと要請していた。2010年、IMFで、中国など新興諸国の発言力(出資比率)を増やす改革の方針が決まり、米政府(民主党オバマ政権)も署名したが、共和党主導の米議会が批准を拒否したまま、改革が座礁している。
中国は、世界のGDPの16%を占める経済を持つが、IMFでの発言権(出資比率)が3・8%しか与えられていない。アジア開発銀行(ADB)では、米国の発言権が15・7%、日本の発言権が15・6%で、米国が覇権国、日本が事務局という位置づけの日米支配体制になっている。中国の発言権は5・5%しかない。中国は、経済力の増大とともにアジアでの政治影響力の拡大を望んでいるが、IMFやアジア開銀での発言権の拡大は、米国(日米)に阻止されている。経済成長が続くアジア諸国には巨大なインフラ整備の需要があるが、アジア開銀の投資はその需要に追いつかず、需給のギャップがある。
中国は、その点を突いて、IMFやアジア開銀での中国の発言権の拡大が阻止されている以上、アジアでのインフラ投資需要の増加に応えるため、中国主導で新たな国際開発金融機関を創設するしかないという理論で、AIIBの創設を呼びかけた。中国などBRICSは、AIIBのほか、世界銀行に対抗しうるBRICS開発銀行(新開発銀行)、IMFに対抗しうる外貨準備基金などの国際金融機関も設立した。
中国(やBRICS)を米国覇権外(ブレトンウッズ体制)に押し出して、AIIBやBRICS開発銀行などを作らせてしまった元凶は、IMF世銀でのBRICSの発言権の拡大を拒否した米議会にある。米国のルー財務長官は「共和党主導の議会がIMF改革の批准を拒否したせいで、中国がAIIBを作り、米国の国際的な信用と影響力が脅威にさらされている」と発言している。
AIIBの加盟国は、昨年10月の創設時点で東南アジアと南アジアのほぼすべての国、中央アジアの多くの国と、中東の一部の国だった。米国が、自国の覇権体制(IMF世銀、ADB)の外側に作られるAIIBを嫌い「AIIBは運営の透明度が低い。環境や人権などの問題を無視して投資する懸念がある」と言って、同盟諸国に加盟するなと圧力をかけたため、日本、韓国、豪州、欧州諸国は加盟していなかった。英国が加盟を発表する6日前にも、ケリー米国務長官がドイツに対し、AIIBに加盟しないよう要請していた(ドイツは、この時点ですでに加盟したいと思っていたことになる)。
英国が3月12日に、先進国で初めて加盟を表明した時、米政府の高官は「中国にすり寄ってばかりいる」と英国を非難したが、この敵対的な匿名高官発言は、米国がAIIBに反対する本当の理由が、環境や人権を無視した投資への「懸念」でなく、自国の世界支配(覇権)を邪魔する中国への「敵対」であることを浮き彫りにする逆効果をもたらした。それから数日内に、独仏伊やスイス、ベルギーなどの欧州勢と、アジア周辺の豪州と韓国がAIIBへの参加を正式に発表するか、参加を検討していると表明した。
急速に経済台頭する中国に、英国が「すり寄ってばかりいる」のは事実だ。英国の国家戦略は、ロンドンを世界の金融センターとして維持し続け、国際金融の儲けで存続し続けることだ。米国中心の債券金融システム(米金融覇権)の崩壊感がリーマン危機以来ひどくなり、対照的に中国を筆頭とする新興諸国の経済台頭が顕著になる中で、英国は国際金融センターとして機能し続けるため、米国から罵倒されても、中国にすり寄り続けねばならない。
3月末のAIIBへの創設時加盟の締め切りまであと20日弱という絶妙なタイミング(他の諸国も急げば加盟できる)で、英国が加盟を発表し、それを機に他の諸国がなだれを打って加盟を表明する流れを英国が作り出したことで、英国は、中国に恩を売ることができた。英国は以前、チベットや香港などの人権問題で中国を非難する「冷戦構造(=米英覇権)の維持」を国策としていた。2012年にその国策を捨て、経済面重視で中国にすり寄る策に180度転換したが、最近まで中国は英国に対して懐疑的で、中国首相訪英時の歓迎の赤じゅうたんの長さが数メートル足りないと言って怒るなど、意地悪をしてきた。今回AIIBの加盟で中国に恩を売ったので、中国は英国に意地悪しなくなるかもしれない。
英独仏や豪州は、AIIBに加盟することで、今後ますます増えそうな中国によるアジア向けのインフラ投資に参加でき、自国の金融界や産業界に儲けを与えられる。まさに「中国にすり寄ってばかりいる」といえるが、詭弁家ぞろいの欧州勢は「中国に透明度の高い投資をさせるためには、AIIBに入らず外から批判するのではダメで、創設時から加盟し、内側から改善していく必要がある」と言って、自分たちの加盟を正当化している。投資を受けるアジア諸国の側としても、AIIBに欧州勢が入ってくれると、中国の言いなりにならなくてすむ度合いが高まるので歓迎だ(アジア諸国はAIIBに日本も入ってほしい)。
米国では、上層部に「米国も入るべきだ」という意見があるが、入りそうな感じが現時点で全くない。米国が入ったら日本も入るが、米国が入らないなら日本も入らない、これが日本の戦略だろう。世界でダントツの対米従属だ。今の日本は、中国にすり寄っていない数少ない国の一つだ(中国人観光客に対しては、みっともなくすり寄っている)。しかし日本は同時に、米国の覇権が崩れているのにそれを見ず、米国にすり寄り続ける数少ない国の一つでもある。
オーストラリアは、中国に資源を売ることが経済の大黒柱なので中国と協調したいが、米国の同盟国として中国包囲網に協力して国内基地への米海兵隊の駐留を許すこともやらざるを得ず、台頭して強気になる中国と、好戦的になる米国の間で外交のバランスがとりにくくなっていた。今回のAIIB騒動で、英国が先導してくれたおかげで、豪州は対中協調・米国離れの方向に苦労せず一歩進んだ。
世界銀行の総裁(Jim Yong Kim、米国人)は、これまで不十分だったアジアのインフラ整備への投資を補完してくれるものとして、AIIBの設立を歓迎している。国際協力の現場では、対抗意識が少ない。AIIBがIMF世銀体制の対抗馬であるのは、この問題を国際政治(覇権争い)として見た場合だ。
経済協力として見ると、アジアへのインフラ投資が足りないのだから、設立者が中国だからという理由で米日がAIIBに入らないのはおかしい。中国は、日本にも米国にも、AIIBへの加盟を誘っている。国際協力の経験が豊富な米日など先進国がAIIBに入り、中国による運営の下手なところを助けてやるのが筋だ。
FT紙は、欧州などがAIIBに加盟する動きを、世界がドルよりも人民元を好むようになっていることを象徴するものだと書いている。通貨の分野では、中央銀行による債券買い支え(QE)がないと米国のドル基軸体制を維持できない状態になっている。中国などBRICSは、ドル崩壊に備え、各国の自国通貨を使った貿易体制を組んでいる。ドル基軸体制とIMF世銀体制は同一のものだから、中国がIMF世銀と別にAIIBを作ったのは、ドル崩壊への備えであるともいえる。ユーロ諸国が、ドルより人民元とのつながりを重視し、AIIBに入るのも自然な動きだ。
AIIBは設立まで1年半の時間しかかけていない。ちょうど、米連銀がQEを続けられなくなり、代わりに日欧にQEをやらせる動きをしていた時に、中国は、AIIBやBRICS開発銀行などIMF世銀体制の代替組織の設立を急いで準備していた。
日本は、ドルを延命させるため、日銀が新規発行の日本国債の全量を買い上げる過激なQEを続けている。いずれ日銀のQEは効果が下がる。日本国債の金利上昇とデフォルト、超円安などの混乱が起こり、日本は経済破綻する可能性が増している。すでに、日銀がQEを減らして軟着陸的に終了させるのは非常に困難だ。出口はない。日本は自分を人身御供にしてドルを救おうとしているが、日本が破綻した後、ドルも延命策が尽きて破綻しそうだ。具体的に何が起きるか予測が困難だが、大変なことになる。
このきたるべき大変な事態を予測して、中国などBRICSは、ドル崩壊の大惨事が起きても自分たちが溺死せずにすむ「ノアの方舟」的な、ドルに頼らない決済体制を準備している。その一つがAIIBだ。こうした通貨の面でも、日本は負け組で、中国が勝ち組だ。最近の日本では、中国を嫌悪・敵視・批判る言論が歓迎される半面、中国を客観的・肯定的にとらえて分析する言論は、誹謗中傷を受ける。中国の台頭や日本の衰退を食い止めるには、まず中国を冷静に分析することが必要だが、今の日本ではそれができない。日本人は、中国を嫌うばかりで、中国に負けないようにする方策を冷静に考えることを自分たちに禁じている。このままだと日本はますます中国に負ける。負けを自覚することも抑制されているので、負けがどんどん進む。
今の日本の嫌中的な風潮を煽っている勢力の背後に、米国のネオコンがいるかもしれない。ネオコンの雑誌の一つであるコメンタリーは最近、安倍の中国敵視策を「オバマの中国包囲策よりも良い」と賞賛し、安倍の軍事拡張やTPP加盟策を評価する記事を出した。米政権中枢に近い筋に評価されてうれしいと喜んでいると、いつの間にか自滅の道を進まされていることになるかもしれない。
関連記事
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
ソ連の北方四島占領作戦は、米国の援助のもとで実施されたという「発見」 『さらば!検索サイト』太田昌国著 現代書館
また私の頭の中で「歴史は新しく作られる」という例が増加した。表記のpp.77~79に記述されている
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の
-

-
Quora 古代日本語の発音
youtubeで、「百人一首を当時の発音で朗読」という動画を見ました。奈良・飛鳥時代の上代日本語
-

-
2022年8月ジャパンナウ観光情報協会原稿 アフターコロナという名の観光論 原稿資料
◎ジャパンナウ原稿案 2020年冬から始まった新型感染症は日本の人流・観光業界に
-
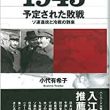
-
歴史認識と書評『1945 予定された敗戦: ソ連進攻と冷戦の到来』小代有希子
「ユーラシア太平洋戦争」の末期、日本では敗戦を見込んで、帝国崩壊後の世界情勢をめぐる様々な分析が行
-

-
Oneida Community Mansion House
https://www.bbc.com/reel/playlist/hidden-historie
-

-
書評『ペストの記憶』デフォー著
ロビンソン・クルーソーの作者ダニエル・デフォーは、17世紀のペストの流行に関し、ロンドン市長及び
-

-
ホテルアセッセトマネジメントとAirbnb 人の移動の自由・労働者の囲い込みと専門職大学の在り方
これも機能分化である。運送機能の分化を考えてきたが、宿泊機能も分化している。オーナーとオペレーターへ
-

-
歴史は後からの例「殖産興業」
武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社
