ウェストファリア神話
国際観光を論じる際に、文科省からしつこく、「国際」観光とは何かと問われたことを契機に、国際について考えざるを得なくなり、本書にたどり着いた。ここにも、「歴史は後から作られる」の実例がある。
「ウェストファリア条約 その実像と神話」
明石欽司著(慶應義塾大学出版会)書評
| 海道大学法学研究科教授(欧州大学院大学(伊)ブローデル上級研究員) 遠藤乾 |
| 「水平的主権国家体系」の始点をめぐる、スリリングな論考 600頁に及ぶ歴史書を通じて、4半世紀にわたる著者の知的な格闘を共有できるのは幸せである。この書物とともに、多くの実務家は自らの常識を疑い、研究者は講義内容を変更することになろう。 歴史や外交を少しでもかじった人ならば、ウェストファリア条約/体制ということばを耳にしたことがあるはずだ。それはたいていの教科書や歴史書で、1648年の同条約を起点とした主権国家体制(の成立)と同一視されてきた。 著者の明石が「ウェストファリア神話」と呼ぶ広く受容されたイメージによれば、30年戦争を終結させたこの条約を契機に、主権国家が水平的に並列し、教皇や皇帝のような国家上位の権威や価値がなくなった。こののち、国家ごとに宗教(および統治体制)を選び、それぞれの内政に不干渉とする原理が確立された、ということになる。 明石が、ラテン語を含む西洋語を駆使して条文に当たり、専門の国際法史を中心に神聖ローマ帝国国制史に手を広げ、膨大な文献の検討を通じて丹念に条文/通説/実態を選り分けることで、最終的に否定するのがこの神話である。 まず、ウェストファリア条約の名宛人は多様で不均質である。平等な国家が集まって決めたものではない。 次に、同条約は、それ以前から存在していた領邦主や都市の政治的・宗教的諸権利を現状追認した色彩が濃く、近代の主権国家間関係を新たに設定したのではない。 さらに、帝国国制について、同条約は本質的な改革を導入しなかった。つまり、17世紀半ばの段階で、領邦の主権国家化という現象はなかった。当時皇帝と帝国等族の紐帯はまだまだ生きており、帝国はじつに19世紀初頭まで残存するのである。 ではいったい、いつから、なぜ、国際関係の基本常識に関するこのような途方もない集団麻痺が起きたのか。 ここから明石は、ウェストファリア条約に関する言説の変遷を追跡することで、歴史的に理由を探し始める。 まず、締結当時「帝国の基本法」の色彩が濃かった同条約は、1713年のユトレヒト条約以降「欧州の基本法」という重要性を後付けで付加される傾向にあった。 また、同条約は、締結からなんと1世紀以上経た18世紀末になるまで、国際関係や国際法の文献において今日のように特殊な位置を占めるとは考えられなかった。 さらに、上記のような「神話」が急速に浸透するのは、19世紀中葉のことであった。1841年公刊のホィートン『欧州国際法史』が決定的な契機とされる。さかのぼれば、その素地を形作ったのは18世紀半ばのマブリーやコッホらによる実定法的な「条約史」の叙述であった。 こうした「神話」破壊は、じつは、オジィアンダーやテシィケ(『近代国家体系の形成――ウェストファリアの神話』と題する分厚い邦訳本もある)といった質の高い先行研究でもなされている。これらに対し、明石の研究は、帝国国制史に学んで神聖ローマ帝国や皇帝の意義を掘り下げ、「神話」形成史の解明に力点を置き、国際法史への含意を汲みとることで、一境地を開いている。 こうした研究に対し、ウェストファリアでないのならば、いつどこで水平的な主権国家の併存という事態が生じたのかという問いはありえよう。「神話」破壊とその形成史に焦点を合わせる本書はそれには直接には答えないが、そのかわり、現在優勢な観念を過去に投射し、それによって過去を捏造することに対し警笛を鳴らす。 およそ国際法であれ、国際政治であれ、主権をこの4世紀通用してきた不動の原理と捉え、国家間条約の重要性を無意識のうちに前提にしがちであるが、近代の「国際」法や「国際」政治は、もともと普遍的な枠の中で不均質な主体を包み込んできた歴史的連続性の下に長らくあったのだ。 歴史家としての矜持からか明石は多くを語らないが、これは最現代における地域や地球規模の現象を検討する際のカギを提供するという。また本書は、国家意思をどう制御するのかという課題を法実証主義の名の下で放逐してしまった国際法学の現況への鋭い批判を内包している。 ともあれ、有効な神話破壊は多くの思考の種を植えつける。長く読まれるべき古典として、多くの方に薦めたい。(外交フォーラム2009年10月号) |
関連記事
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
保護中: 7-1 先行研究1(高論文要約)
高論文 「観光の政治学」 戦前・戦後における日本人の「満州」観光 (満州引揚者)極楽⇒奈落 ホ
-

-
2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」聴講
2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」を聴講してきた。観光学も脳科学の
-

-
1932年12月16日『白木屋の大火始末記』
関東大震災の始末が終了したころ 地下三階地上七階建てデパートの4階から出火 クリスマスツリーの豆電
-

-
大関真之『「量子」の仕業ですか?』
pp101-102 「仮にこの性質を利用して、脳が人の意識や判断、その他の動作を行っているとしたら、
-

-
運輸省(航空局監理部長)VS東亜国内航空(田中勇)のエピソード等
https://www.youtube.com/watch?v=flZz_Li7om8
-

-
QUORAにみる歴史認識 第二次世界大戦時、なぜ戦況は悪化したのに、(日本は)戦争は辞められなかったのですか?
第二次世界大戦時、なぜ戦況は悪化したのに、戦争は辞められなかったのですか? 日本では、開戦時
-
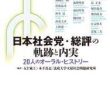
-
日本社会党・総評の軌跡と内実 (20人のオーラル・ヒストリー) 単行本 – 2019/4/8 五十嵐 仁 (著), 木下 真志 (著), 法政大学大原社会問題研究所 (著)
港区図書館の蔵書にあり、閲覧。国鉄再建に関し、「公共企業体(国鉄)職員にスト権を与えるか否か」の政府
-

-
動画で考える人流観光学 西洋人慰安婦に関する映画
She Ends Up In A Japanese Concentration Camp For



