書評 三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』日本の近代化にとって天皇制とは何であったか
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
歴史認識
日本の近代とは明確な意図と計画をもって行われた前例のない歴史形成の結果
前近代の日本にはこれに対比しうる顕著な歴史形成の目的意識性を見出すことは難しい
しかしそのことが歴史的独創性を意味するものではない 欧州の経過資本主義を受け入れることを前提として形成
目標は自明 方法が不明 日本自身が機能の体系として再組織化 機能主義的思考様式の重要性を強調 福沢諭吉、田口卯吉、長谷川如是閑、田中王道、笠信太郎
しかし欧州が機能の体系としてとらえられえるものではない。そのことが分かっていた永井荷風
キリスト教の機能的等価物としての天皇制 聖と俗の二元の欧州
詔勅批判は自由か? 大日本帝国憲法下で副署のない例外的な詔勅があった。
それが教育勅語 詔勅批判の自由を主張する美濃部を検事は追及
井上毅 勅語の宗教性と道徳性の徹底した希薄化 政治的状況判断の混入の排除
道徳の根源が皇祖皇宗の遺訓 日常化した儒教的徳目
国務大臣の副署のない、立憲君主制の原則によって拘束されない絶対的規範として定着 宮中にいて文部大臣に下付する方法をとる
日本の近代においては、教育勅語は多数者の論理、憲法は少数者の論理 不安定化を促進
関連記事
-

-
QUORAにみる歴史認識 英国はなぜ世界の覇者になれたんでしょうか?
英国はなぜ世界の覇者になれたんでしょうか? この話を解く鍵は実はイギリスにはないと
-

-
Quoraにみる歴史認識 高2です。東京書籍の教科書には、朝鮮総督府が言論などの自由を奪い、武断政治をした。所有者の明確でない土地を没収し多くの農民が困窮したとあります。これを戦前の日本に肯定的な人はどう捉えるのでしょうか。?
私は別に「戦前の日本に肯定的な人」ではないのですが、東京書籍の教科書がそれしか書いていないのだと
-
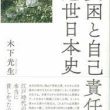
-
『貧困と自己責任の中世日本史』木下光夫著 なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追及する社会となってしまったのか。それを、近世日本の村社会を基点として、歴史的に考察
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか 奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村
-

-
🌍🎒モンゴル観光調査の準備~社会主義が生み出した民族の英雄~
8月17日から2週間、地球環境基金の仕事でモンゴルの観光、環境調査に参加する。予備知識を得るため参考
-
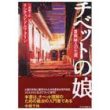
-
『チベットの娘』リンチェン・ドルマ・タリン著三浦順子訳
河口慧海のチベット旅行記だけではなく、やはりチベット人の書物も読まないとバランスが取れないと思い、標
-
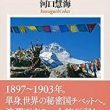
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか
-

-
Quora 日本が西洋諸国の植民地にならなかったのは何故だと思いますか?
https://jp.quora.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%
-
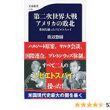
-
渡辺惣樹著『第二次世界大戦 アメリカの敗北』
対独戦争をあくまで回避するべきと主張したチェンバレンら英国保守層 対独戦争は膨大な国力を消費し、アメ
-

-
戦後70年の価値観が揺らいでいる」歴史家の加藤陽子氏、太平洋戦争からTPPとトランプ現象を紐解く 真珠湾攻撃から75年、歴史家・加藤陽子氏は語る「太平洋戦争を回避する選択肢はたくさんあった」 三国同盟の見方 歴史は後から作られる例
/https://www.huffingtonpost.jp/2016/12/0


