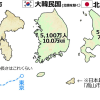歴史認識と書評『海軍と日本』 池田清著 中公新書
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
未分類
書評1 ○ 著者は海軍兵学校(73期)卒業、終戦時海軍中尉で潜水艦に乗務し、戦後は東京大学法学部に学び東北大学法学部教授になった経歴を持つ。
○ 太平洋戦争の主役は海軍であり、アメリカ、イギリス海軍より日本海軍は明らかに劣勢であった、にも関わらず、海軍は陸軍の暴走をを阻止できなかった。
○ 山本五十六大将は日米戦において日本海軍の限度は2,3年であると述べている。
○ 日独伊三国同盟に猛反対した米内光政、山本五十六、井上成美など少数の理性派も居たのにも関わらず開戦派に押し切られ、世界海戦史上例を見ない惨敗を喫した。
○ 1941年、イギリスは極東における最大拠点シンガポールを防衛するため戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と巡洋戦艦「レパルス」を基幹とする東洋艦隊を配備した。日本海軍航空隊はイギリス東洋艦隊戦艦2隻(プリンス・オブ・ウェールズ、レパルス)を撃沈し、この方面での初期作戦上で大成功をおさめた。 また、当時の「作戦行動中の新式戦艦を航空機で沈めることはできないとの常識を覆した。当時の世界の海軍戦略である大艦巨砲主義の終焉を告げる出来事として海軍史上に刻まれている。
しかし日本海軍は旧態依然、巨艦巨砲主義から抜ける事ができなかった。
○ 著者は海軍壊滅の原因を1969年から延べ70人もの関係者の面接による事情聴取を行った。
それをもとに、海軍と戦争・海軍と政治・海軍の体質の三章から検証を行った。
書評2 実は、わたしは守旧の陸軍、開明の海軍という図式を何となく抱いていたのだ。
しかし実際は、日本海海戦の勝利の故に艦隊決戦ばかりを指向する海軍もまた、陸軍と同様、新時代の戦法に対応できなかった。
マレー沖海戦の教訓を生かしたのは、勝者である日本ではなかったのだ。
ハンモックナンバーによる人事面の膠着、人材の育成方法の失敗など筆者の断罪は、兵学校出身者だからこそ、より辛らつだ。
内部にいた人間だからこその筆の走りもあろうが、当時の提督や当事者への聞き取りは、今となっては非常に貴重な資料だと言えよう。
それが初版後四半世紀を経てなお、新刊として入手可能にしている所以であろう。
特に「はじめに」は、著者の思いが吐露されており、有志諸氏にはご一読願いたい一文だ。
書評3 書店の店頭で本書を見かけたら、是非「はじめに」をゆっくり読み通してみてください。全編の基本線がみごとに凝縮された文章です。
興味をそそられたら、33ページと41ページの前後数ページを「高度の平凡性」をキーワードにして読んでください。著者は、これが当時の海軍の最高幹部から中堅士官達にまで一貫して欠如していたことを指摘します。
そして、なぜ組織的にそうした構造・体質になってしまったかについては、全編を通じて丹念な分析がなされます。海軍の衰滅についての、特に人事・教育面に深くメスを入れた文章は、具体的で説得力があります。
著者は海軍兵学校を卒業し20歳の海軍中尉として終戦を迎えた方です。部外者ではなく、かといって内部中枢でもなかった。この立場視点から、なぜ貧しかった日本が歯を食いしばって国力を注ぎ込んで築き上げた海軍が、勝つ見込みのない戦争に突入していったか、また痛恨事の連続といってよいほどの過誤を重ねた戦いをしたのか、通説が与える説明へのわだかまりに自問し自答した結果が本書とのことです。
関連記事
-

-
シニアバックパッカーの旅 ジャパンナウ原稿 人流大国・中国
LCCの深夜便を利用して、1泊3日の南京(850万人)、蘇州(1060万人)、杭州(920万人
-
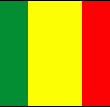
-
🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 マリ共和国(国連加盟国181か国目)BKOからダカールへ
https://photos.google.com/album/AF1QipMC
-

-
🌍🎒2023夏 シニアバックパッカーの旅 2023年9月3日 国連加盟国170か国目アルジェリア ティパサ(世界遺産) シェルシェル
Facebook投稿文 2023.9.2 国連加盟国170ヶ国目アルジェリア 2時間
-
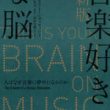
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 視覚 知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避、色盲メガネ
◎松井冬子 博士論文「知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避」 生まれ
-

-
🗾🎒 🚖シニアバックパッカーの旅 2016年8月1~3日 弘前・青森 チームネクスト
チームネクストの研修会が弘前で開催。この機会に現地の北星交通社長の下山さんのお世話で弘前のねぷたと青
-

-
Participation in press tour for Jeju (preliminary knowledge)
The international tourism situation of Jeju is cha
-

-
動画で考える人流観光論 観光資源論 贋作の観光資源的価値
第51回国会 参議院 文教委員会 第4号 昭和41年2月17日 https://kokkai.nd
-

-
明治維新の見直し材料 岩下哲典著『病と向きあう江戸時代』第9章 医師シーボルトが見た幕末日本「これが日本人である」
太平の世とされる江戸時代に自爆攻撃をする「捨足軽」長崎奉行配下 福岡黒田家に「焔硝を小樽に詰めて肌身