「中国のシェアリングエコノミーを見誤るな~「マッチング先進国」の競争力とは」のメモ書き
https://wisdom.nec.com/ja/business/2018032202/index.html?cid=wis_np252
王永(Wang Yong、以下敬称略)という中国人の名前を知る日本人は少ないだろう。中国で自家用車によるライドシェアを初めて広く社会に知らしめたことで記憶されている人物である。
彼は朝晩のライドシェアを実践し始める。後に「順風車」という呼称で世の中に広まり、一種の社会現象になった行動の端緒である。
2012年の春節(旧正月)には、中国中央テレビの人気司会者と王永らを含む7人が呼びかけ人となり、「順風車で故郷に帰ろう」というキャンペーンがスタート。この年は600人の自家用車オーナーが車の座席を無料で提供、約1000人が相乗りで帰郷した。このイベントは年々拡大、翌13年には1万人、14年には2万5000人が利用した。ライドシェアという共有経済の概念は広く社会に知られるところとなった。
ところが「順風車」は拡大と同時に、その限界も見えてきた。安全性や法律的な課題もあったが、最大の問題は車(座席)の供給が追いつかないことだった。「順風車」は一種の社会運動で、無償の善意が前提である。ガソリン代の均等割り程度の負担はあったが、基本はあくまで個人の好意で、活用されずに遊んでいる社会資源の有効活用に主眼があった。
もちろんこれは有意義な話なのだが、規模が大きくなると善意だけでは供給が足りない。
現在、中国の配車サービスで圧倒的なシェアを占める滴滴出行(DiDi)などの企業は、まさにこのタイミングで誕生した。DiDiがシェアライドの事業を始めたのが2014年、有償の「順風車」をスタートしたのが翌15年である。「順風車で故郷に帰ろう」キャンペーンが始まって4年目のことだった。ここから中国のシェアエコノミーは大きく姿を転換していく。
DiDiは当初こそ、普通の市民が自分の車を使って副業として収入を得る、米国のUberの中国版的ビジネスを展開していた。しかしその後、運転手は徐々に専業化し、車両も会社が提供するケースが増え、シェアリングエコノミー的色彩は徐々に薄れていく。要は「遊休資産の活用」ではニーズに応え切れなかったのである。
そして2016年7月、中国政府はライドシェア企業の経営条件を定める「インターネット手配タクシー管理サービス暫定法」を施行。この法律の登場で、個人の車を活用したUber的なライドシェアの営業には正式な許可が必要になり、運転者には厳格な資格要件が定められた。有償の「順風車」も同様である。これが決定打となって、自分の車を使って収入を得るタイプのライドシェアは中国の大都市では事実上、できなくなった。
王永たちの始めた無償の「順風車」は現在もある。しかし大きな広がりにはなっていない。実を言えば、ここで詳細は触れないが、王永自身もかつて投資家や政府系の資金を得てみずから事業化を試み、失敗している。その後、ライドシェアのコンセプトを本格的なビジネスとして成功させたのがDiDiなどのIT企業だった。
都市部では自転車を所有する必要はなくなり、スポーツ用など一部の特殊なスペックのモデルを除き、自転車の販売量は大きく下がった。マイカーやタクシーの近距離利用も減り、渋滞も減少したという。マッチングの高度化が人々の行動を変えたのである。
その後、街に放置される自転車が増えすぎ、無断で投機、廃棄される自転車が山積みとなり、社会問題化した。「共有経済をうたっているのに、何という資源の無駄か」と中国国内でも大きな批判が起きた。そういう事態が起きたのも、サービス提供者がマッチングの精度を極限まで高めようとすれば、街に置く自転車の数を増やすのが最も有効な手段だったからだ。
その結果として中国の大都市には、アプリ一つで、いつでも、どこでも好みのタイプの車が迎えに来るタクシー配車の仕組み、どこからでも乗れて、どこでも乗り捨てられる自転車、何百種類ものメニューから選んだ料理があっと言う間に自宅に届くデリバリー、マンションの敷地内にあって24時間、必要なものが揃う無人コンビニなど、「いつでも、どこでも、欲しい商品やサービスが手に入る」状況が次々と出現した。これらはすべてマッチングの精度を極限まで突き詰める姿勢から生まれてきたものである。
中国の個人信用情報評価システムの整備【「信用」が中国人を変える、スマホ時代の中国版信用情報システムの「凄み」】https://wisdom.nec.com/ja/business/2017041101/03.htmlなどに見られるように、ビッグデータの蓄積と活用では中国社会は(その是非はともかく)日本を含む先進諸国より圧倒的に有利な条件を備えている。さまざまな個人の嗜好に応えられる商品やサービスを「いつでも、どこでも、欲しいものが欲しい時に」提供できる体制をつくる。中国が強い競争力を持つのは、実はこの点においてである。
関連記事
-

-
🌍🎒 🚖シニアバックパッカーの旅 世界人流観光施策風土記 2017年9月 フィリピンはマニラの観光・交通事情 承前
フィリピンの首都マニラに9月11日から15日まで、チームネクストの調査に参加する。 フィリピンは今
-
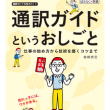
-
沖縄の中国人レンタカー報道
日本政府観光局(JNTO)が2016年6月20日に公表した訪日外国人のレンタカー利用状況に関する資料
-

-
🌍🎒 🚖 マニラのライドシェア状況報告 チームネクスト IN 新潟 11月1日
新潟でのチームネクストに参加し、マニラの報告を行った。 三条市のデマンド交通の説明を市長と中越交通
-

-
メディアやセミナーに踊らされるMaaS
Mobility as a Service(MaaS)とは、運営主体を問わず、情報通信技術を活用
-

-
タクシージャパンのライドシェアに関する記事(労組関係)
タクシージャパンで、戸崎肇氏及び国際運輸労連ロンドン本部内陸運輸部長浦田氏の講演内容の紹介記事を読ん
-

-
東京交通新聞1月11日インタヴュー記事(定額運賃制タクシー)
寺前教授インタビュー 3機能に分化する運送業 ――現在、タクシー事業は外資の白ナンバー自家
-

-
侮辱されたUber運転手の報道と欧州での訴訟報道
CNNは、NYPD警官がアメリカに来て2年のUber運転手を侮辱しているニュースを流しています。NY
-

-
歴史は繰り返す 悪質(?)ランドオペレーター対策 米人保護→日本人保護→中国人保護
戦後まで一貫して観光政策はインバウンドであった。外貨獲得が目的である。国際観光ホテル整備法、通訳案内
-

-
自家用自動車の共同使用(ライドシェ)
タクシー業界がライドシェに過敏になっているのか、行政当局もライドシェに否定的な報道が目立つ。しかし、
-

-
「ボランティアドライバー」 グローバリゼーションをダラスから考える 公研 2019年4月
ハンツヴィル 米国製造業の雇用がこの30年間で減少してきた原因は、グローバ
