「地消地産」も「アメリカファースト」も同じ
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
観光資源
『地元経済を創りなおす』枝廣淳子著 岩波新書を読んだ。ちょうど教科書原稿を書いているときだったので参考になった。
外国人観光客が増加しても地域住民所得が増加していないことを論文にまとめている。標記の書物は大変参考になった。
「漏れバケツ」理論 https://www.japanfs.org/ja/files/wbg_131205_02.pdf を紹介してる。地域内乗数効果の説明であり、専門家には常識的なことであるが、ネーミングからしてこのほうが学生にはわかりやすいであろう。
日本中の地域の最大の「バケツの漏れ」はエネルギー料金というのも言われてみると当然。唯一の例外は屋久島で、屋久島電工が提供する水力発電で供給されているからだ。
英国トットネス地方(人口12000人)の成功例を紹介ている。「コーヒー戦争に勝つ」と題して、全国チェーンのコーヒーショップの進出を阻止した話を紹介。地元の42軒のカフェを利用する運動を起こしたということである。地元でお金が回り続ける運動として紹介している。
学校給食 地産地消ではなく「地消地産」を提唱している。学校給食では地元産品を使えということである。しかし、流通革命前全国に存在した地酒、地醤油は全国ブランドに席巻された。ボリュームディスカウントを禁止ない限り当然の流れである。市場メカニズムを活用しないで地産地消を唱えていても効果は薄いから、政策的に行うことになるが、無理に行えばアメリカファースト政策と同じである。制度的に行っていたのが、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)に基づき地元商工会議所等が行っていた商業活動調整協議会である(商調協)。当然のことながら消費者からの反発は大きかった。
「創造的過疎」という言葉も称されている。人口減少は受け入れるということである。しかしどこか言葉遊びの感じが否めめなかったのも、やはり、トランプ大統領が言っている「アメリアファースト」を地域的に主張しているだけのような気がしたからである。勿論地元民が満足してい実行しているならそれで構わないわけで、米国民がアメリカファーストに満足していればそれで構わないのであるが、それでは世界経済の成長はストップしてしまうであろう。合成の誤謬というやつであろうか。狭い範囲では好意的に受け止めるメンタリティがあるが、米国大統領が言うとインテリは反発するするのである。
地域経済循環図 RESAS https://resas.go.jp/#/13/13101
https://resas.go.jp/regioncycle/#/map/13/13100/1/2013
バケツ漏れの例として離島が数多く出てくるが、沖縄の数字を見ると、南大東島(人口1339人)は所得高い。ハワイ並である。公務員給与が高いわけではない。ラスパイラス指数は100を割り、90である。最低賃金も737円と全国最下位レベルである。基幹産業は大規模なサトウキビ栽培であり、手厚い農業補助があるのかもしれない。 人口は1970年 2275人から減少している。
一人当たり市町村民所得(2013年度)
南大東町 4632
北大東町 3373
嘉手納町 2880
与那国町 2582
恩納村 2431
那覇市 2430
浦添市 2317
竹富町 2238
石垣市 2143
県全体 2102
宜野湾市 2037
宮古島市 1969
名護市 1943
沖縄市 1938
糸満市 1848
うるま市 1679
大宜味村 1609
今帰仁村 1421
沖縄県企画部統計課「平成25年度 沖縄県市町村民所得」
http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170602005/20170602005-25.pdf
関連記事
-

-
観光資源の評価に係る例 米国の有名美術館に偏り、収蔵作品は「白人男性」に集中
https://www.technologyreview.jp/s/117648/more-th
-

-
『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話 ムハンマドの活
-

-
ウッドストック50周年中止 歴史は後から作られる
newspicks のコメントが面白い。Wikiの解説とは一味違う。これも歴史は後から作られる例か
-
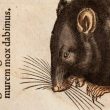
-
ペストの流行 歴史は後から作られる例
BBCを聴く。中世の黒死病、ペストの流行はネズミによるものだと、学校で教えられたはずだが、残存するデ
-

-
『公研』 2018年2月号 「日本人は憲法をどう見てきたか?」
歴史は後から作られるの例である。 境家史郎氏と前田健太郎氏の対談 日本国民が最初から憲法九条
-

-
観光資源としての吉田松陰の作られ方、横浜市立大学後期試験問題回答の例
今年も一題は、歴史は後から作られ、伝統は新しい例を取り上げ、観光資源として活用されているものを提示
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 動画で見る世界人流観光施策風土記 モンゴル紀行 メモ書き シャーマン動画 トナカイ解体動画
ツァータン族の居住地の4泊分は、通訳代、移動費を別にして、180万ツグルであった。 ツァーマン
-
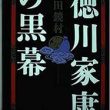
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-

-
ハイフンツーリズム批判と『「日本の伝統」の正体』藤井青銅著
観光研究者が安易に○○ツーリズムを提唱していることへの批判から、これまで伝統や歴史は後から作れると述

