書評『ペストの記憶』デフォー著
ロビンソン・クルーソーの作者ダニエル・デフォーは、17世紀のペストの流行に関し、ロンドン市長及び区長によって制定・公布される条例・1665年、患者の出た家屋とペスト患者に関する条例、街路を清掃し快適に保つための条例、節度のない者たちと無駄な集会に関する条例を紹介するとともに、ペスト流行時には、患者が一人でも発生した家では、住民全員がそのまま40日間家屋に閉鎖され、一歩も外に出られないことを紹介している(『ペストの記憶』)。同書の訳者である武田将明は訳者解題で「現代日本に住む人々にとって、本書が三百年前のイギリスで書かれたことは、にわかに信じられないのではないか。行政府が毎週公表する死者の数に一喜一憂し、さらにはその数値を疑う市民たち。突然大量に現れた自称専門家たちの説く、真偽の定かでない対策。さっさと被災地を後にする人と、あえてそこに留まる人。さらには、避難者を忌避する自治体や、後日被災地に戻った避難者を排除する残留者。風評による経済被害。これらは、2011年3月11日に発生した地震と津波、そして原発事故のあと、私たちが見てきた後掲の一部と重なる」「1722年という、まだ世界が近代に入り始めたばかりの時期、アメリカ独立もフランス革命も経験していなかった時代に、すでに市民が市民を管理するという自律的な権力の抱える問題点を理解し、ペストという壊滅的な危機を媒介にして、その光と闇を描き切った点にこそ、本書の普遍的な価値がある」と解説するとともに、ペスト・ツアーとして「頑張れば一日でほぼすべてを見てまわれる」ロングエイカーとドルリー小路の交差点、クリップルゲートのセントジャイルズ教会(デフォーの胸像もある)、バンフィル・フィールズ(ペスト療養所があったところ)等を紹介している。
書評1 2020年に入ってCOVID19が拡がり、世界は一変してしまった。本書やカミュの『ペスト』が広く読まれるようになったという。H.F.という筆者(デフォーにロンドンペストのことを語ってくれた叔父がモデルではないかと言われているらしい)の著述の形をとっており、デフォー自体は1665年に5歳であったとのことなので、直接体験したことではない。あくまで作品だが、当時の様子を色濃く映している。
ロンドンの東部から西部に向かってペストが拡がっていく様子、郊外へ逃げるか留まるかの選択、貧困層が都市を脱出した後に「ペスト」かもしれないからと迫害される様子、ペスト最盛期を超えたときに早々と警戒を解いて感染し死亡したことなど、生々しく描かれている。都市機能が保たれたのは、市が、ペスト最盛期であっても資金を投入してパンを絶やさなかったこと、死体を放置しなかったこと(多くは夜間、デッド・カートに乗せて巨大な穴に埋葬されたという)であったという。ペスト感染者が一人でも出たらその家は封鎖され、監視人が置かれたこと、必死で逃げ出そうとする人が多かったこと、殺された監視人もいたこと・・・といった「住宅封鎖」。無症候者が出歩いたことで結果として感染を広げてしまったことなど、COVID19が拡大している現在と通ずる叙述もある。
訳者である武田将明氏は「生権力の露呈」として、「本書の醍醐味は、ペストという圧倒的な暴力を囲いこみ、封じ込めようと努める市の行政府が、市民を保護する側面と抑圧する側面を合わせ持つという、秩序の両義性にこそ認められる。市民の自由を制御せずに、ペストを管理することはできないのだ」と述べる。都市機能、あるいは文明社会の機能維持の暗部を描写していると思う。
本書はペストに遭遇した都市を題材に、危機に瀕した人間の行動、それを処置する行政の姿を生々しく描写したたぐいまれな傑作と思う。
関連記事
-
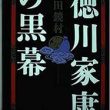
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-

-
「今後の観光政策学の方向」 人流・観光研究所所長 観光学博士 寺前秀一
① 旅が大衆化すると「Tourist」概念が生まれるのだとすると、日本における「
-
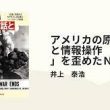
-
アメリカの原爆神話と情報操作 「広島」を歪めたNYタイムズ記者とハーヴァード学長 (朝日選書) とその書評
広島・長崎に投下された原爆について、いまなお多数のアメリカ国民が5つの神話・・・========
-

-
ゆっくり解説】突然変異5選:新遺伝子はどうやって生まれるのか?【 進化 / 遺伝 子 / 科学 】
https://youtu.be/bGthe_Aw1gQ ミトコンドリアと真核生物の起源:生物進化
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-

-
『1964 東京ブラックホール』貴志謙介
前回の東京五輪の世相を描いた本書を港区図書館で借りて読む。今回のコロナと五輪の関係が薄らぼんやりと
-

-
ネット右翼を構成する者 メディアが報じるような「若者の保守化」現象は見られない
樋口直人は『日本型排外主義』の中で、大部分は正規雇用の大卒ホワイトカラーであるとし、古谷経衡も「ネ
-

-
植田信太郎 脳の「大進化」(種としての進化)、「小進化」(集団としての進化)
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/rigakuru/03
-

-
中国「デジタル・イノベーション」の実力 公研2019No.665
モバイル決済は「先松後厳」まずは緩く、後で厳しく 日本の逆 AirbnbやUberが日本で
-
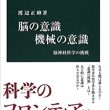
-
『脳の意識 機械の意識』渡辺正峰著 人間は右脳と左脳の2つを持ち,その一方のみでも意識をもつことは確かなので,意識を持っていることが確実である自分自身の一方の脳を機械で作った脳に置き換えて,両脳がある場合と同じように統一された意識が再生されれば,機械は意識を持ちうると結論できる.
Amazon 物質と電気的・化学的反応の集合体にすぎない脳から、なぜ意識は生まれるのか―。多くの
- PREV
- 歴史認識と書評『海軍と日本』 池田清著 中公新書
- NEXT
- 書評『ロボットと生きる社会』

