書評『ロボットと生きる社会』
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
脳科学と観光
新井紀子 AIが下す判断と人間が下す判断は違う AIは基本は検索。人間は実験ができないので科学的に判断できない。今はサルでも実験禁止
地球温暖化もいつまでたっても解決できない 脳の容量が限界
四色問題、ケプラー問題 人間に解けないで機会が解ける問題はある。
ロボットスーツ 脳を計測するのではなく、単なる筋電のデータを意思だと思ってロボットスーツが動作している
近代法において人間の「意思」がどこから出ているものに定義されているのかよくわからない
川口大司 甲板員の時代からある機会に仕事を奪われること
平田オリザ 無駄な動きマイクロスリップ 練習すればするほどリアルから遠ざかる 石黒浩先生はどうすればロボットにマイクロスリップの動きをさせられるか研究
認知心理学の佐々木正人 認知心理で解析できる匠の技はせいぜい1%
舞台俳優 昨日と今日で間の取り方が0.2違うとわかる
関連記事
-
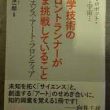
-
冒険遺伝子(移動しようとする遺伝子) 『科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること』川口淳一郎監修
P.192 高井研 ドーパミンD4受容体7Rという遺伝子 一時期「冒険遺伝子」として注目された
-

-
脳科学 ファントムペイン
四肢の切断した部分に痛みを感じる、いわゆる幻肢痛(ファントムペイン)は、脳から送った信号に失った
-

-
書評 AIの進化が新たな局面を迎えた:GTP-3の衝撃
米国コロナ最前線と合衆国の本質(10)~AIの劇的な進展と政治利用の恐怖~ https://
-

-
サムスン、ヒトの「脳をコピペ」できる半導体チップの研究を発表
https://japanese.engadget.com/samsung-plans-to-c
-

-
『意識はいつ生まれるのか』(ルチェッロ・マッスィミーニ ジュリオ・トノーニ著花本知子訳)を読んで再び観光を考える際のメモ書き
観光・人流とは人を移動させる力であると考える仮説を立てている立場から、『識はいつ生まれるのか』(ルチ
-

-
意識あるロボットの出現とホスピタリティー論の終焉
かねがね、観光学研究で字句「ホスピタリティー」が使用されていることに大きな疑問を感じていた。意識
-

-
保護中: 池谷裕二氏の一連の「脳と心」にかんする著作を読んだメモ
外の世界は「目」を通して第1視覚野に写し取られ、そのあと、色に反応する第4視覚野や動きを見る第5視覚
-

-
『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハー
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 視覚 知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避、色盲メガネ
◎松井冬子 博士論文「知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避」 生まれ
-
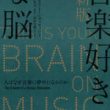
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
- PREV
- 書評『ペストの記憶』デフォー著
- NEXT
- 書評『人口の中国史』上田信

