『意識はいつ生まれるのか』(ルチェッロ・マッスィミーニ ジュリオ・トノーニ著花本知子訳)を読んで再び観光を考える際のメモ書き
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
脳科学と観光
観光・人流とは人を移動させる力であると考える仮説を立てている立場から、『識はいつ生まれるのか』(ルチェッロ・マッスィミーニ ジュリオ・トノーニ著花本知子訳)に興味を持ち読んでみた。脳科学の研究者間の競争は熾烈であり、研究対象としてとりのこされた脳の部位はないに等しいようである。先日も錯覚研究会に参加し、ますますその感を強くした。
本書では、意識を生み出す脳と、意識を生み出さないコンピュータの違いはどこにあるか、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介している。統合情報理論とは「脳などのシステムが処理する情報の豊富さと統合性によって、意識の発生を説明しようとする」理論である。つまり「意識を生み出す基盤は、おびただしい数の異なる情報を区別できる、統合された存在である。つまり、ある身体システムが情報を統合できるなら、そのシステムには意識がある」というのが、統合情報理論である。なお、錯覚研究会の資料によれば錯覚が発生するメカニズムは数式化されている。
我々は眠りに落ちると意識を失い、夢をみているとき(とくにレム睡眠時)には独特の意識的な経験をする。統合情報理論は、この意識を説明するのに、実用面でどこに説得力があるのであろうか。脳幹に傷を負い植物状態に見えるロックトイン症候群患者(映画「潜水服は蝶の夢を見るか」の主人公https://youtu.be/7olM7fRxEU4)の意識の有無の診断や、麻酔薬を投与する意識が失われる理由、右脳と左脳をつなぐ脳梁を切断する(スプリットブレイン)と、1つの脳のなかに意識が2つ生まれる理由を説明する場合に、本書はこの統合情報理論を持ち出している。
統合情報理論からすると、意識の発生条件を満たすのは、当然小脳ではなく視床−皮質系である。我々の脳の視床−皮質系のニューロンの数は200億であるのに対して、小脳のニューロンは800億もある。しかし、意識発生の鍵を握る部位は視床−皮質系であって、小脳ではない。
外界とのコミュニケーションが取れない植物状態の脳も、意識がある場合があるのではないかとの疑問から行った実験。 その一つは、fMRIを使って、健康な被験者と脳に損傷を負って全く意識がないと診断された患者を使って、テニスをしているところを想像させるよう話しかけたところ全く同じ大脳の特定の部分に反応が現れたという。同様に、著者たちが開発したTMS脳波計を使って脳に刺激を与えて現れる波形を調べると、脳に損傷を負って植物状態とされた患者にも正常な波形が現れる時があるという。著者が開発した意識の測定装置(一定の刺激を与え、その反応を測定する機械)を使った実験によれば、覚醒している時と寝ている時では、脳への刺激を与えた時の反応が全く異なる。ここで、意識がある状態とない状態がほぼ特定される。
〇 動物には意識があると言えるのか、コンピュータによってニューロンネットワークを再現して意識が生まれるのか?
脳に意識が生まれるには、外界との刺激が必要になり、脳内で因果関係を捕らえるための反応がシナプスのつながりによって徐々に複雑な出来事をとらえられるようになっていく。いずれにしても、意識が生まれるためには、非常に微妙なバランスが必要である。
〇vivekatrek氏の書評がアマゾンにでていたので以下紹介する。
「今から20年前、私が45歳の時、私が管理する中央研究所のIBMスパコンに400×500個の視覚細胞からなる視覚認識ユニットをプログラムした。視覚細胞は非線形振動子(ノーベル賞を受賞したホジキン・ハクスレイ偏微分方程式を近似した東北大学の矢野雅文教授の線形高次方程式を使用)でモデル化し、視覚細胞の相互作用を可能にするニューラルネットで大脳視覚野をモデル化して画像のパターン認識を計算したことがある。パターン認識は、トポロジーを拡張した記憶画像の一般化で柔軟な画像認識を可能にしたものである。一ヶ月間占有で計算した結果、万有引力のような遠隔作用を仮定しなければ画像認識が出来ないという結論が導かれた。つまり、隣り合う神経細胞に情報が伝搬する時間と遠く離れた神経細胞に情報が伝搬する時間に差があってはいけないという結果だったのである。これは視覚細胞の相互作用は隣接する視覚細胞だけでなく遠く離れた視覚細胞との相互作用も導入する必要があるということになる。」
「色の識別に関する心理学の実験で同様な事例(脳内の時計は過去と未来が逆転するかに見えるという実験結果)があることを知り、あの計算機実験の結論は正しかったのだと得心したのである。大脳は時間差の調整を意識に昇らせずに巧妙に行っているのである。だから、人間はそうした処理に時間がかかっていることに気づかない。本書p.172で「なぜ意識は発生するまでに時間がかかるのか?(それは)視床-皮質系の内部で、情報が高いレベルで統合されるためには時間がかかるのだ」と述べているが、具体的には上記したような作業を行っているのである。」
「p.123で意識の単位として、身体的システムの情報量を定めるΦ(ファイ)が提案される。Φは「多様な相互作用」と「統合」を評価することができる(p.137)。人間で、約800億個の神経細胞からなる「小脳」と約200億個の神経細胞からなる「視床-皮質系」を比較すると、「小脳」は独立した多数のルーチン・モジュールからなるのでΦは小さいが、「視床-皮質系」は相互作用系が生み出す無数の選択肢から必要な統合を行うのでΦは大きい。しかし、実際の脳活動におけるΦを測定する巧妙な実験を行うと、予想通りの結果が得られていない。」
「上記した私の実験で非線形振動子に仮定した『オープンな系』が「多様な相互作用」を生み、トポロジカルな認識過程の『エントロピー減少メカニズム』が「統合」を生む。「視床-皮質系」の脳波パターンが多様な相互作用や統合過程に対応する訳ではないので、1個の神経細胞の脳波が測定できるようにならなければ、意識のプロセスを解明するのは難しいと思われる。」
vivekatrek氏の説の極めつけは意識一元論の可能性を否定しないことである。
「本書も「視床-皮質系」という物質が『意識』を生むと考える「物質一元論」を前提とする。しかし、『意識』が「視床-皮質系」という物質を生んだと考える「意識一元論」も可能である。「物質一元論」の立場では、『意識』が生まれたのは偶然だと考えるから、『意識』を生む必然的な設計指針が無い。しかし「意識一元論」の立場では、『意識』を生命体に与えるための必然的な設計指針が得られる。その証拠は実際の生物の脳が余りにも似ていることである。魚類、両生類、爬虫類では、脳幹が脳の大部分を占める。小脳は、小さな膨らみにすぎない。大脳も小さく、魚類と両生類では、生きていくために必要な本能や感情を司る「大脳辺縁系」のみである。大脳辺縁系は、進化的に古いことから「古皮質」と呼ばれる。爬虫類では「新皮質」がわずかに出現する。鳥類や哺乳類になると、小脳と大脳が大きくなる。特に大脳の新皮質が発達し、「感覚野」「運動野」といった新しい機能を持つようになる。霊長類では新皮質がさらに発達して大きくなり、「連合野」が出現し、より高度な認知や行動ができるようになった。こうした事実を見る限り、『意識』を肉体次元で実現するための設計指針が皮質系であると考えざるを得ない。」
ロジャーペンローズ等の説明では「脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる素粒子より小さい物質であり、重力・空間・時間にとわれない性質を持つため、通常は脳に納まっている」が「体験者の心臓が止まると、意識は脳から出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇生しなければ意識情報は宇宙に在り続ける」あるいは「別の生命体と結び付いて生まれ変わるのかもしれない。」とされるから意識一元論である。
〇 最後の感想、「死は恐る必要なし。死を体感出来る意識が無くなるから」に奇妙に納得させられた。
関連記事
-

-
gコンテンツ協議会「ウェアラブル観光委員会」最終会議 3月4日
言い出したはいいが、どうなることやらと思って始めた会議であったが、とりあえず「終わりよければすべてよ
-

-
観光学研究の将来 音譜、味譜、匂譜、触譜、観譜
ベートベンの作曲した交響曲が現在でも再現できるのは音譜があるからである。これと同じように、ポール
-

-
書評『法とフィクション』来栖三郎 東大出版会
観光の定義においても、自由意思を前提とするが、法律、特に刑法では自由意思が大前提。しかし、フィク
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 脳の動作原理
https://youtu.be/8rUDMeoQvWE https://
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 ミラーニューロン
https://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_t
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-
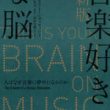
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
観光学が収斂してゆくと思われる脳科学の動向(メモ)
◎ 観光学が対象としなければならない「感情」、「意識」とは何か ①評価をする「意識」とは何か
-
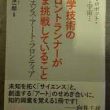
-
冒険遺伝子(移動しようとする遺伝子) 『科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること』川口淳一郎監修
P.192 高井研 ドーパミンD4受容体7Rという遺伝子 一時期「冒険遺伝子」として注目された
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
