「食譜」という発想 学士會会報 2017-Ⅳ 「味を測る」 都甲潔
学士會会報はいつもながら素人の私には情報の宝庫である。観光資源の評価を感性を測定することで客観化しようという提案をさせてもらっているが、味もしかりである。フードツーリズムを提唱する観光研究者に是非読んでもらいたい一文である。
なお、一昨日敬愛する農業学者の神門善久氏と久しぶりに話をした。氏は日本の農業をダメにしたのは消費者であり、消費者の味覚の劣化であると唱えられている。私も同感であるが、この一文を参考すれば客観化できるかもしれない。ただし、昔の日本人の味覚を示すデータがないので食譜の重要性を認識した次第である。
筆者は「味」は測ることができるのであろうかと問題を投げかける。語感のなかで視覚、聴覚、触覚は記録と再生ができ、結果コミュニケーション可能であるとされる。
なお、聴覚の方はレコードとNHKが民謡に普及に寄与したと観光では理解しており、民謡は古いものではないと私はりかいしていたが。
氏は、味覚と臭覚は不可能であるように思えると次に問題を投げかけ、「味覚センサー」の開発でかなり変わってきているという。
私たちが心に思い、言葉にする味は、五感が統合された感覚であり、主観そのものである。ところが下で感じる味はどうであろうか。味細胞は各味質に対応し分化している。そのため、味細胞から味神経、そして脳へ味情報が伝えられえる際に大きな信号処理はなされない。この事実は、化学物質に由来する味は、既に舌のレベルで決定しているということである。以上から「脳で感じる味」と「舌で感じる味」が違うことに気づかされる。味覚センサーはこの「舌で感じる味」を数値化するものである。
味には5つの基本味がある。甘味、塩味、苦味、酸味、うまみである。これに物理的感覚でもある渋味と辛味が加わる。辛味や痛みは温度感覚である厳密には味覚ではない。渋味は味覚と触覚の中間の味と考えられており、味覚では苦味に類する。
味覚センサーは今から30年近く前の1989年に発明された。ヒトの感じる基本味の数値化に成功している。化学物質ではなく味質に選択性を示すのである。
この味認識装置は多くの食品へ適用され、その味の定量化ならびに新食品の開発に利活用されている。
味覚センサーの電圧出力は味強度に変換されるが、その際、ヒトの識別能が化学物質濃度の1.2倍以上という性質を利用する。つまり、人は1.2倍より小さな違いを識別できない。アサヒスーパードライは苦味を抑制、その後の第三のビールはさらに苦味が抑えられ、酸味を増やした傾向にある。世界のビールを同様に測定したが、日本のビールの占める味の位置と大差ないことが判明した。「味を目で見る」とことができるのである。
味覚センサーに記録された味のデータベースは味の譜面「食譜」である。楽譜があるから二百年以上前のベートーベンを再現して聞くことができる。
日本航空の機内で提供されるコーヒーは、食譜により味を実現したものである
氏は「味覚センサーは日本で発明されたものである。これらのセンサーの作る日本発のデータベース並びに人の官能によるデータベースの共有は、新しい時代を予見させる。」と締めくくるが、官能のデータベースは、まさに感性のデータベースであり、感性アナライザーを用いた我々の実験が大きく採用されることが望まれる。
関連記事
-

-
【ゆっくり解説】【総集編】ガチで眠れなくなる「生物進化」の謎6選を解説/ミッシ ングリンク、収斂進化、系統樹、生命起源【作業用】【睡眠用】
https://youtu.be/ACEmkF1-g88
-

-
希望難民ご一行様 ピースボートと「承認の共同体」幻想 (光文社新書) 新書 – 2010/8/17
ピースボートというクルーズ旅行商品があり、かつて週刊誌にその悪評が掲載されたことがある。消費者保護を
-

-
QUORAに見る観光資源 日本から出たことがないのでわからないのですが、日本は本当に治安が良いのですか?松本 貴典 (Takanori Matsumoto),
日本から出たことがないのでわからないのですが、日本は本当に治安が良いのですか?松本 貴典 (Tak
-

-
サムスン、ヒトの「脳をコピペ」できる半導体チップの研究を発表
https://japanese.engadget.com/samsung-plans-to-c
-
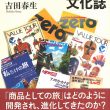
-
『パッケージツアーの文化史』吉田春夫 草思社
港区図書館の新刊本コーナーにあり、さっそく借り出して読んだ。JTBでの実務経験が豊富な筆者であり、
-

-
公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉 〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
-

-
現代では観光資源の戦艦大和は戦前は知られていなかった? 歴史は後から作られる例
『太平洋戦争の大誤解』p.183 日本人も戦前はほとんど知らなかった。戦後アメリカの報道統制
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな


