自動運転車の可能性『ロボットは東大に入れるか』新井紀子
自動運転車の可能性は、「自動」の定義にもよるが、まったく人間の手を借りないで運転することはかなり遠い将来である。高速道路等の道路と車が一体となって管理できるところから始まり、管理のしっかりした施設である、ホテルの駐車場等がその次に可能性が出てくるのであろう。従ってやはりシステムとしては鉄道に近いと考えた方がよさそうである。
その理由は、当分、人間の脳の解明ができない(数学でかけるか?)ということにあるからである。
新井氏や冷泉氏の著作、レポートでも記されているように、人間がかいた犬と猫のイラストはロボットは判別できない(写真等は判別できる)、道路上の「水たまり」「風に舞うゴミ」「昆虫の群れ」といった対象物を正確に認識する能力はない、といったことがあるからである。
『ロボットは東大に入れるか』(新井紀子著)メモ
人間の脳は数学でかけるか
入試 答えが決まっていたら、必ずできるか
ちゅーりんぐ 1 有限の知識 2特定の条件の下における特定の手続き 3同様に繰り返す なかでも3がポイント、パスカルも気が付いていた
ホッブスは、理性は足し算や掛け算のように計算ができると考えていた
ガリレオ 宇宙は数学という言葉で書かれている
ホッブスとは逆にデカルトは言語を話す機械は絶対にできない
意味を理解することは機械にはとてつもなく難しい
ロボットはイラストに弱い
写真は「この世界」をカメラという機械で「観測」した出力結果
イラストは人間の脳という「なんだかわけのわからないもの」を通って出力される
AI完全 計算機によって解くことが難しいとされている問題 例えば言葉を理解すること
逆に人間であるか否かを判定するCHAPTCHA スパム防止に用いる
アマゾンにメカニカルタルク 機械では難しい仕事を人間に安く外注する仕組み 犬と猫の判定は機械でできるが、かわいいネコの判定はできない
ソフトバンクのペッパーの「感情エンジン」は感情の理解というよりも感情の分類
東ロボが克服しなければならない最大の問題はあいまいさや常識 「岡山と広島に行った」 「岡田と広島に行った」
〇 冷泉彰彦 『from 911/USAレポート』 第772回
1番目は、自動運転車の実用化ですが、これは中身を知れば知るほど難しい問題であるということが分かって来ました。まず、グーグルやアップルが、アメリカの例えばカリフォルニアやアリゾナで走らせている「自動運転試験車」を見ていますと、いかにも「近い将来」技術的なブレイクスルーが起きるような印象を与えます。 ですが、実際はそんな簡単な話ではありません。例えば、この2018年の前半だけで、自動運転試験車が事故を起こしたり、あるいは簡易自動運転機能を誤解して機械に操縦を任せていたドライバーが深刻な事故を起こしたりという事件が複数起きています。 そうした事故の検証をして行く中で見えて来たのは、この技術の難しさということでした。例えば、現時点での自動運転車は「カメラ」と「ミリ波レーダー」そして「レーザー照射センサー」更には「超音波センサー」や「可聴音センサー」を使って周囲の状況把握を行うようになっています。 ですが、現在のAI技術は「人間のドライバー並み」の判断能力には至っていません。まず、降雨時や夜間には認識度が大きく下がります。自動車や標識、白線などは認識させるためのビッグデータができつつあるので、ある程度は理解できますが、例えば道路上の「水たまり」「風に舞うゴミ」「昆虫の群れ」といった対象物を正確に認識する能力はありません。
関連記事
-

-
錯聴(auditory illusion) 柏野牧夫
マスキング可能性の法則 連続聴効果 視覚と同様に、錯聴(auditory illu
-

-
動画で考える人流観光学 脳が心を生み出す仕組み 他者起源説
https://jinryu.jp/blog/?p=43483 ヒトの心はどのように生れ、進化して
-

-
動画で考える人流観光学 【コンテナホテル宿泊記】災害時は移動して大活躍
こうなると、自動運転機能が付随すると、社会は大きく変わるかもしれない。まさに、住と宿の相対化である。
-

-
動画で考える人流観光学 ものづくり 自動運転
https://youtu.be/mcvFGggt5-A ht
-
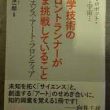
-
冒険遺伝子(移動しようとする遺伝子) 『科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること』川口淳一郎監修
P.192 高井研 ドーパミンD4受容体7Rという遺伝子 一時期「冒険遺伝子」として注目された
-

-
『ファストフードが世界を食いつくす』エリック・シュローサ―著2001年
ただ一つの言葉で言い表すと、画一性 トーマス・フリードマンは自著の『レクサスとオリーブの木』
-

-
『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハー
-

-
Mashuup Ideathon 感情系API特集 のイベントに参加して 2016年8月9日
表記アイデアソンというイベントの勧誘があり、今まではあまり興味がなかったが、感情系APIがテーマとい
-

-
自動運転時代のアルゴリズム 自家用車優先思想の普及と道路運送法の終焉
自動運転車の技術的問題は別稿で取り上げているが、ここでは道路使用の優先度の問題を考えてみる。
-

-
『脳の誕生』大隅典子 Amazon書評
http:// www.pnas.org/content/supp1/2004/05/13/040


